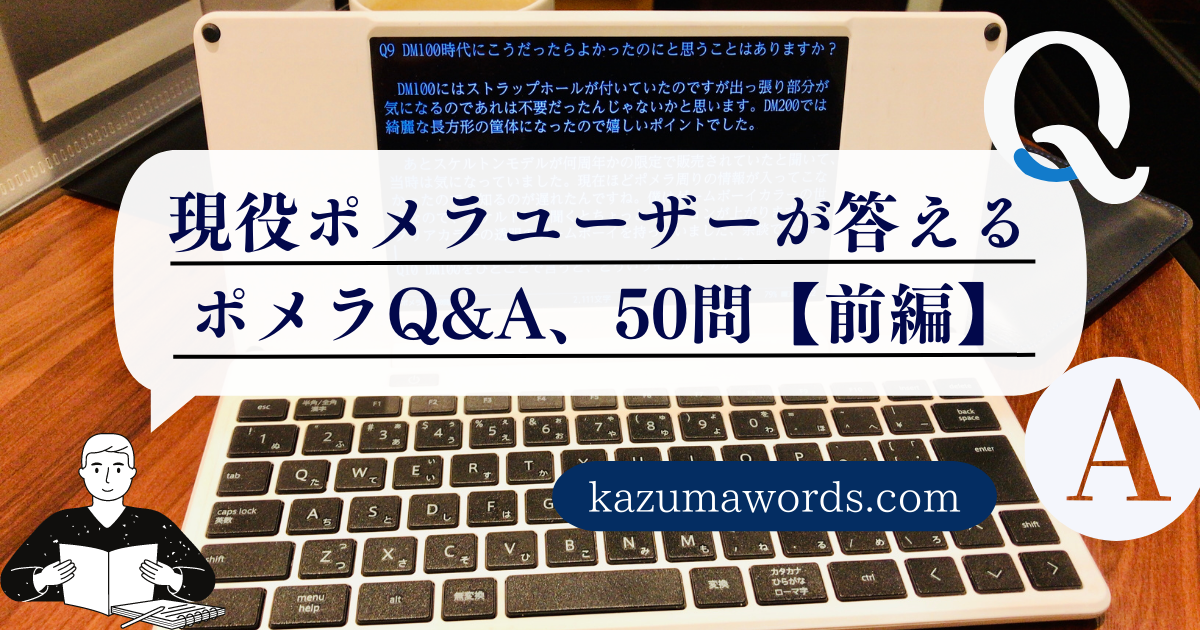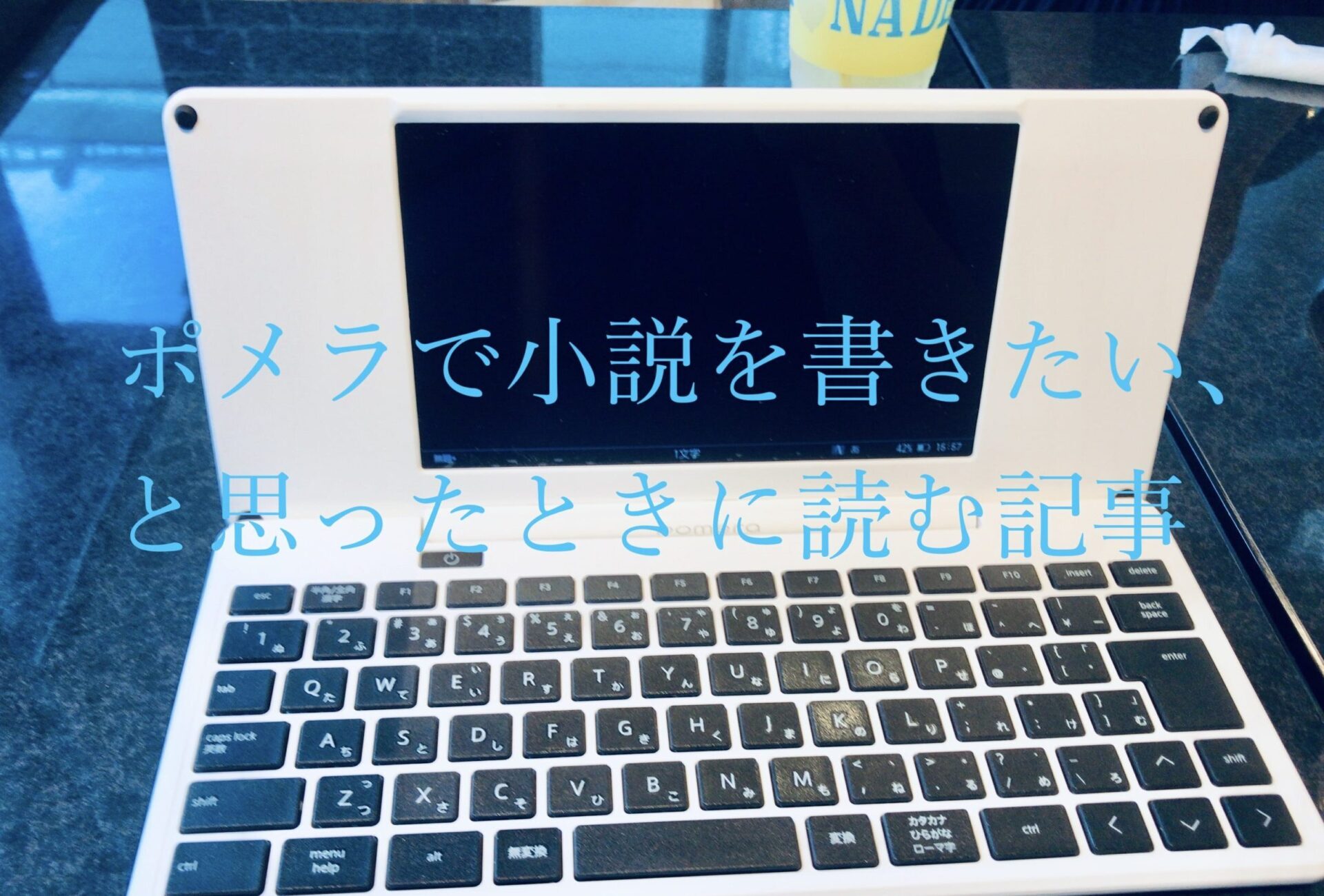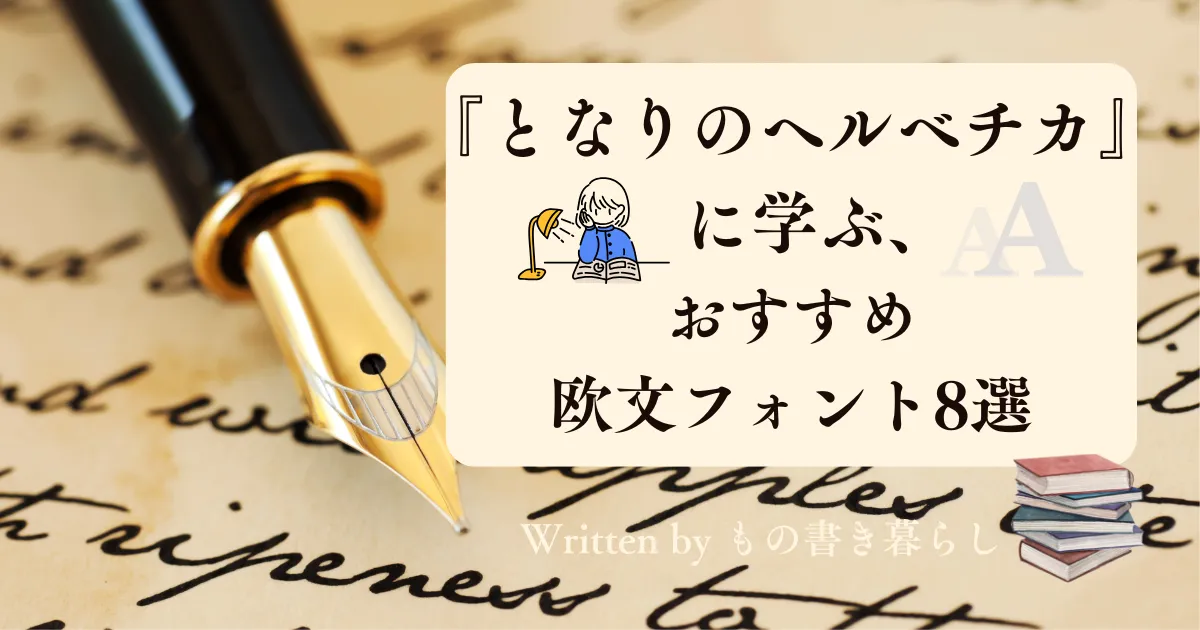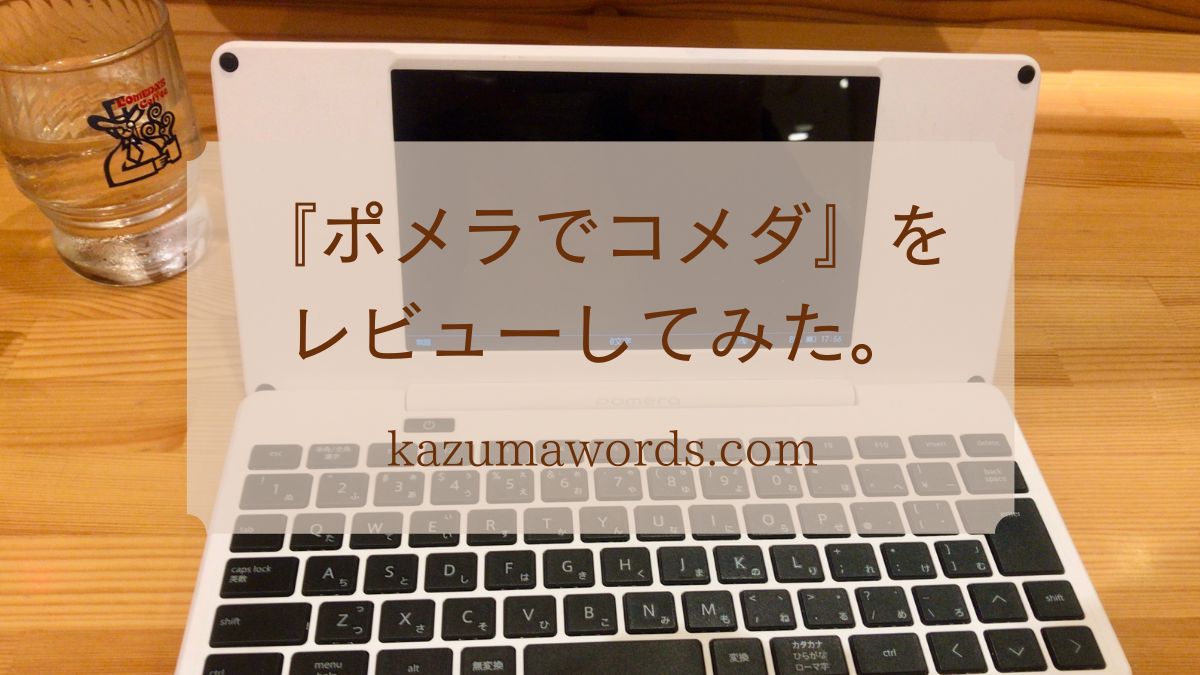村上春樹『職業としての小説家』に学ぶ、オリジナリティの創作術

小説の書き方に迷ったら手に取りたい本

皆さんは小説を書くとき、何を頼りに文章を書いていますか?
書き方に迷ったときに書店へ行くと、「小説の書き方」というタイトルの付いた本を目にすることもあるかもしれません。
作家志望の方がよく手にする本として有名なのが、国内だと保坂和志さんが書いた「書きあぐねている人のための小説入門」、高橋源一郎さんの「一億三千万人のための文章教室」。
海外では、バルガス=リョサの「若い小説家に宛てた手紙」、パトリシア=ハイスミスの「サスペンス小説の書き方」などがあります。
このなかのいくつかの本は、文学ブログ『もの書き暮らし』でもご紹介してきました。
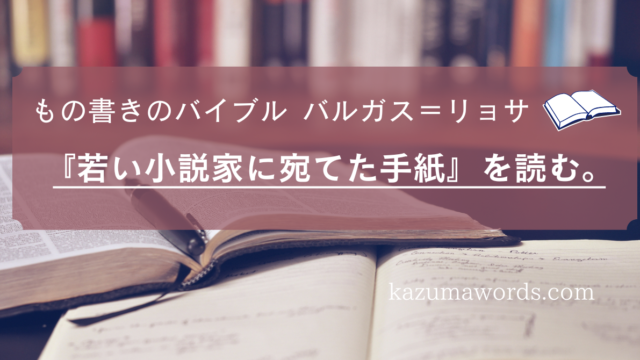

小説の書き方というのは、おそらく厳密に言うとその人自身が見つけるしかないもので、教えたり、教わったりすることのできないものです。
一方で、「書くための手がかりになる本」はあるんじゃないかと思っていて、僕も何冊かそういう本を探して手元に置いています。
そのなかでもとくに、小説を執筆するときの姿勢から、「何を書くのか?」というところまで、出し惜しみせずに書かれた本として、村上春樹さんの『職業としての小説家』が印象に残っています。
今回は『職業としての小説家』から、ものを書くときのヒントを探してみます。
では、さっそく中身について見ていきましょう。
村上春樹『職業としての小説家』の概説

『職業としての小説家』は2015年にスイッチ・パブリッシングから発売された本で、現在は新潮文庫で文庫化されています。
「あとがき」にもあるように初出は、翻訳文学を紹介する雑誌として有名な『MONKEY』で2013年~2015年に掛けて連載されていました。
本書の1章から6章がMONKEYに掲載され、7章から12章は本書のために書き下ろされたものです。
とくに前半部の1~6章は、村上さん自身が雑誌掲載前から書き溜めていたという文章で、小説の執筆に関するコアな部分は、実はこの前半部に書かれているのではないかと僕は思っています。
今回、取り上げるのは第四章「オリジナリティーについて」です。
第一章~第三章には、村上さんが作家になるまでの生い立ちと、どういう経緯で職業作家になったのかという裏話が書かれています。
ファンの方にとっては待望の章ですが、村上さんにとっての個人的な経験が含まれているため、小説を書こうとしているすべての人に当てはまる内容かというと、ちょっと毛色が違う気がします。
たとえば、村上春樹さんが小説を書こうと思ったのは、明治神宮でヤクルトスワローズの試合を観ていたときで、デイブ・ヒルトンがツーベース・ヒットを打った瞬間に、小説が書けるかもしれないと確信されたそうです。
村上さんはそれを「エピファニー」と呼んでいますが、こういうことは誰にでも起こるわけではなさそうです。ある人にはあるだろうし、ない人にはない。
一方、第四章~第六章は、小説を書くための具体的なところに踏み込んで書かれてあると僕は感じました。今回の記事では「第四章 オリジナリティーについて」に絞って取り上げます。
作家のオリジナリティとは何だろう?

あらゆる芸術表現に言えることですが、作品には作家固有の表現が含まれていなくてはならない、とよく言われます。
小説だと「文体」で、言葉の選び方や間の取り方、文章の流れなどを見たときに、「これはこの人の表現だ」とはっきり分かるのが作家のオリジナリティーとも言えるでしょう。
村上さんはオリジナリティーについての話をするときに、ビートルズやビーチボーイズの音楽を例に持ち出してこう仰っています。
今にして思えば、要するに彼らは優れてオリジナルであったわけです。他の人には出せない音を出していて、他の人がこれまでやったことのない音楽をやっていて、しかもその質が飛び抜けて高かった。彼らは何か特別なものを持っていた。それは十四歳か十五歳の少年が、貧弱な音の小さなトランジスタ·ラジオ(AM)で聴いても、即座にぱっと理解できる明らかな事実でした。とても簡単な話です。
『職業としての小説家』村上春樹著 新潮文庫(2016)p.90~91
ビートルズのどこがどう優れているのか、というのは言語化するのは難しいけれど、「凄い」っていうのは、一度聴けば分かることですよね。
現代ではビートルズの音楽は、「既に価値が決まっているもの」として世に認知されていますが、おそらくリアルタイムの世代で聴いていた方は、もっと衝撃を感じて聴いていたはずです。
作家や作品が「オリジナル」であることの定義
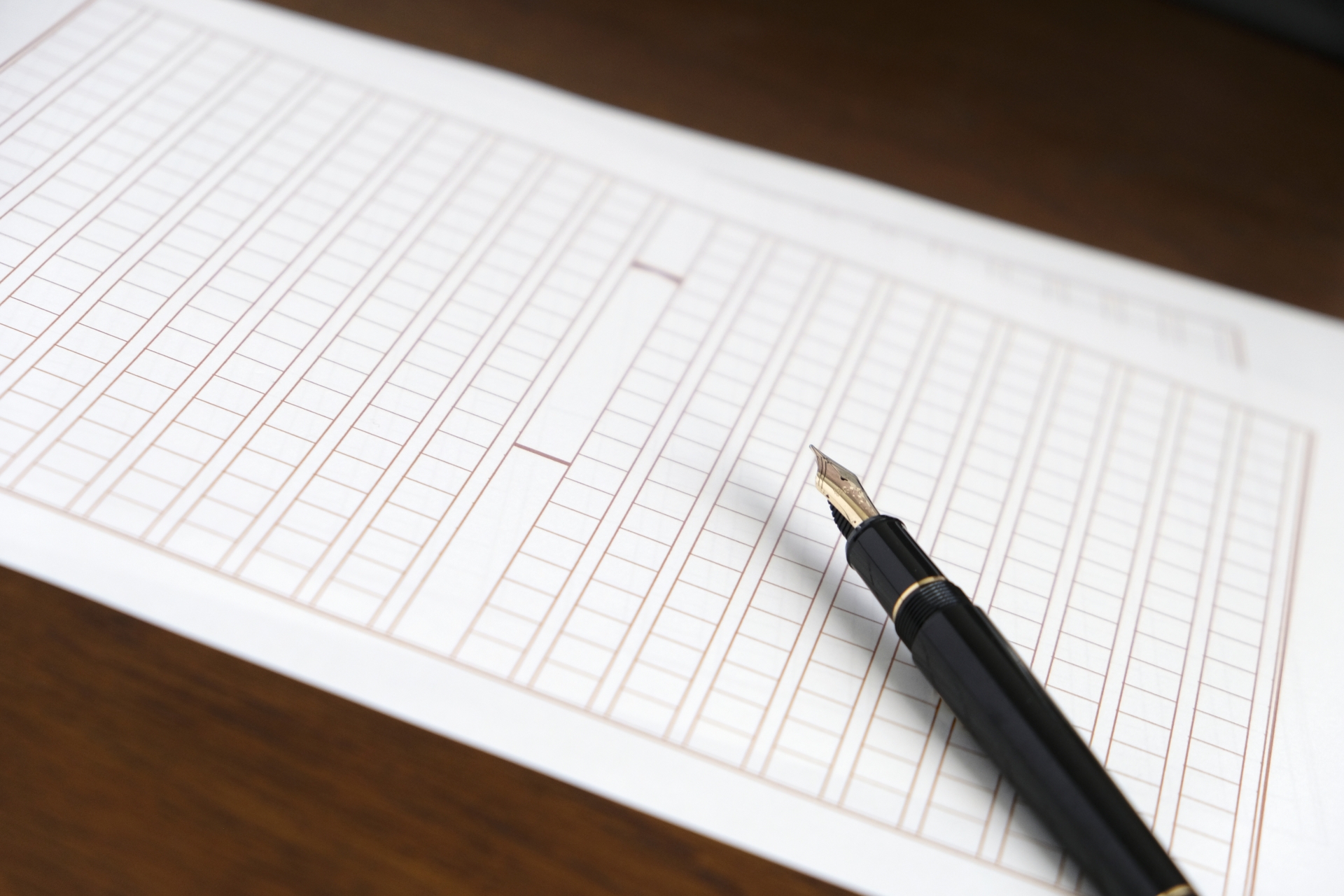
僕なりに、オリジナリティの定義をちょっと簡単にまとめてみると、
①他の人が真似できない表現が含まれていること
②前衛的であること(まだ誰もやったことがない表現であること)
③十五歳の少年少女が作品を前にして明らかに「すごい」と分かるもの
これは本文からゆるく定義したものですが、村上さん自身の定義はこのようになっています。
僕の考えによれば、ということですが、特定の表現者を「オリジナルである」と呼ぶためには基本的に次のような条件が満たされていなくてはなりません。
(1)ほかの表現者とは明らかに異なる、独自のスタイル(サウンドなり文体なりフォルムなり色彩なり)を有している。ちょっと見れば(聴けば)その人の表現だと(おおむね)瞬時に理解できなくてはならない。
(2)そのスタイルを、自らの力でヴァージョン・アップできなくてはならない。時間の経過とともにそのスタイルは成長していく。いつまでも同じ場所に留まっていることはできない。そういう自発的・内在的な自己革新力を有している。
(3)その独自のスタイルは時間の経過とともにスタンダード化し、人々のサイキに吸収され、価値判断基準の一部として取り込まれていかなくてはならない。あるいは後世の表現者の豊かな引用源とならなくてはならない。
村上さんは作品がオリジナルであるかどうかの要素に「時間の経過」が関わっていると言います。
この辺りが村上さんの哲学とも言える部分ですが、その作家がオリジナルであるかどうかは時間が証明する、と。
当たり前の話ではありますが、作者が自分の作品をいくら「オリジナル」だと声を大にして叫んだところで、自作がオリジナルだと言えるわけではありません。
その作品が「オリジナル」かどうかを決めるのは、作品を読む読者に委ねられています。
作者が、オリジナルであると判断するためには、ある程度のかさ(分量)の作品が必要だと村上さんは言います。
ベートーヴェンを評価するには、交響曲が一曲だけでは作品が立体的に見えてこず、第一~九番まで作り上げたからこそ、第九番の価値が分かる、というわけです。
ただいっとき世間の耳目を引くような作品が作れたとしても、それだけでオリジナルと呼べるわけではなく、職業作家としてオリジナルでありつづけるためには、まだやったことのない表現方法に挑戦し、バージョンアップ(変化)し続けなければ、オリジナルとは呼べない。でなければ、ただの「一発屋」で終わってしまう。
この定義を噛み砕いていくと、「作家としてオリジナルであること」の定義はかなり厳しいものとなっています。
この本のタイトルは「職業としての小説家」なので、「職業作家」としての「オリジナルの定義」とはどういうものか、プロ中のプロと同じ目線で語ってくれているわけです。
たとえ、この本を手に取る読者がまだ小説の素人であったとしても、そこに忖度や手加減はありません。
とはいっても、小説を一度書こうとしたことがある方なら分かるはずですが、オリジナルな作品をたったひとつ作るのだって苦労するはずです。
僕も十年くらい書いて、まともな小説ひとつこさえることもできませんでした。小説家にはなれなかったので、僕の職業はライターやブロガーになりました。
小説を書きたいひとのお手伝いができればと思って、『もの書き暮らし』のブログを運営しています。
「オリジナル」な小説とは、どのように書かれるのか?

話が逸れましたが、では、オリジナルな作品とはどうやって書けばいいのでしょうか?
村上さんは、「どういう小説を書きたいか?」は最初からはっきりしていたと言います。
そしてオリジナルな文体や話法を見つけるためのヒントをいくつか提示されています。
自分のオリジナルの文体なり話法なりを見つけ出すには、まず出発点として、「自分に何かを加算していく」よりはむしろ「自分から何かをマイナスしていく」という作業が必要とされるみたいです。
『職業としての小説家』村上春樹著 新潮文庫(2016)p.107-109
村上さんが『風の歌を聴け』で「群像」の新人賞を取ったとき、「小説とはこのように書かなくてはならない」という制約(思い込み)もなく、当時の文芸の状況も知らず、モデルとするような先輩作家もおらず、ただ「そのときの自分の心のあり方を映し出す自分なりの小説が書きたかった」と本書のなかで語っておられます。
「小説を書くときに、その行為を楽しめるかどうか(それをしているときに、あなたは楽しい気持ちになれますか?)」というのをひとつの基準にする、と村上さんは言います。
日常生活で抱え込んでいること、悩んでいることは、小説を書くときには一旦まるっと脇に置いて、自分の楽しさや喜びを見いだせる文書を書くこと。
というのも、自分が求めていることを書こうとすると、話は避けがたく重くなってしまい、自由に創作ができなくなってしまうから、という理由が挙げられます。
僕は思うのですが(というか、そう望んでいるのですが)、そのような自由でナチュラルな感覚こそが、僕の書く小説の根本にあるものです。それが起動力になっています。車にたとえればエンジンです。あらゆる表現作業の根幹には、常に豊かで自発的な喜びがなくてはなりません。
『職業としての小説家』村上春樹 新潮文庫(2016)p.111-112
「何も求めていない自分」から出発すること

僕が作品の「オリジナリティ」について考えるとき、最もヒントになると思われる箇所は以下の部分です。
これはあくまで僕の個人的な意見ですが、もしあなたが何かを自由に表現したいと望んでいるなら、「自分が何を求めているか?」というよりはむしろ「何かを求めていない自分とはそもそもどんなものか?」ということを、そのような姿を頭のなかにヴィジュアライズしてみるといいかもしれません。
『職業としての小説家』村上春樹著 新潮文庫(2016)p.112
村上さんは、小説を書くときに、自分が「何を求めているか?」と問うよりも、「何も求めていない」自分を想像してみるといいと勧めています。
これを僕なりに解釈してみます。(以下の部分は管理人の考えを含みます)
たとえば小説を書く時って、「自分が人生で求めてきたもの」や「常日頃から思い悩んでいること」を、小説の中に反映させてしまいがちです。
とくに作者と作品のなかの登場人物が近すぎるときってけっこうあるんですよね。小説が自分にとって大事なものだと考えていればいるほど、ひとつの小説のなかに自分の悩んできたことをすべて入れ込もうとしてしまう。
あれもこれもと、自分で経験したことのすべて(総体)を小説という容れ物に入れようとしたって無理なんです。だってそれはただの文字で、ただの小説なんだから。一人の人間の人生が経験したこと、感じたこと、考えたこと、思い悩んだことが、たったひとつの小説に収まるわけがない。
だから、自分の人生で経験したことが、小説を書くときにかえって邪魔になる場合がある。
たとえば、書き手である僕が過去の経験から「家族のことが嫌い」だったとします。だからといって、「家族が嫌いだ」ということを延々と物語のなかに籠め続けたってやっぱり物語としてはどうにもならない。嫌なことについて書いているんだから、物語が楽しくならないのは当たり前です。
それを書いているときに書き手が「楽しい」と思えるなら、まだ見込みはありますが、こうした身の回りのことをつらつらと書きはじめると、作者が先入観を持ってしまって、さきほどの例だと、書くときに「家族=悪」という簡単な図式に当て嵌めてから作品を作るようになります。
するとどうなるかというと、登場人物が偏ってきて、作者にとって都合のいい言葉ばかりが並んでいくわけです。それを赤の他人が読んでもあまり面白いとは言えない、独り善がりな文章に近づいていきます。簡単に言うと、現実との接点を失ってしまうんですね。リアリティが欠けていく。
日本の昔の小説は、「私小説」といって、身の回りのことから描きはじめるのが主流でした。この「身の回りで起きた出来事」に価値判断を下さないまま、小説の中で描くことってかなり難しいんです。どこかで自分を俯瞰して見るような、自分で自分を突き放すような書き方ができないと難しい。
だから、自分の人生で経験したこと、思い悩んだことから一旦離れて、書いていて楽しいと思える物語を想像してみる。
そのストーリーを想像するために、妨げになるような人生の経験は、小説を書くときには忘れる。そういった経験は、自由に小説を書くときの足枷になってしまうから。
経験をマイナスするとは、そういう意味だと僕は解釈しました。
忘れるって言ったって、べつに「作者がそのことをほんとうに忘れる」わけではないので、たぶん好きなことを書いていてもふとしたときに出てくるんですよね。そういう自然な表現の方がいいのではないか、という提案です。
作者が作者自身の人生に引っ張られずに小説を書けるようになれば、書き手の想像力の足かせになっていたものが外れて、より自由にのびのびとした表現ができるようになる。
そうすれば、そこにオリジナリティは自然と宿る、というのが、村上流の「オリジナリティ」の創作術、と言えそうです。
もの書きに迷ったら、村上春樹『職業としての小説家』を読む

今回は、村上春樹さんの著書『職業としての小説家』から、作品のオリジナリティについて解説してみました。
ブログでのご紹介は、かなり要約したもので、本書のたった一箇所にしか過ぎません。ものを書きたいという方には、もっと沢山のヒントがこの本のなかに詰まっています。
小説を書きたい、という人は、『職業としての小説家』をぜひ手に取ってみてください。
僕がはじめてこの本を書店の店頭で手に取ったとき、村上さんからの「小説を書くための招待状」のように感じました。
創作で行き詰まったときに、お守りとして手元に置いておきたい一冊です。
kazuma
余談:
noteでは、もの書きの日常を綴った「ポメラ日記」を連載しています。最近、SNS(Twitter)を止めて、自分のための時間に充てるようになったので、それについて書いています。
monogatary.comの文学賞に応募した件(「51対49の小説」)は、選考落ちでした。応援してくださった方々はありがとうございました。めげずに創作を続けます。近況などを近いうちにポメラ日記に綴ろうと思っています。