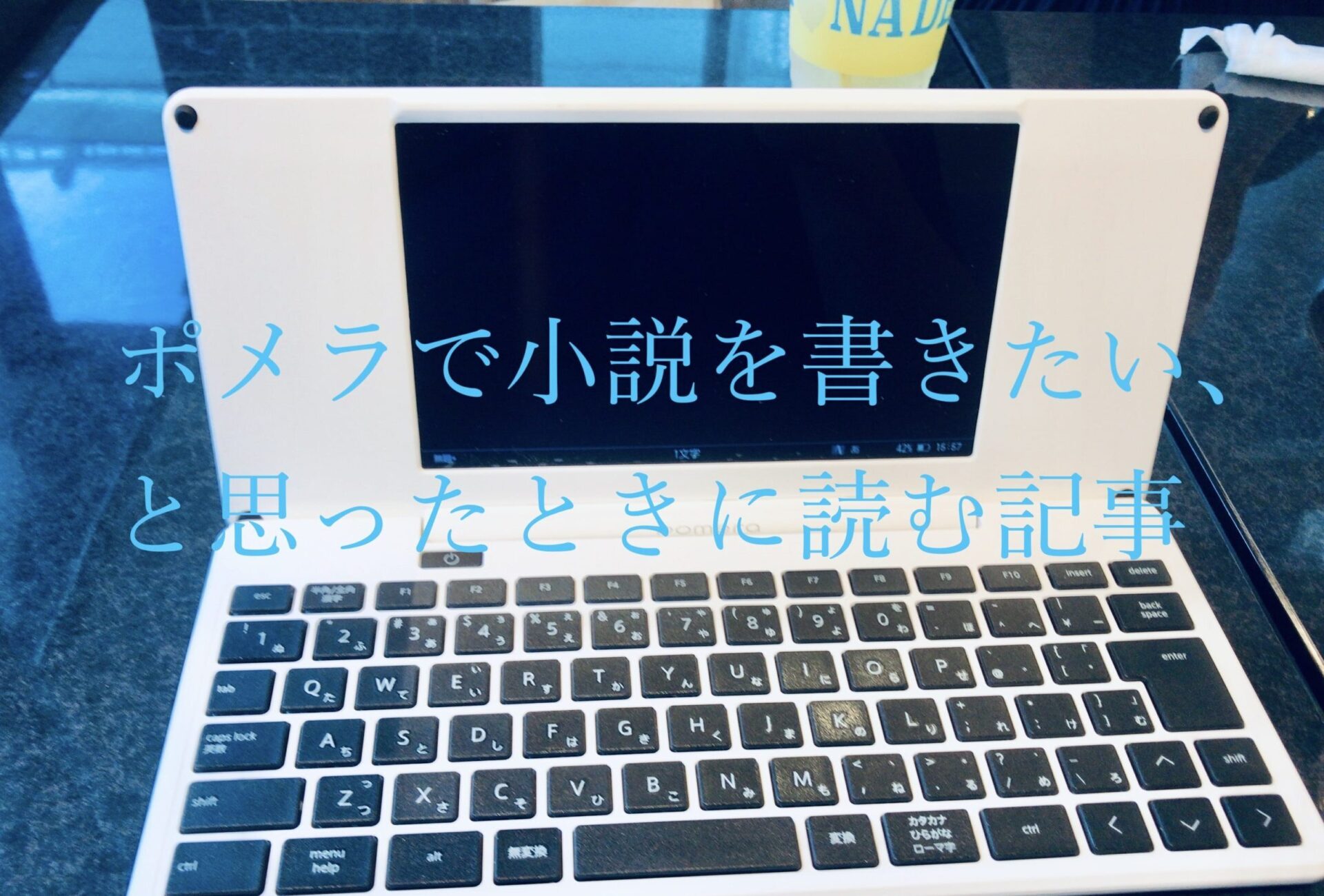「夏目漱石の『門』を読みながら考えたこと」
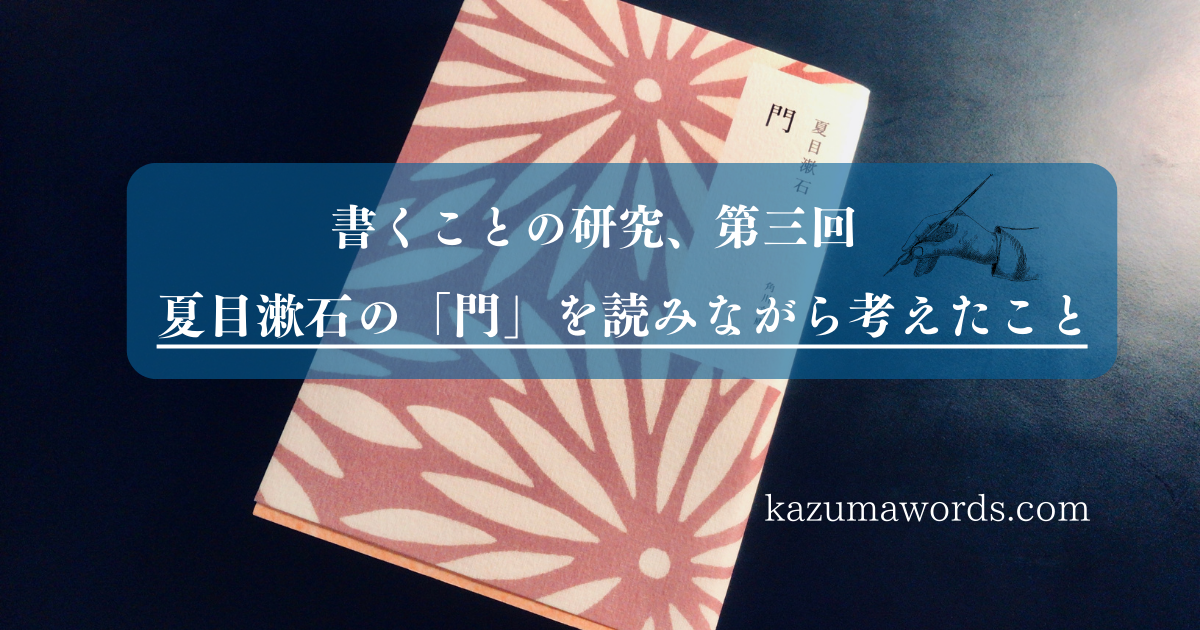
夏目漱石の『門』を持ち歩いて
夏目漱石の『門』を持ち歩くようになった。といっても、まだ読みはじめたばかりで、冒頭の数ページを行ったり来たりしている。
これまで本を読むときは、読み終えた箇所には戻らずに一筆書きで読んでいたのだけど、何だかちょっと学生の頃よりも頭に入りづらくなっているので、どこまで進んだっけと思って、数ページ前から読みはじめることが多い。
この作家はどういうことを考えてこの文章を書いているか、なぜここでこの表現を使っているのか、とちょっと立ち止まって考えてみたりしている。
漱石の『門』の最初の箇所を読み始めた印象としては、漱石の小説に出てくる登場人物ってわりと街中をぶらぶらと歩いたりしていることが多いなと思った。なんというか、風景が流れていくのをゆったり眺めている感覚がする。物語のなかの時間の流れが遅く感じる。
漱石の小説の「間」、手の内を見せないで進行する物語
主人公の宗介はどうも弟の小六から用事を頼まれているらしいのだが、どうも腰が上がらないらしく、ようやく出かけたと思ったら、切手と「敷島」の煙草を買って、そのまま散歩をはじめる。
漱石は小説のなかでそれぞれのシーンにけっこう間を取るタイプみたいだ。そして読者が気が付かないうちに自然な会話や風景描写の流れのなかで、物語の駒を進めていく。その歩みは牛歩のようにゆっくりなのだけど、宗介や妻の語っていることは、そのシーンを通り過ぎてみると、どうも気がかりになってくる。
たとえば冒頭のシーンで、宗介は「近江(おうみ)」の「おう」の字がよくわからないと言って、裁縫仕事をしている細君に尋ねている。妻はそんなことは大して気にも留めていない風で、天気の話をしようとしているのだが、宗介は噛み合わないように、まだ字のことが気に掛かっている。
しまいには、字がその通りには見えない、まったく違った風に見えることがあると話すが、妻は取り合わず、それは神経衰弱のせいじゃないかと話した宗介に同意する。
その時点では何の意味があるのかは分からないが、どうも匂わせるような会話が続いていくのである。宗介はこの後も、何かにつけ小六の用事を済ませるのはどうも気が進まないといった具合で、先延ばしにし続ける。
なぜなのかは、そのシーンからは分からない。漱石は読者に手の内を隠しながら物語を進行させる癖があるように思う。大事なことは言わないまま、その表層だけを読者に提示して、日常を描いていく。
その日常は非常にゆったりと流れているように見えるんだけど、それは氷山の一角であって、その下では全然別のテーマを進行させている。
延々と日常について語っているようでいながら、それはただの表向きの顔で、ポーカーフェイスで読者を欺いているところがあるなというのは感じられる。
「間」の取り方は、文体にも繋がっている?
漱石の作品を読んでいて思うのは、その作家ごとによって独特の間の取り方があるんだろうなと思う。
たとえば僕の好きなサリンジャーなんかは、一度エンジンが掛かると、平気で読者を置き去りにする。バナナフィッシュなんかがいい例だ。最初から読者に分からせるつもりなんかないし、ついてこれるとも思っていないような書き方をする。
実際、気が付いたときにはシーモアはピストルの引き金を引いていて、彼はなぜ死んだのか、という謎だけが残って読者は途方に暮れる。でもその終わり方が美しいと感じられるのはなぜだろう。
カポーティの場合は、余計な間というのがまったくなくて、出来事が流れるように切れ目なく続いていくという印象がある。
それも小説全体として見たときにいいテンポだったなあと思うのではなくて、一文一文、ワンセンテンスの単位で、きっちり照準を合わせてくる感じがする。
カポーティの短編を読むときは他の小説に比べて引き込まれるのが早い。エンジンが掛かったことにも気が付きませんでした、というくらい滑らかに発進して、読者に色んな美しい光景を見せてドライブし、結末に来ると滑らかに車庫入れする。
こんなひとが運転する後部座席に乗るのはきっと楽しいだろうと僕は思う。
こういう間の取り方っていうのは、文体とも関係が深い気がする。もし他の誰にも似ていない、自分の間というものを小説のなかで展開できたら、そのひとのシグネチャーというか、専売特許になるだろう。
たとえば、カズオ・イシグロが語るときの間ってちょっと他のひとには真似できないところがあると思う。僕は翻訳で読んでいるから、翻訳者の文体によるところもあるんだろうけれど、あれだけゆっくり構えて登場人物の台詞を引き出してきたり、抑えたトーンのまま迫ってくる感じは、ちょっと他にはないなって思う。
日本文学に詳しいわけではないけれど、梶井基次郎の『檸檬』のリズムはかなり自然に感じる。「えたいの知れない不吉な塊」に押さえつけられた「私」がとつとつとひとりで語りはじめる、あの感じ。
独白なんだけれど、決して誇張されるわけでもなく、京極の街をひとり軽やかに下って行くときの歩幅。
檸檬を丸善に置いていくときは快活に、果物屋の人参葉や慈姑を眺めるときはゆったりと。街中を歩く足音まで聞こえてくるような文章で、ああいうのが理想じゃないかな。
書き手のオリジナリティは言葉になる以前のもの
文章の間の取り方っていうのは、作家のリズム感というか音楽的なセンスと結びついていると思う。作家に必要なのは決して意味の通る文章が書けるという能力だけじゃなくて、そういう他の素養が関係しているんじゃないか。
村上(春樹)さんは、ジャズ音楽を愛好していて若い頃はジャズ喫茶まで開いたりしているけれど、言葉にならないところで文章のテンポに影響していると思う。文章の内容って伝えることだけに徹したとしたら、ある意味では誰が書いても似通ってくる、無味乾燥なものに近づいてくると思う(僕はライターをやっていて実用文を書くときにそのことをつくづくと感じている)。
そこで他人と差を付けようとするのは難しくて、文体のなかにオリジナリティが認められるとするなら、その言葉になる前の要素――たとえば、作家の文章の流れ、呼吸のリズム、言葉の語感、書き手のなかで発声する前に行われる一瞬の取捨選択、『あれは言って、これは言わない』――に依っていて、それは単に論理的な文章を書くときには使われることのない、作家の生得的なものが現れるときに、独特の間合いが生まれるんじゃないかと思っている。
そう考えてゆくと、書き手のオリジナリティというのは、書くことそのもののなかにあるというより、書く以前に作家が持っている身体的な感覚やリズムと結びついていると言えそうだ。
バイオリンを演奏するときも、そのまま弓を弾いても音は鳴らない。でも段々と弾き込んでいくと、そのバイオリンそのものが持っていた独特の音色が鳴るようになる。
バイオリンの形は定まっているんだけど、実はそれぞれに個体差があって、そのバイオリンだけが持っている位置に指を置いて、弦を弾くと、他のバイオリンではそういう風には鳴らないはずなのに、その個体だけは鳴る、というポイントがある。
書きながら探さなくてはいけないのはそういうポイントで、他のひとでは語り得ない、自分だけが持っている声がどこにあるか、どうすればそれを物語のなかで最大限に引き出すことができるか、探り当てる必要がある。
僕がこれまでの短編で書く度に人称を変えたり、語る人物の立ち位置を変えていたりしていたのはそういうわけで、どうすれば読者のいる観客席まで言葉を響かせることができるか、その耳元まで音を叩き込むことができるか、どこに自分の声があって、どこにないのか、というのを試していた。
もしそのポイントを探り当てることができたら、あとはその声が一番響くような語り方を探そうと思っていた。
いままで小説は物語として楽しんできたことが多かったので、こういう風に、一箇所ずつ感想を確認しながら書いてゆくのは面白い。
内容を味わうというよりは、作家の裏手側に回ってその仕組みや原理みたいなものを解釈できるようになったらいいなと思う。今日はその練習としてやってみた。
書くことの研究、第三回はこれにて終わり。
2022/12/14 16:40
kazuma
余談:『サマータイムレンダ』というSFループもののアニメをときどき観たりしているんだけど、そのエンディングテーマで流れているcadodeというアーティストの曲が気になっている。まだそれほど注目されていないみたいだけど、語感というかリズム感がよくてずっと聞いていられる。執筆後の休憩に聴いたりしている。