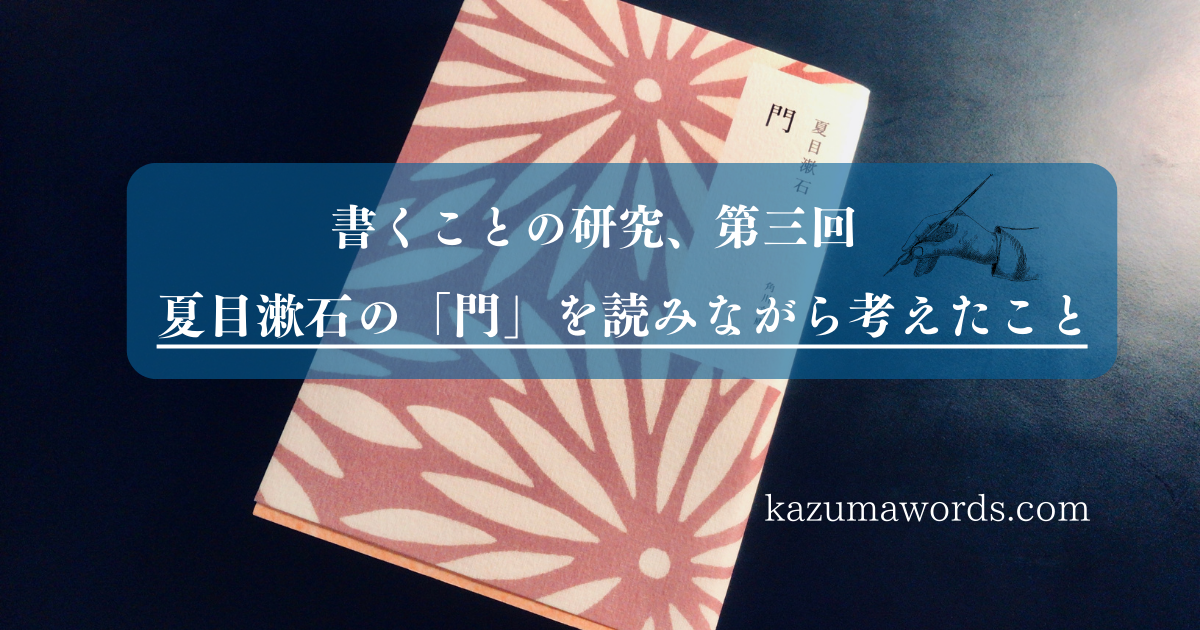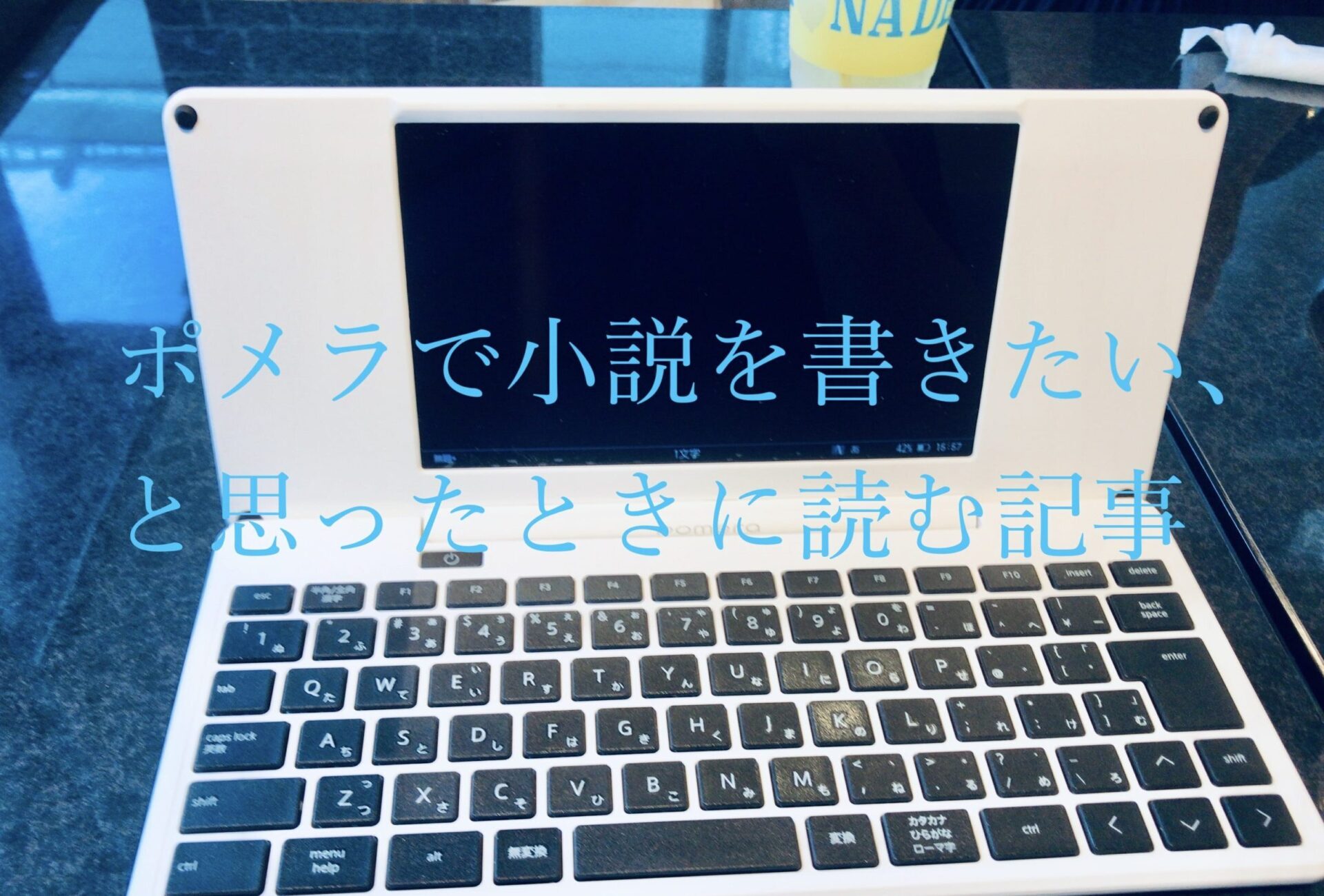「ポメラ日記16日目(タネも仕掛けもない小説を書くことについて)」

喫茶ポメラ、デビューしました。
・今日は金曜日(執筆時)で作業が終わったので、喫茶店に来てみた。近場にはあまり空いているところが少なかったので、ちょっと歩いて隣町まで来ている。
普段は在宅なので、外に出て歩くという機会がなくて、歩くのもいいだろうと思った。
喫茶店に辿り着くまでに二十分くらいあった。その道中で書くことを考えたりしながら、席に着いた。
ずっと週五日、ノートPCの前に張り付いて書くというのは中々精神的につらいものがある。やはりポメラを持ち出して外で書くというのはいい習慣だと思う。
歩きながら書くテーマを決めていたら、その時間も無駄にならない。帰りに買い出しも済ませれば、また執筆や読書に使える時間が増える。
在宅のひとにはぜひお散歩ポメラを推奨したい。「街歩き×ポメラ」はかなり相性がいいと思っている。
僕にコミュニケーション力があったら、「お散歩ポメラの会」を立ち上げたいくらいだ。とりあえず喫茶ポメラ、ソロデビューしました。
ついに喫茶ポメラデビューしてしまった。街中ポメラ、色々回りまくったので、ありがたみがよく分かる。ちゃんとしたテーブルがある、雨に濡れない、虫もいない、コーヒーもある。快適。#喫茶ポメラ #街中ポメラ pic.twitter.com/4aVnrfunf0
— kazumawords. (@kazumawords) September 9, 2022
次に応募する公募について考えていること
この一週間、どの公募に出して書いていくか、それとも個人的に書いていくか迷っていたが、前から気になっていた文藝賞に応募してみようかなと思っている。期日に間に合えばだけれど。
12月末が短編賞の応募期限で、長編はいつも通り3月末になっている。公募がメインというよりかは、あくまでも腕試し、記念受験くらいのつもりで。
いま読んでいる本について
いまはカズオ・イシグロの「わたしを離さないで」を読んでいる。もうひとつ読んでいる本は、「歩道橋の魔術師」という本だ。これは知り合いのところに寄ったときに貰った。
以前行った郊外の図書館がよかったので、また行こうと思っている。その時に見つけた芥川選の怪異・幻想譚もかなり気になっているのだけど。いまは読書の時間を見つけるのが課題。本はライターの仕事がはじまる前の時間で読むようにしている。
最近は作品を作るために読書するようになった。
「君は花束を忘れた」を作ったときは、話の順序や登場人物の置かれている立ち位置が読者にはっきりと分からなくても成り立つものを作ろう、と考えて文章を書いた。
昔は、自分の興味に従って純粋にものを読んでいたのだけど、いまは書いているものに役立つ本を自然と探して棚の中を目で追いかけている。
カズオ・イシグロの本はどれも話の骨組みがしっかりしていて、読みながらこういう風に書くのかと参考にしている。
もちろん、同じように書けるわけはないし、書く必要もないのだけど、自分だったらどうするか、ということを考えながら読むようにしたいと思っている。
僕がいま目指している書き方について
同じ語り方を目指しても二番、三番煎じにしかならないので、亜流となるのではなくて、独自の路線を見つけたい。
誰もやったことのない書き方で書くというのが、純文学路線のひとつの要素としてあると思うけど、そこに自分のトーンを乗せて物語を書けるようになったとしたら、たぶんはじめて作品として成立するようになるんじゃないかと思う。
とはいえ、僕が考えたことくらい、当然、古今東西の作家たちはとっくに考えているはずで、新しさなんてもう出尽くしたと言われている小説で、どうやって立ち回りを演じるのか。
十年書いてきてよかったことは、たぶん無意識ながらに書き続けてきたことで、作品ごとに僕のカラーというか書きたいものをなんとなく掴んできたことだ。
小説の中で描きたいイメージを羅列する
僕が小説の中で描きたいイメージを簡単に羅列すると、
・現実をベースとしながら、現実にはいない奇妙な人物やシチュエーションを用意し、その中で語ること
・モノトーンの景色を描くこと
・タネも仕掛けも「ない」小説を書くこと
現実をベースとしながら、現実にはいない奇妙な人物やシチュエーションを用意し、その中で語ること
物語が現実の地平から離陸する瞬間に、僕の想像力はもっともうまく働く気がしている。それが僕にとっては一番物語になりやすい形(十八番)と感じている。
小説の中で非現実の要素を持ってくるためには、リアリスティックで強固な土台がなければならず、それが裏打ちされていればいるほど、ちゃんと離陸することができるようになる。
どうやって飛ぶのか、いつ、どのタイミングで離れるのか、その飛び方を小説を作るときに考える。
モノトーンの景色を描くこと
これは僕の心象風景が基本的にそういうものであることに由来する。作品から鮮やかな色彩を感じ取る、という感想を貰うことはほとんどない。
文学学校でも作品について、モノトーンですねと言われたことがある。四六時中、壁とディスプレイに向かい合って文章を書いているやつだから、そうなるのは致し方ない。
これを逆手に取って、物語に活かせないかと思った。現実で景色がモノトーンに見えることはまずない、けれどそういう風に感じ取られることはある。
幻想的なシーンを書こうと思ったら、却ってこのモノトーンな書き方は利用できるのではないかと思う。
現実にはない無機質な描写、登場人物の孤独やかなしみを表現するのにいちいち極彩色の絵筆はいらないのだ。たぶん墨と余白があればそれで十分ではないだろうか。
タネも仕掛けも「ない」小説を書くこと
物語の順序や登場人物の動機が分からなくても表現として成り立っているものを作りたい。
物語の順序っていうのは、一般に起承転結と呼ばれているもので、そういうものに沿って書かれた物語を「タネと仕掛けのある」小説だと僕は個人的に呼んでいる。
物語の構造として、順序があるというのはストーリーの基本と言われているけれど、こういう本を逆から読んだとすると「結」のシーンを説明するのに「転」のシーンが必要になり、「転」を書くためには「承」のシーンが、「承」のシーンのために「起」が必要になる。
起承転結に委ねると同じ型の小説ができる
別にそれがわるいってわけではなく、その構造そのものは小説の面白さとはまったく関係がないのだけど、でもこの通りに書いたとしたら、全員が全員、同じ型の小説を書くことになるのだ。
起承転結の順番を入れ替えてみても同じことで、そのバリエーションが増えたというだけのことに過ぎない。そういう型をいくら覚えて自分の中に叩き込んだって、たぶんその型通りのものしか書けないだろう。
そしてそれはたぶん新しい小説、ではない。
夏目漱石の「草枕」、どこから読んでも面白い小説の話
これは確か夏目漱石が「草枕」の中で言っていたことだと思うんだけど、小説というのはどこ(本の途中)から読んだとしてもいい(僕はこれを小説はどこから読んでも面白いものになっていなくては駄目だと解釈した)、筋なんていちいち追わなくったって面白い小説は面白い、普通の小説はみんな探偵が発明したものだ、こういう風に言っている。
さらに漱石は踏み込んで人情にはもう飽き飽きした、そういうものは俗世間でいやというほど体験した、それをわざわざ小説の中でやる必要もなかろう、芸術はおそらく人の心の機微を描く中にあるのではなく、そういう人間的な情緒を離れ、絶したところ(自然、非人情)にある、と考えていたんじゃないだろうか。
タネと仕掛けのある小説の原理。からくりはわからないから面白い
「タネと仕掛けのある小説」はたぶん一度読んだら、その本の面白さのからくりが分かってしまう。
かくかくしかじかのことがあって、だから主人公がこうなって、結末はこれ、みたいに展開が分かってしまう。
その小説の面白さがどこにあるかはっきり分かっていて、説明が付けられるものだ。
大衆小説(エンタメ)はこれを是としている。その方が読者にわかりやすく感情を揺さぶることができる。
そういう小説は一般のひとびとにも受け入れられやすい。面白さがどこにあるか、わかるように作られているからだ。
もちろん小説が物語である以上、右から左に読んでいくもので、話の筋が必要になることは免れないだろう。
でも僕はその物語の展開に依存する度合いをなるべく減らしたいのだ。
何か登場人物がある行動を取るのにいちいち理由があって、それを後から説明するような小説にしたくない。
説明がつかないものがあっていい。物語の筋から脱却すればするほど、その小説は自由になっていくのではないだろうか。
どうやって物語の筋に頼らない小説を書くか
問題はどうやってその筋に依らない小説を書いていくか、である。
わざとらしく関節を外したように筋から離れるのは、あざとさが残る。作者の意図が透けて見えるのは、そこに新味があっても何だかいやらしい。
仮に思い付けたとしても、それは表面上の技巧の話であって、一度限りの書き方だろうという気もする。
僕の表現としてこれ以外にはあり得ないという語り方でなおかつ、自然に物語の筋に依らないものを書くことはできないものか。
僕が書きたいのは「タネも仕掛けもない(=その小説の面白さの仕掛けやからくりがわからない)小説」、それでも面白いと思ってもらえるような小説なのだ。
面白い小説は狙って書けるようなものなのか?
小難しく考えているけど、こういうのってたぶん狙って書けるようなものではないんじゃないかしらという気がする。
短編を作るとき、僕は何かしらのねらいを付けて(たとえば今回は一人称で語る、話の順序や主人公の立ち位置がわからないまま進む小説にする、など)書くんだけど、読み直したときにほんとうにいいなと思う表現は、狙いのなかになかったもの、物語が進行してきて自然なアドリブが生まれるときのような気がする。
プロットだとか小説の設定だとか、そういう周辺に付随するものはすべて、この自然な即興が生まれる瞬間のための下準備に過ぎないんじゃないか。
J・D・サリンジャーの「シーモア──序章──」は、これから書くもの書きのための本としても読める
サリンジャーの小説に「シーモア――序章――」というものがある。
グラス家の次男で作家でもあるバディ・グラス(サリンジャーの投影した分身とも言われる)がシーモアとの過去を回想するというストーリー。その中で、ビー玉遊びについて語っているところがある。
相手が投げたビー玉に向かって、転がしたビー玉を当てることができたら勝ちという他愛のないものだが、僕はここで語られていることがかなり好きだ。
もしかしたらこれは作家であるサリンジャーが、シーモアという架空の天才(もうひとりのサリンジャー)の姿形を借りてアドバイスを授けているシーンとしても読めるのだ。
シーモアはなぜかこのビー玉遊びの試合において圧倒的な成績(十中八九勝つ)を誇り、バディ・グラスはどうやっても彼に勝つことできない。
バディは相手のビー玉に狙いを付けて打つんだけど、シーモアは狙って当てたとしたら、そんなものはただの「運」だと言い切るのである。
「そうむきにならないで狙ってごらんよ」と彼はそこにまだ立ったまま言った。「狙って相手のビー玉に当てたって、それは単なる運だよ」彼はわたしたちに話しかけ、語りかけていたのだが、魔法のようなあの時刻の雰囲気をこわすようなことはなかった。が、わたしがそれを破った。しかもわざと。「狙えば、運じゃないじゃないか」わたしは後ろにいる彼に向って言った。何もそんなに大きな声を出したわけではなかったが(傍点をつけたにもかかわらず)、どちらかというと、わたしの声は実際に感じている以上にいらいらしていた。ほんの少しの間、彼は何も言わず、ただ歩道のふちに立ってバランスを取りながら、わたしにもなんとなく感じとれる愛情のこもったまなざしでわたしを見ていた。「だって、そうなんだもの」と彼は言った。「相手のビー玉に――アイラのビー玉に――ぶつけたら、嬉しいだろう。もし、うまく相手のビー玉にぶつけて嬉しいなら、こっちの玉がうまく相手のビー玉に当るなんてことを心の中ではそんなに期待してなかったからだよ。だからそこには何がしか運というものがはたらいているはずなんだ。そうさ。そこには偶然というものが多分になきゃならないんだ」
J・D・サリンジャー著「大工よ、屋根の梁を高く上げよ シーモア──序章──」野崎孝・井上謙治訳 新潮文庫 p.262-263.
このシーンはシーモアを描いた箇所で溜息が出るほど美しいところだと僕は思っている。
背景には禅や弓道の思想があるんだろうけれど、それでもシーモアという人物の魅力が十二分に引き出されている。
のみならず、この小説は実はもの書きに向けて書かれたものじゃないかと思うことがある。
本当に書きたいものに出会うとき、狙ったものの中にはない
本当にビー玉に当たるとき、書きたいものに突き当たるときっていうのは、狙ってやった表現のなかにはないんじゃないかと思うのだ。
周到に用意されたプロットの中に表現が生まれてくるのではなくて、そこから離れる瞬間に描いたものが、小説の表現として最も美しいものが現れるのではないか。
人間が当たり前だと思ってきた道理や理屈、あらかじめ用意されていたものから飛び立つ瞬間に。
どの文章を読んでも、これは「武内一馬」の文章だって、分かるようになったら一番いい。
まだ僕の文章は安定していないし、模索中の形ではあるけれど、いつか独自の文体をものにしたいのだ。
その上で、あまり他の作家がやっていないような語り方を見つけられたとしたら、その時にはじめて胸を張って、僕の作品です、と言える一編が書ける気がする。
もう十年、追いかけてみる。駄目だったらそれでもいいんだ。
2022/09/14 17:04
kazuma
もの書き本紹介コーナー:漱石の「草枕」・サリンジャーの「大工よ、屋根の梁を高く上げよ シーモア──序章──」
もの書き本紹介コーナーです。今回取り上げた夏目漱石の「草枕」、サリンジャーの「大工よ、屋根の梁を高く上げよ シーモア──序章──」は、これからものを書きはじめる、もの書きにおすすめ。
小説や芸術について夏目漱石やサリンジャーはどういう風に考えていたか、その一端を掴むことができるかもしれない。
「草枕」は芸術について、サリンジャーの「シーモア──序章──」はものを書く上での心構えについて重要な示唆が含まれている。
これから小説を書くひとにはこの二冊を勧めます。いずれそれぞれの本について、もの書きの視点でまとめた記事を書こうかと考えている。今日は、これで。