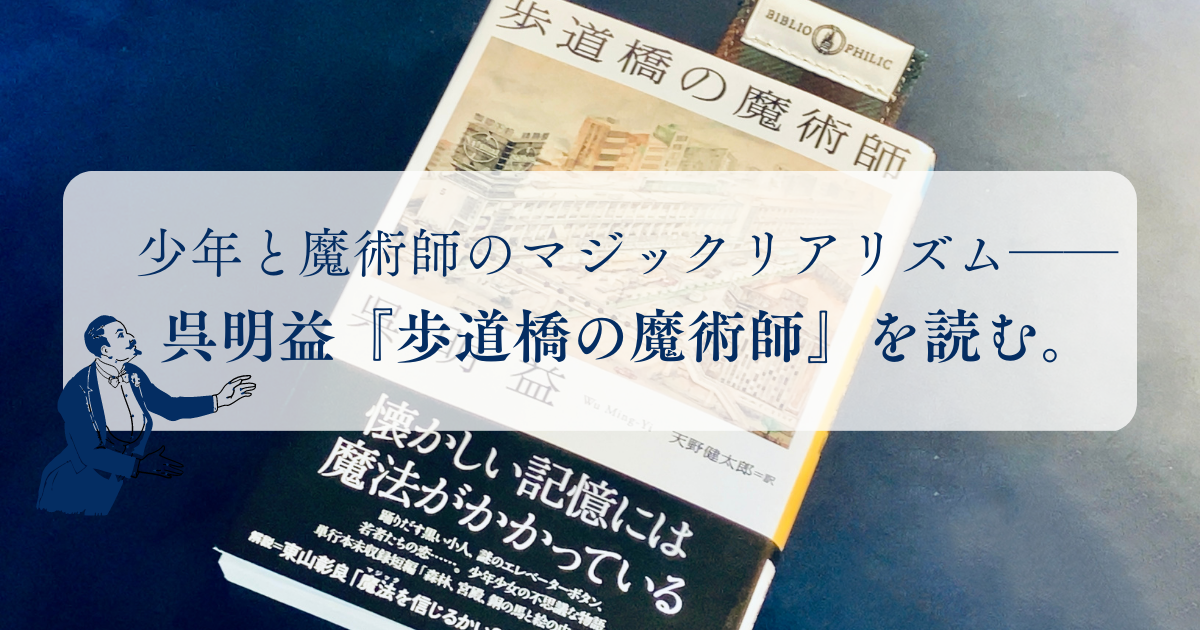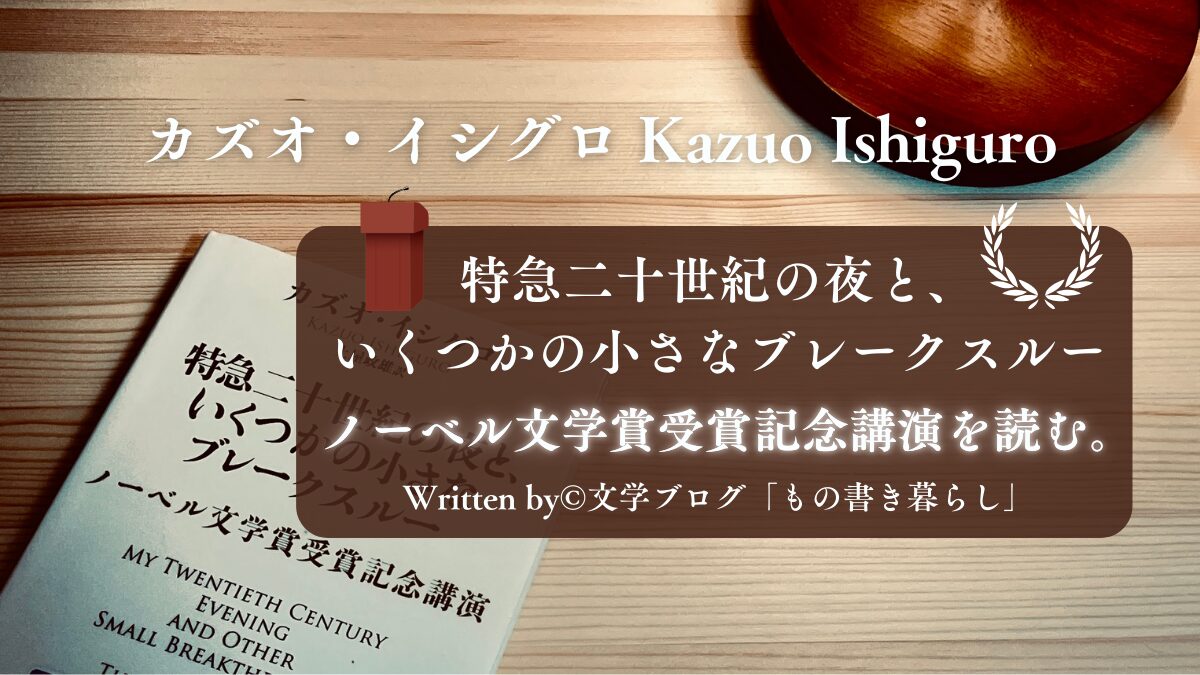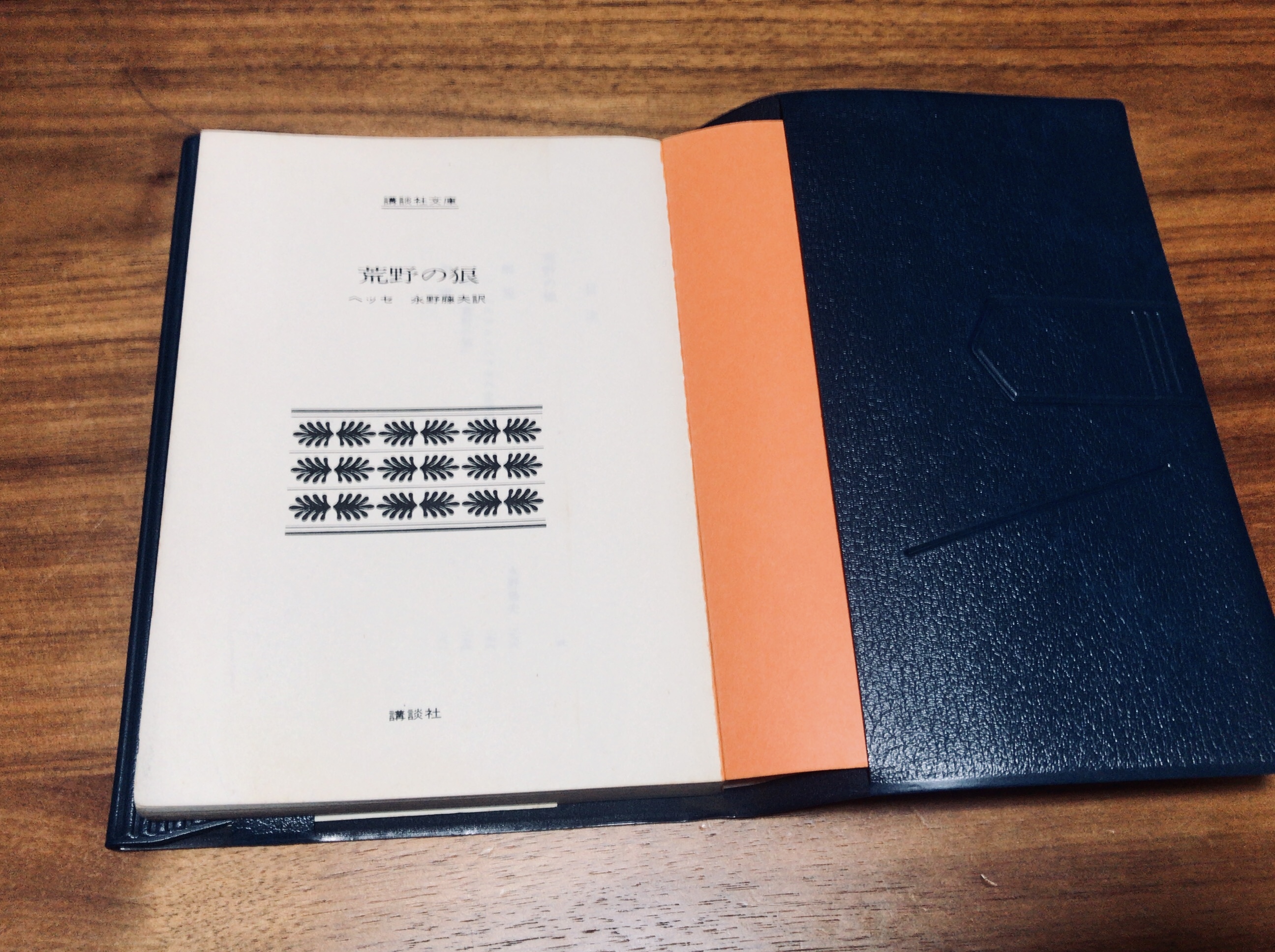「もの書きのバイブル バルガス=リョサ『若い小説家に宛てた手紙』を読む。」
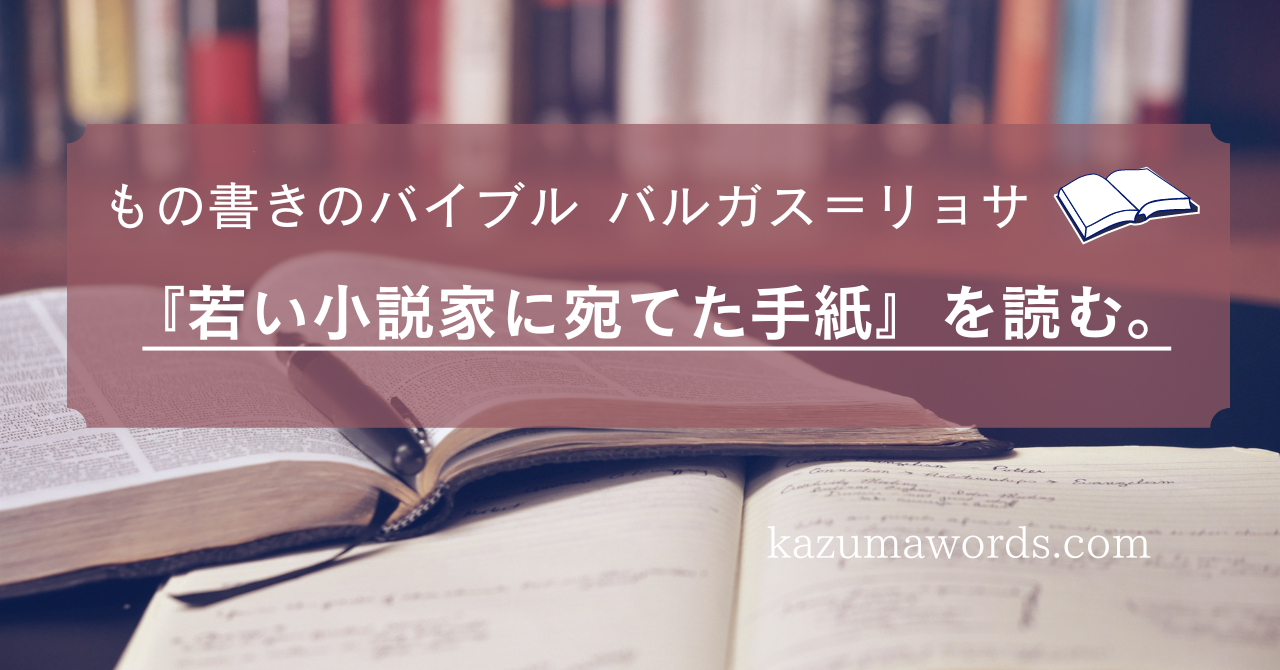
『若い小説家に宛てた手紙』を読んだので
今回、取り上げる本はマリオ・バルガス=リョサの『若い小説家に宛てた手紙』です。バルガス=リョサは1936年生まれのペルー出身の作家で、ラテンアメリカ文学を代表する作家のひとりと目されている。2010年にノーベル文学賞を受賞して、国際ペンクラブの会長も務めた人物だ。
バルガス=リョサは小説だけではなく、評論なども行っており、同じく南米の有名作家であるガルシア・マルケスの文学論(『ある神殺しの歴史』)なども書いている。
この『若い小説家に宛てた手紙』は書簡形式(バルガス=リョサと作家志望の青年が交わした手紙のやり取り風)で書かれており、バルガス=リョサが、自身の小説観や創作論を通して、若い作家志望の書き手にアドバイスを送るという体で書かれた本だ。
一晩かけて読んだ。もっと早くに読んでいればよかったと思う一方で、書きはじめた頃では書かれてあることの意味が少しも掴めなかったと思う。これを読んで小説が書けるようになるわけではない。でも書くことの不思議さ、小説が生まれてくるからくりの一部が解き明かされているように感じた。 pic.twitter.com/sFZNjbgRf9
— kazumawords. (@kazumawords) October 18, 2022
『若い小説家に宛てた手紙』はもの書きのバイブル
僕も創作にまつわる本はいくつか読んだのだけど、小説がいったいどのようなものか、どういうからくりで動いているものなのかを解き明かすという意味で、一番的を得ていると思ったのがこの本だ。
僕が『若い小説家に宛てた手紙』を読んだのは、書きはじめてから十年になったところで、読み終えた感想としてはもっと早い時期に読んでおきたかった本だった。小説を書くひとにとってはバイブル本といってもいいだろう。
目次は十二章に分かれており、どれも読み応えのあるものなので、少しずつ紹介していこうと思う。今回の記事では、作家の資質を説いた第一章『サナダムシの寓話』を取り上げます。
小説はどのようにして生まれるか? どうすれば作家になれるのか? 作家志望の問い
第一章『サナダムシの寓話』で語られているのは、小説とはどういう経緯で生まれてくるものなのか、どうすれば作家になれるのかという問いについてバルガス=リョサが答えています。
冒頭、熱意のある作家志望の青年が、作家になるためにはどうすればいいかという手紙をバルガス=リョサに送ったことからはじまる。
バルガス=リョサ自身も、かつてはそういう風に悩んだことを明かしていて、作家に手紙を送って教えを請いたかったが実際にはできなかったと話しています。
訳者のあとがきにはバルガス=リョサがいた当時のペルーは識字率が低く、本を買ってまで読むひとはほとんどいない環境だったと記されている。
作家になろうと目指すことは「まとも」ではないと見なされることで、若い頃のバルガス=リョサが肩身の狭い思いをしながら書いたことは想像に難くない。
現代の日本でも、当時のペルーほど過酷ではないにしろ、世に出る前の作家志望というのは、あまり褒められたものではないと思われてしまっている。
いまのところ書き手が唯一認められるのは、何らかの文学賞を獲ったり、商業出版により書店に本が並ぶ場合で、多くの若い書き手はそのことを夢見て、あわよくば作品からの収入だけで生活したいと思うものなのだけど、バルガス=リョサは、作品からそういう見返りを求める行為はやめた方がいいよ、と冒頭で警告している。
「手紙を書いてこられたことを見ると、あなたは私のように萎縮しておられないのでしょうね。冒険をおかしてでも作家になりたい、作家になれば数々の奇跡が待ち受けているはずだ――手紙にそう書いておられなくてもわかります――ただ一ひと言忠告しておきますと、そういうことはあまり考えないこと、成功したらなどと考えて夢を織りすぎないことです」
『若い小説家に宛てた手紙』バルガス=リョサ 木村榮一訳 新潮社(2000)p.8より引用
書くことに現世的な見返りなど微塵も考えない方がよい
小説を天職だと考えるほどのひとであれば、書いたことによって生まれる結果など、気に掛けるはずがない、とバルガス=リョサは言います。
作家は書くという行為そのもののなかに報いを求めるもので、書いたものによって得られる現世的な見返りなどはどうでもよいと考えるものだから、と言うんですね。
もし首尾良く本が出版されるようなことがあっても、そういう名声は一時のものに過ぎず、本来評価されるべきものが評価されず、そうでないものがもてはやされることも往々にしてあるので、小説の外側にあるものを意識するな、自分の作品を書き上げることだけに意識を向けろと言っているわけです。
僕がこの本を持っているのは、通っていた古本屋さんにおすすめされたことがきっかけでした。ある意味、僕自身のそういう傾向を見透かされてのことだったのかな、とあとになって思います。
作家の資質は現実に対する不信、『If』の世界を想像する力
じゃあどういうひとが作家になるのか、という問いに対し、バルガス=リョサは、その人物に現実に対する不信があることを挙げます。
文学って言うのはそもそも反抗から生まれてくるもので、何に反抗するの? って言われると、目の前の現実に対してだと言うんです。
幼い頃に空想にふけって楽しんだりしたことはありませんでしたか? 現実にはないけど、こうだったらいいのにと思ったりしたことは? 実はこうしたことが創作をはじめる萌芽になっているとバルガス=リョサは話します。
僕の場合だと、なにか理不尽な目に遭ったり、つらいことがあったりしたときに、その場にいない昔の友人のことを思い浮かべたりしていました。学生の頃の話です。何か困ったときにそいつだったらどうするだろうと、ちょっと想像してみたりするんですね。
ひとりで街中を歩いてるときも、河原を散歩しているときも、部屋のなかにうずくまっているときも、もし隣にそいつがいたらどうだろうと。大人になっても、たまにそういう風に考えることがあります。
現実にはないけど、こうだったらよかったのに、という「If(もしも)」の世界を考える性質が、実は作家になる資質のひとつだとバルガス=リョサは言っているんです。
小説が描くものは実際にあった人生、ではなくて、そのように生きたくても生きられなかった、もうひとつの可能性としての人生を描いているんです。
バルガス=リョサはこれを「月の裏側」という言葉で喩えています。
ぽっかり空いてしまった空洞のなかに架空の住人を棲ませて、物語を演じさせることで、何とかその叶わなかった願いを鎮めようとしているんですね。
だから、小説は誰かが実際に生きた人生のストーリーじゃない、その裏側にあった虚構だというわけです。
創作の根底にあるものは現実への反抗
それで作家という生き物は、現実よりもその想像した世界の中に生きたい、あわよくばこの目の前の現実と取り替えたい、そういう欲求をもつひとのことだと。
欲求を持つだけでは収まり切らず、書き言葉によってそれを具現化しようとします。
それが作家としての資質であって、たとえどんなに明るい、優しさに満ち溢れたストーリーを書いてみたところで、創作の本質にあるものは現実への反抗だとバルガス=リョサは看破します。
だからこそ、かつて小説は検閲の対象となり、政府によって厳しく見張られていた歴史があります。
本来は思想ごと変えかねない、危険な代物と見なされていたんですね。(ただそういう風に小説と現実を混同して、現実の人生を小説に合わせようとすると手ひどい目に遭う、と話してもいます)
では、実際に作家というのは、小説をどのように捉えているのでしょうか。ここで持ち出されるのが第一章のタイトルにある「サナダムシ」のたとえ話です。
もの書きは「サナダムシ」を体内に飼うように、文学に仕える殉教者
小説を書こうとする人は誰でも体のなかに「サナダムシ」を飼うように、生活のすべてを文学に捧げるようになるだろうと、バルガス=リョサは言います。
小説を生活の優先順位のなかで一番上に持ってこいと言っているんです。
これってかなりシビアな話です。小説をものにするためなら、他のすべてのものを犠牲にすることになると言っているわけですから。
ものを書きたければ、文学の奴隷となって仕えることになる、とバルガス=リョサは話します。
「文学の仕事というのは、暇つぶしでも、スポーツでも、余暇を楽しむための上品なお遊びでもありません。他のすべてをあきらめ、なげうって、何よりも優先させるべきものですし、自らの意志で文学に仕え、その犠牲者(幸せな犠牲者)になると決めたわけですから、奴隷に他ならないのです。」
『若い小説家に宛てた手紙』バルガス=リョサ 木村榮一訳 新潮社(2000)p.16より引用
バルガス=リョサには実際にサナダムシを体内に宿したホセという友人がいたようですが、このホセは食堂で会話しているときにバルガス=リョサにこう語ります。
僕たちは映画館や展覧会に出かけていったり、本屋を回ったり、何時間も議論を戦わせたりするけれど、それは自分が好きでやっているのではなくて、体内にあるサナダムシのためにやっているような心地がすると、バルガス=リョサに語るのです。
文学もこれと同じで、小説を書こうとする人は人生で体験するどんな出来事もすべて小説のために使われ、やがて休むことのない活動に変わって、生活全体を覆い尽くすようになるだろうと説きます。
フローベールが話していたように、「ものを書くということはひとつの生き方」になり、そういう生き方は美しいが、多くの犠牲を強いるようになっていきます。
それを仕事として選び取ったら、生きるために書くのではなく、書くために生きるようになるのだと話しているのです。
そして、小説家の世界には早熟の天才など存在せず、みな一様に何年、何十年と気の遠くなるほどの時間をかけて、ようやくひとつの作品が生まれるのだということを話しています。
詩や音楽のように若い頃から華々しく世に現れることはなく、小説家は時間を掛けて自らの才能を築くものだというように書かれているんですね。
まとめ 生きて体験することはみんな書くことのためにあると考えるのが作家の生き方
一章の『サナダムシの寓話』を読み終えての感想は、ここに書かれてあることを実践するのは、口で言うほど簡単なことではないなと思います。
小説を書くためだけに生きられたら作家としては一番いいですが、じゃあそれで生活が成り立つの? 明日のご飯が食べられなくなっても同じ事を言えるか? ということも当然のように起こってくると思うんですよね。
バルガス=リョサも若い頃は相当苦労して書いたひとで、学校をいじめによって退学したり、学費や生活費を稼ぐために七つもアルバイトを掛け持ちしたことがあったり、大学の論文を書くためにアマゾン川の調査に突っ込んでいったりしています。
でもそういった経験が作品に活かされて結果的には世に出ることになったので、大事なのは日々の生活を過ごしながら、小説を書くことを諦めずにいることじゃないかなと思います。
日常の苦しみも、悲しみも、みんな書くことのためにあるって、休む間もなく考え続けられたら、そのひとはいつか作家になるだろうという気がします。
以上が第一章『サナダムシの寓話』の読解でした。またぼちぼち更新していきますので、お付き合いくださいませ。
noteではポメラDM250を使って執筆した「ポメラ日記」を連載しています。日常にまつわることを文学の話題と絡めて紹介しています。

2022/11/27 15:48
kazuma