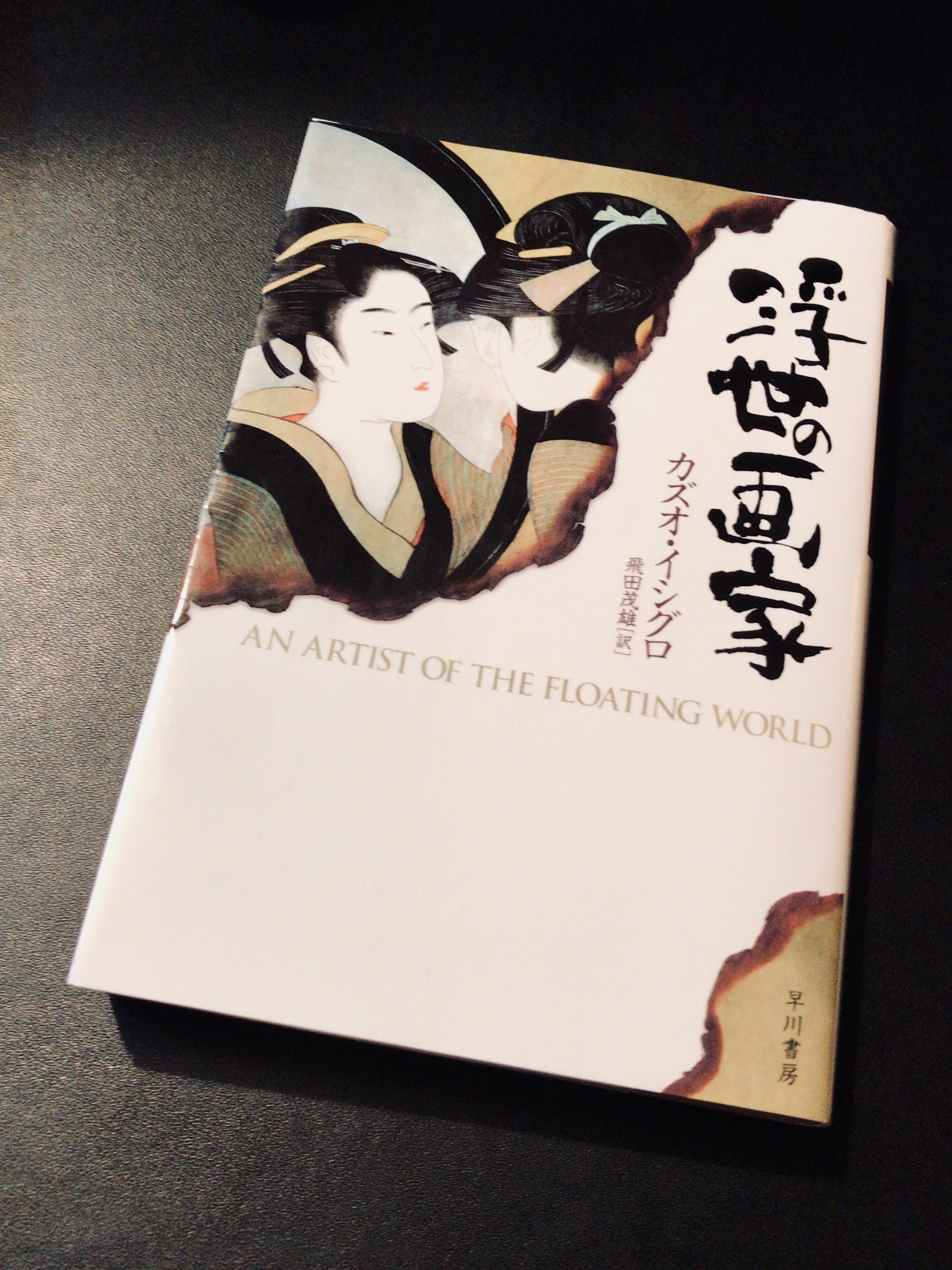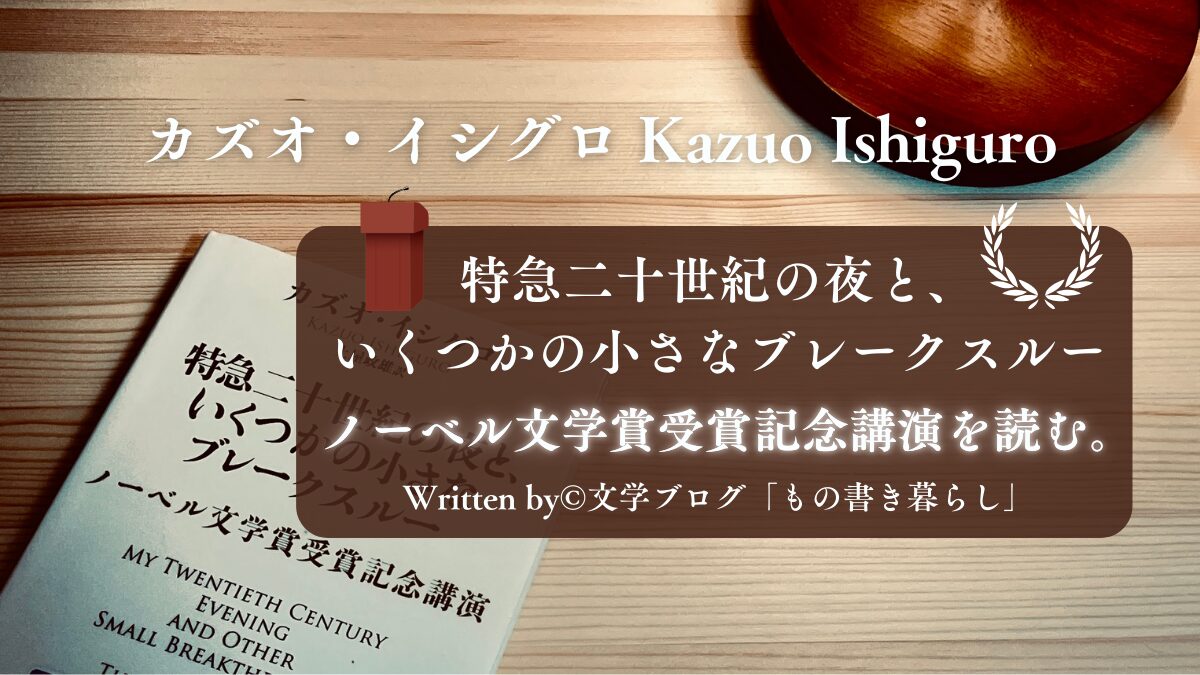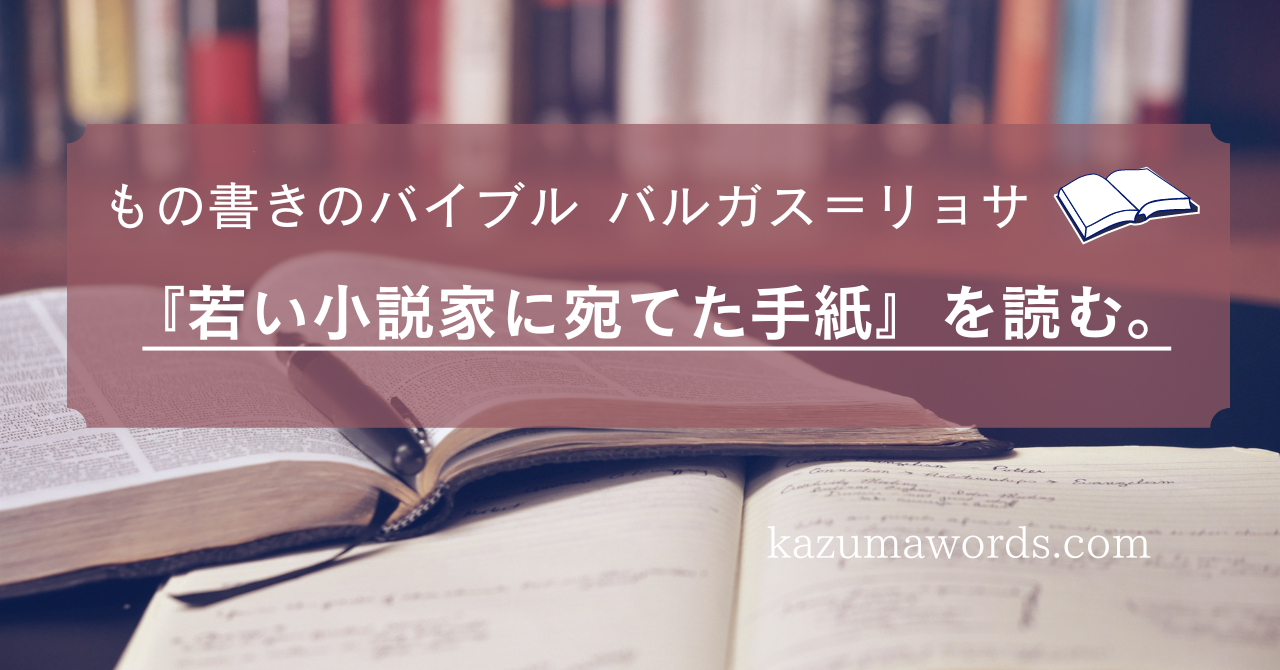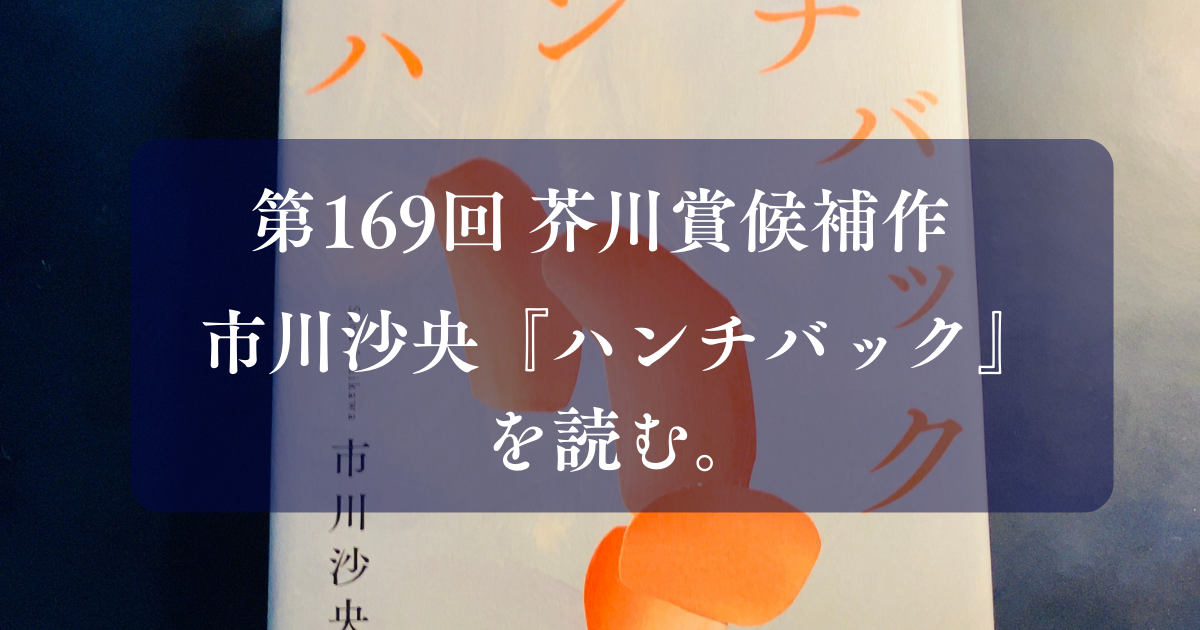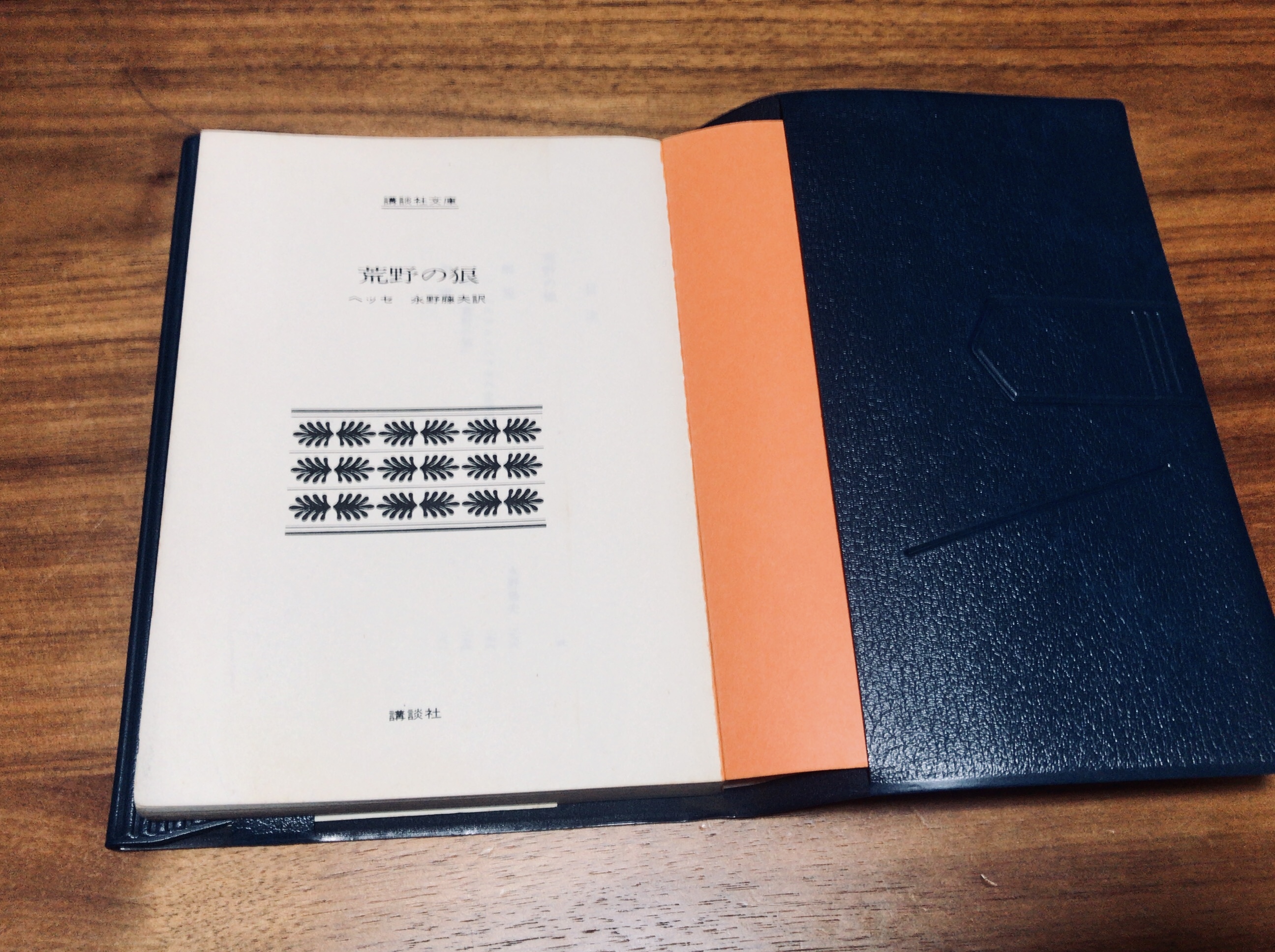「もの書きが読む、カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』」

カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』を読んだ話。
こんにちは、もの書きのkazumaです。今回は以前読んだ本の話をしようと思う。
カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』。これはカズオ・イシグロの代表作で、2005年に発表された作品だ。日本ではハヤカワ(epi文庫)から出ており、翻訳は土屋政雄氏が手がけている。
カズオ・イシグロは2017年にノーベル賞を受賞して、日系の英国人ということもあり国内でもかなり注目を集めたイギリスの作家だ。
ノーベル賞の受賞前から海外文学ファンの間で読まれている作家だったんだけど、受賞を機に増刷され、いまでは本屋で見かけないということはなくなったんじゃないだろうか。
原題の『Never let me go』という名前で映画化されたり、日本でも綾瀬はるか、三浦春馬、水川あさみ主演でドラマ化したりした。
僕がカズオ・イシグロではじめて読んだ作品は『わたしたちが孤児になった頃』で、上海とロンドンの二つの場所を舞台にした冒険ミステリなのだけど、緻密に組まれた物語の構成と落ち着いた語りにすぐに引き込まれたことを覚えている。
そのあと立て続けに『浮世の画家』『遠い山なみの光』『夜想曲集』といった作品を読んでいった。
この『わたしを離さないで』も例に漏れず、落ち着いた語り口でありながらスリリングな展開というイシグロ作品に共通する魅力がある。
現代の作家でここまでどっしりと構えて、読者を迎え撃つという語りをするのは世界的に見ても珍しいんじゃないだろうか。
僕にとってのカズオ・イシグロという作家は軍艦というかヘビー級のチャンピオンのようなもので、ゆっくり進みながらも確実に読者を打ちのめす、そういう語りをするひとだなと勝手に思っている。
『わたしを離さないで』の早川書房版を持っている人がいたら、そのカバー表紙を見て欲しい。そこに映っているのは一本のカセットテープだ。
タイトルにもなっている『わたしを離さないで(Never let me go)』とは、作中に出てくる曲のワンフレーズなのだけど、この物語において重要なシーンで使われている。
『わたしを離さないで』は、ある種のトリックのようなものが仕掛けられているため、未読のひとはぜひ一読してから、この先のレビュー記事を読むことを勧めたい。
この作品の内容を知ってから読むにはあまりにもったいないことだから。
もの書きが読む、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』ブックレビュー
さて、以前の記事でも取り上げたように、この小説はキャシー・H(愛称はキャス。以下、キャスとして記す)という人物の一人称の語りで進む。
『介護人』という謎の職業についているキャスは、過去の記憶を回想する形で読者に向かってものを語りはじめる。
第一部でキャスが語るのは幼少期の記憶だ。
彼女は『へールシャム』という寄宿学校で育ったことがわかる。キャスの友人には、かんしゃく持ちで周囲からばかにされている少年・トミーと、わがままでありながらもリーダーシップを持ち、周囲から人望のある少女・ルースがいる。
冒頭から読み始めていくと、そもそも『介護人』とは何のことか? そして何やら曰く付きで語られる『へールシャム』とは何なのかが読者の頭にもたげてくる。
キャスたちが通う寄宿学校・へールシャムは、周囲を森に囲まれており、どうも一般的な世間からは隔絶されているらしいことが徐々にわかってくる。
外界からはわずかなトラックを通じて物資などが届けられるのみで、生徒たちは『販売会』を通してしか、外の世界の品々を手に入れられない。
自分のものをわずかしか持っておらず、あとは『交換会』と呼ばれる生徒たちが作った作品を渡し合うフリーマーケットで手に入れる。
生徒たちが自分のものといえるのはそれらしかない。おまけに「マダム」と呼ばれる人物が『交換会』に出品された優秀な作品のみを集めて持って行く。はっきり言って謎だらけの幕開けである。
寄宿学校の子どもたちを監督するのは『保護官』と呼ばれる大人たちで、教師の役割を果たしているが、どうもそれだけではないらしいことがのちに分かってくる。
かんしゃく持ちの少年・トミーは足をふみならしたり、大声でわめいたりしながら、周囲に向かって怒りを表すことがあり、このことによって周囲の生徒たちからはあざ笑われることになるのだけど、なぜトミーがこんな風に怒るのか、実は本人にも周囲の生徒たちにも掴めていなかった。
語り手のキャスも早い段階でトミーに対して心を開くよう、打ち解け合おうとするのだが、どうもこの行為については嫌悪感を持っているようで、早くトミーに落ち着いた振る舞いをして欲しいとこの時点では思っている。
気取り屋のルースは、周囲の人心掌握に長けた人物で、クラスの花形の生徒として振る舞っている。キャスとも気の置けない付き合いをするが、思春期特有の近づいたり、離れたりということを繰り返しながら、キャスと友人関係を続けている。
キャスとルースが繋がっているのは、お互いに秘密を共有し、他の誰にも話さないという信頼関係が築かれていることに他ならないが、のちにそれはルースによって破られ、成長したトミーとの三角関係に発展する。
作中でルースとキャスは最も長い期間をともにしているように見える。この二人を表すとすれば、秘密を共有した腐れ縁、といったところだろうか。
なぜヘールシャムの生徒たちは秘密を抱えて生きなくてはならなかったのか
物語の大きな軸は二つあって、寄宿学校へールシャムの秘密と、生徒たちの出生の秘密、保護官たちの秘密というように、「なぜ彼らがこのように育たなければならなかったのか」ということが明かされる縦軸と、もうひとつがトミー、ルース、キャスの幼なじみ同士の三角関係、幼少期からの運命をともにしているこの三人が成長していく過程を描いているのが横軸となっている。
ここで物語の核心部に触れるけれど、ある日、へールシャムの生徒たちは、ルーシー先生という保護官から自分たちの出生の秘密に関わる真実を告げられる。
トミーやルース、キャスといったへールシャムの寄宿学校の生徒たちは、臓器提供のドナーとなるために生まれさせられたクローン人間で、成年に達すれば、自らの臓器を提供する『提供者』にならなければならない運命にある。
つまり、彼らは生まれ落ちたときから自分たちの未来についての運命を予め決定されており、へールシャムで実際に行われているのは一種の洗脳であることを仄めかしたのである。
当人たちは以前から少しずつ聞かされていたことで、自らを納得させようとするが、臓器提供が近づくにつれて、それぞれが自分の運命に向き合うことを余儀なくされる。
ある者は諦念に抑え込まれ、へールシャムの卒業後にいち早く提供への訓練を受けようとし、ある者は何とか提供が猶予される道筋がないか探ろうとする。
第二部でトミー、ルース、キャスの三人は、へールシャムの卒業後にコテージと呼ばれる農場施設に送られることになる。
ここはへールシャム時代には訪れることができなかった森の外にあたり、臓器提供をはじめるまでの最後の猶予期間を過ごすことになる。
いってみれば、トミーやルース、キャスたちの延長されたモラトリアムの期間で、彼らはお互いに結びつくことを通して、自らが生きてきたことの意味を何らかの形にしようとする。
ルースはオフィス街で働くことを夢見ており、トミーとキャスはへールシャムの思い出を捨てきれないまま、周囲の環境の変化に馴染めずにいる。
本人たちは、『提供』のことを意識しないようにしているが、やがて同郷のへールシャム出身の生徒たちがコテージからいなくなるにつれて、逃れられない運命の途上にあることを知る。
コテージに流れた唯一の希望といえるのは、へールシャム出身者にまつわる噂で、お互いに愛し合うカップルであることがへールシャムの上層部に伝われば、提供まで三年間の猶予が認められるかもしれない、というものだった。
コテージに先に着いていた「先輩」たちは、へールシャム出身者である、トミーやルース、キャスからこの噂を聞き出そうとするが、実は当の三人はこの噂についてはへールシャムの在籍中に聞いたことがなく、真偽が確かめられなかった。
やがてトミーは、交換会においてマダムが優れた芸術作品を集めていた理由について仮説を立てるようになる。
生徒の作品を持って行ったのはお互いに愛し合っているかどうか、作品から読み取るためであって、その猶予期間の判断材料にするためだったんじゃないかという大胆な仮説だ。
芸術作品であれば自らの本性を隠すことはできないから、本当に愛し合っているとすれば、それは作品の中に現れるだろうと考えたのだった。
実際は根も葉もない嘘だったが、ルースはこれを最後まで信じ、やがて提供がはじまった段階で、トミーとキャスに対してあたしは最悪のことをした、と打ち明ける。
ルースは、キャスとトミーの方がほんとうは付き合うべき人間だと分かっていたが、キャスとトミーが付き合うことを妨害し、代わりに自分がトミーと付き合った。
そのことを後悔していると謝り、突き止めたマダムの住所をキャスとトミーに渡すのである。この時点でルースは既に提供を経験しており、衰弱状態にあった。
キャスは提供者の介護人として優秀であったためか、『提供者』までにはならずに済んでいたが、トミーは介護人としては切られ、既に提供者になっていた。もう余命がいくら残されているか、提供にあと何回耐えられるか、お互いにわからない状況だった。
いまさらと思うキャスとトミーではあったが、それでもわずかに残された可能性に賭けようとして、トミーとキャスは作った作品を持ってマダムの邸宅に乗り込む。
マダムは話し合いに応じ、そこでへールシャムの真実について語りはじめる。マダムは隠されていたことを明かしてみせたのである。言うなればへールシャム時代の「答え合わせ」の時間だ。
へールシャムは、クローン人間の権利を守るために設立された寄宿学校でマダムや、かつての保護官であったエミリ先生たちによって運営されていた。
へールシャムの子どもたちが、生まれる前から未来を決められており、提供という目的のために存在させられていることを保護官は知っていた。
へールシャムで真実を子どもたちに明かさなかったのは、せめて子ども時代だけでも幸せな記憶を持った人間に育って欲しかったから。
真実を明かしたルーシー先生を解雇したのは、子どもたちを庇護するためで、未来が既に決まっていて、人生が無意味であることを悟らせないため。
もしそれを生徒が知ってしまったら、何もかもが無駄なことだと分かって子どもたちが絶望してしまう。
保護官は子どもたちをだましていることは知っていた。知っていて、子ども時代の幸福と真実を知ることを天秤に掛け、だますことを選んだ。
二人に告げられたのはそういう内容だった。
マダムがわざわざ生徒の作品を持って行ったのはクローン人間も、通常の人間と同じ心を持っているのだと証明するためだった。
提供を猶予するほどの力はへールシャムの運営側にはなく、その噂はでたらめで、へールシャムそのものもクローン人間の権利を擁護する運動を抑えられ、既に廃業したことが告げられた。
自分たちの人生が生まれる前から見知らぬ他人によって決定されており、その運命を受け入れるより他に道はなく、最後の希望も絶たれた二人は、提供する病院への帰途に就く。
途中で車を止めるように頼んだトミーは、成長してからは起こすことのなかったかんしゃくを起こして、野原で絶叫する。
キャスはトミーにしがみつき、そのときにはじめてトミーが怒っていたことの理由は、この真実を覆い隠され、自らで生きる道を決めることも許されない人生の上に生まれさせられたことにあったのではないかということを悟る。
自分たちは仕組まれた壮大なペテンに掛けられ、何の意味も無い人生を生きるよりほかに方法がなかったことを、この時にはっきりと知ったのである。
タイトルの『わたしを離さないで』の意味
『Never let me go』は幼き日の販売会に出てきたカセットテープで、トミーとルース、キャスを繋ぎ留めている記憶に関わるものだった。
キャスはある日、販売会で手に入れたこのテープをなくしてしまう。ルースはその頃、キャスと仲違いをしていたが、キャスと仲直りのしるしにとルースは販売会を探し回ってまったく違うテープをキャスにプレゼントした。
トミーも実はその頃に、キャスのためにそのテープを学校中を回って探していたが見つけられなかった。
コテージにいた頃に、ルースの『親』となる人物を探しに街へ出かけたとき、トミーはそのなくしたテープを探すことを思いつき、キャスとともに知らない外の世界を一緒に回り、ようやくそのテープを見つける。
その曲は母と子の歌で、キャスは歌詞の意味を知らなかったが、音楽室で聴いたときにはまるで自分が母親になったつもりで、子どもがどうか自分から引き離されることがないようにと願って、『Oh baby,Never let me go(どうか、我が子よ、わたしを離さないで』というフレーズを繰り返し、赤子を抱いたつもりで踊り続けるのである。
マダムは過去にへールシャムで偶然このシーンに出くわして泣いてしまう。
彼女が泣いたのは、キャスの心の内がわかったからではない。マダムはキャスのこれから先の運命が分かっていて、彼女が新しい時代に生まれてしまったことを知っていた。もしクローン人間などがいない古い世界にいたなら、彼女は生まれることもなかった。
それでも生まれてきた彼女が、いまはもう消えつつある古い世界の曲を掛けて踊っている。わたしを離さないで、わたしを離さないでと願いながら。
僕はこのシーンを読むとかなりこみ上げるものがあった。読んでいるときには気が付かなかったが、マダムはある意味ではへールシャムの庇護者=隠れた母親のようなもので、その姿や目的を子どもたちには決して明かさなかった。
へールシャムに育った生徒たちのことを、不幸な境遇のもとに生まれてきた子どもたちで、未来は助からないことを知っている。キャスが『わたしを離さないで』という曲を掛けて踊っているときに、その庇護者として彼女は泣いた。
自分ではどうにもできない運命にある子どもを助けることができないとマダムは分かっている。一方のキャスは、そんな運命を知ってか知らずか、自分が庇護される側としての存在ではなく、自らが母親の側に立った空想をしている。
キャスは『わたしを離さないで』というより『わたし(から子ども)を離さないで』と想像しているようなのだ。キャスはクローン人間で子どもを産めない体で生まれてくる。にもかかわらずこんな空想をするのは、自分が本来(クローン人間としてではなく通常の人間として生まれてきた世界)であれば、母親になる未来だってあったにもかかわらず、それが既に最初から奪われてしまっている悲しみゆえではないだろうか。
「わたしの未来であったはずの子どもをわたしから離さないで」、僕にはそんな風に読めるのである。
『わたしを離さないで』の物語は現代の日本の問題と深いところで根が繋がっている
この物語に託されているテーマは、「生まれる前から未来を決められてしまった人間はどう生きるべきなのか」ということだと僕は思っている。
へールシャムで描かれていることは洗脳教育そのものだ。子どもたちをある目的のもとに役立つように誘導し、選択の機会やものを判断するための材料を意図的に奪う。
それが子どもたちの幸せのためになると言って、周囲の大人が囲い込み、目的を達成するために子どもたちの人生を犠牲にする。悪夢以外の何ものでもない。
これが物語の中でしか起きていない出来事だと思えるところに身を置いているなら、おそらくそのひとはずいぶんと運のいい人生を送っている。
フィクションという体を取っているが、これは現在の日本でも起こっている問題と根深く繋がっている。宗教2世、3世の話だ。
僕はカズオ・イシグロの『わたしを離さないで』の物語の意味をほんとうに理解するのは彼らだと思う。
物語の筋や構造というのは、精通していればいくらでも明かすことができる。ちょっとした感想だって書けるだろう。でも説明できるということと、そこで語られているものがどういうものであるか、現実の人生で分かっているかどうかはまったく別の話だ。
カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』の感想をネット上で検索したとき「なぜ逃げないのか」という意見が書かれていて、僕は唖然とした。
この物語を外側から読むと、もっとはっきり言うと他人事だと思って読むなら、そういう感想になるんだろう。一度、彼らのような身になれば分かることだ。
へールシャムにおいて、周囲の森は恐れるべき存在として描かれる。
森を抜ければもちろんその向こうに現実世界が広がっているが、幼い頃から森には行ってはならないと堅く禁じられる。なぜなら恐ろしいことが起こるから。
そう教えられて育つと、森は抜けられないものだと思い込むようになる。
自分たちが提供という目的のために生まれさせられているにも関わらず、そうとは気づかれないように早い段階から寄宿学校で洗脳を行う。
外界との接触を遮断して育て、外の社会とは全く異なる論理を物心が付く前に叩き込む。判断するための材料もろくに与えられておらず、外の世界の子どもたちがどういう風に育つものなのかも知らないままでいるので、どれだけ異常なことなのか比較して知ることさえできない。
ようやく真実らしきものを知るようになるのは提供の直前になってからで、外界から隔てたところで育てられたために、外のひととのコミュニケーションの取り方が分からない。
もしこれらの洗脳から何とか奇跡的に脱することができたとしても、外の世界ではクローン人間という、社会で異質な存在として見なされることになり、へールシャムの内部の他は繋がりを持たない彼らは、外の社会で生きていく術はない。
もし仮に脱するのであれば、へールシャムの内部においても異質な存在になり、外の世界においても常に弾かれる存在として生きることになるだろう。
こういう同質的な集団から単独で抜け出すというのは、過去すべての人間関係を絶たざるを得なくなるので、孤立無援のまま社会に放り出されることになる。
それは殆ど自殺行為にも等しいことで、逃げ延びた先でも彼らは、社会で当たり前のように育った通常の人間のように生きることができず、マイノリティのなかのマイノリティとなって肩身の狭い思いをしながら暮らすだろう。
さて、逃げることの困難さがいくらかわかっていただけるだろうか。
ネット上にいくらでも転がっている感想、彼らが「なぜ逃げないのか」という問題について
なぜ逃げないのか、さっさと逃げればいいじゃないか、そんな風に読むことは簡単だ。鎖につながれた象の話を知っているだろうか。
サーカスの象は小さな頃に一本の杭に打たれた鎖に足をつながれる。子象のときに逃げだそうとしてこの杭を抜こうと必死で足を引っ張るのだが、鎖を抜くことはできない。
やがて大きく成長し、小さな杭などすぐに抜くことができるのに、大きくなった象は子どもの時の頃の記憶を憶えていて、この鎖を抜くことすら考えなくなり、大人しくつながれたままでいる、というたとえ話だ。
逃げることすら思いつけないように育てられているということがどうして分からないのだろうか。なぜ当たり前のように個人の自由意志でどうにかなる問題だと思っているのだろうか。カズオ・イシグロが描いたのはそういう個人の努力の範疇でどうにかなる問題を描いていたのだろうか。
僕は違うと思う、これはそういう運命を生まれつき背負わざるを得なかった人間についての話だ。
このなかの登場人物は結局、誰も助からない。ルースは真実を知らないまま、だまされた嘘を信じたまま提供で亡くなり、トミーは真実を知ったが逃れるには遅すぎたし、そのような手立ても彼らには存在しない。
残されたキャスは友人二人を失い、孤独の中でひとり涙を流す。『わたしを離さないで』という曲は理想を歌っているに過ぎず、そんな世界はもう彼らが生まれた時点でとっくに過ぎ去っていて、それでもキャスは後生大事にそのカセットテープの思い出を携えて、最後のときを迎えるだろう。
トミーは、へールシャムの真実をマダムやエミリ先生に聞かされたあと、こんなことを言う。
「ルーシー先生が正しいと思う。エミリ先生じゃない」
頭で考えてわかるようなものは大したものではないように思う。物語の中にはいつも理屈を超えたものが含まれていてほしいのだ。
2022/10/20 22:39
kazuma