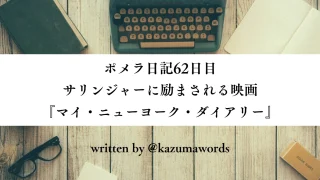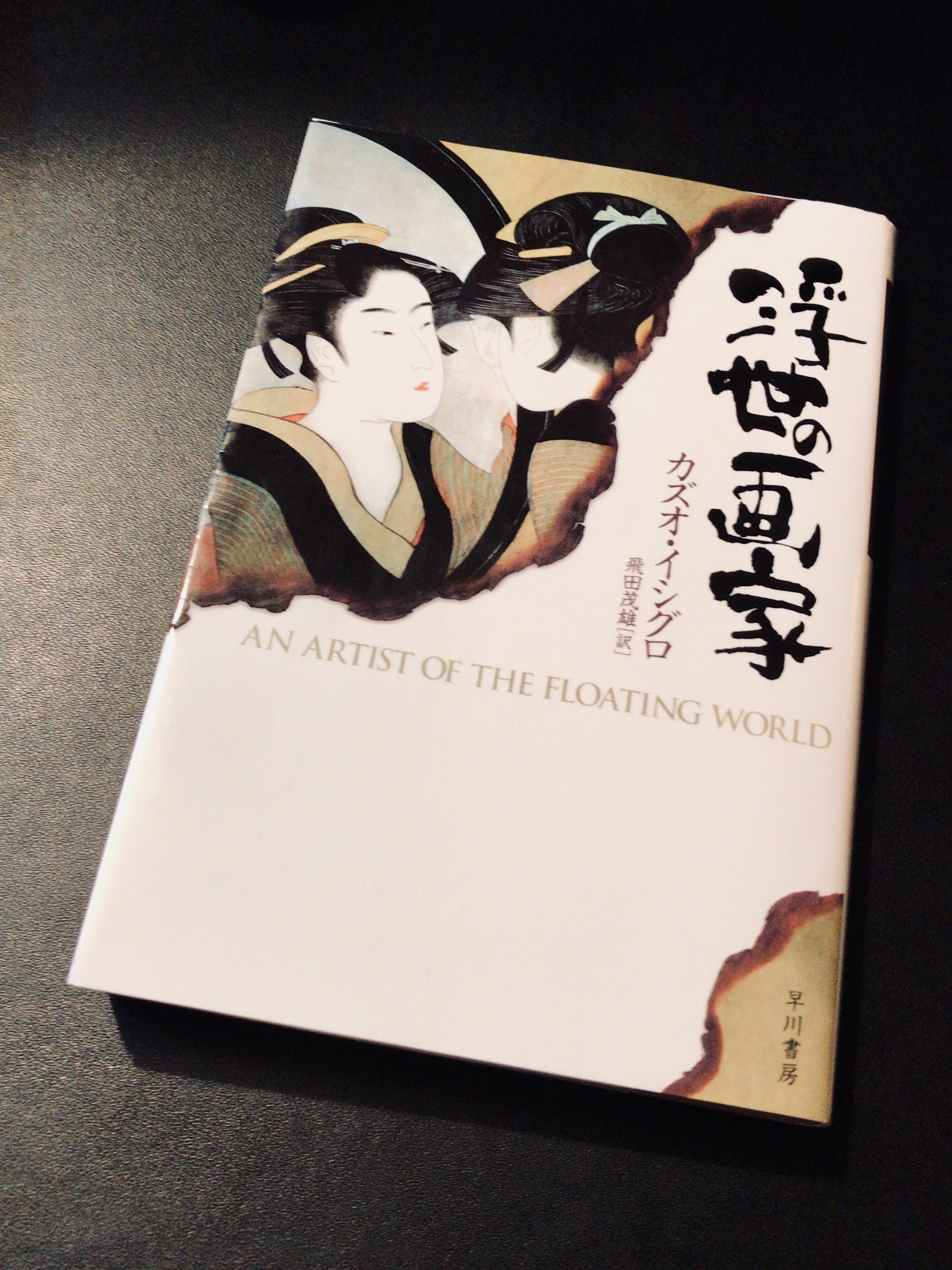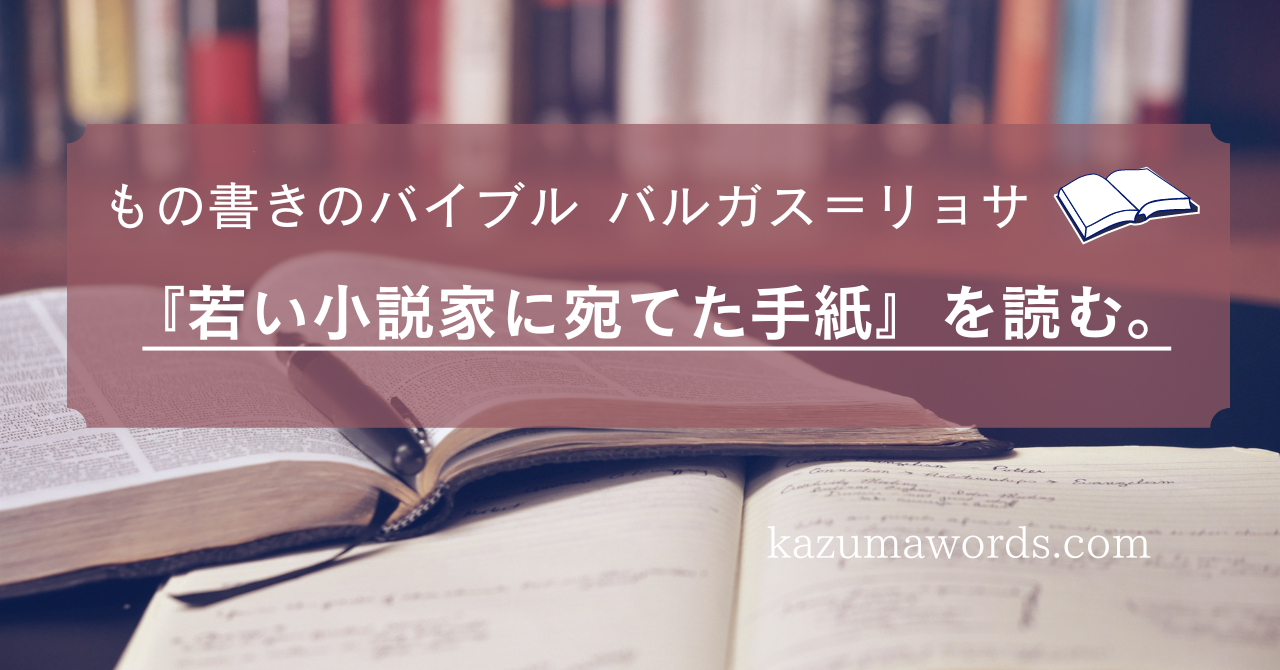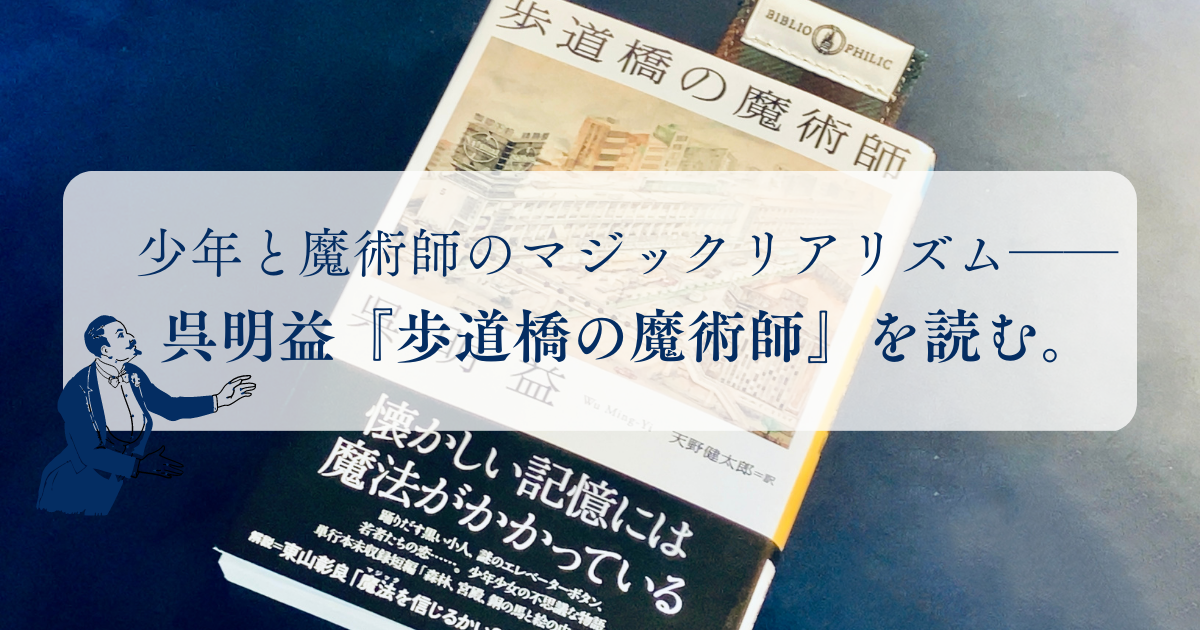「サリンジャーと過ごした日々」を読む。

晩年のサリンジャーと会話した、ある出版エージェントのお話

『サリンジャーと過ごした日々』という本を知っているだろうか?
原題は『My Salinger Year』で、著者はジョアンナ・ラコフ。米国の詩人だ。
実は彼女は、サリンジャーファンなら誰もが驚く経歴を持っていて、晩年のサリンジャーの出版エージェントとして勤めていた過去がある。
存命中のサリンジャーと会話する機会があったのも奇跡のような話だが、それが彼女の人生を変えてしまったかもしれない。
今回は「サリンジャーと過ごした日々」の物語をひも解いてみよう。
小説を書きたいと思っているけれど、日々の仕事に追われて書きあぐねている人は、参考になることが見つかるかもしれない。
「サリンジャーと過ごした日々」のあらすじ

「サリンジャーと過ごした日々」の主人公は、ジョアンナだ。名前から分かる通り、著者のジョアンナ・ラコフであり、この物語は実話に基づく、ノンフィクション・ノベルになっている。
ジョアンナは大学院を卒業したばかりの本好きの女の子。24歳になった彼女は勤め口を探していた。
大学で英文学を専攻したジョアンナは「他人の詩を分析するのはもうたくさん」というわけで、アカデミズムの世界から去って、「自分の詩を書きたい」と願っていた。
「昼は都会のニューヨークで働き、夜はカフェや安アパートで執筆する」という作家志望なら一度は夢見る生活を送るため、とある出版エージェントの面接を受ける。
就職コンサルタントの話によれば、ニューヨークでも歴史のある、老舗の出版エージェントらしい。
「出版エージェント」がどんなものだか、全く知らないまま、面接を受けることにしたジョアンナ。
「タイプライターは打てるか?」と聞かれて、就職コンサルタントの言うとおり「1分間に60語は打てます」と答えたジョアンナは、めでたく採用される。
採用時の面接を担当したのは「ボス」で、この出版エージェンシーの代表を長く勤めている女性社長だ。
面接では、ジョアンナが「フローベール」を読んだことについて語ると、「フローベールもけっこうだけれど、出版エージェントなら存命の作家も読まないとね」と釘を刺される。
入社して彼女に任せられたのは、旧式のタイプライターでテープに吹き込まれた音声を片っ端からタイプすること。
そして、ボスからは「ジェリー」の電話番号と住所は、ぜったいに誰にも教えてはならない、と半ば脅し気味に言われる。
「ジェリー」って誰のこと? と思いながらも、ジョアンナはボスの部屋を出る。会社の本棚に置かれていた本の背表紙と目が合う。そこにあったのは、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』『フラニーとズーイ』『ナイン・ストーリーズ』だった。
サリンジャーだ。この会社の担当作家の中には、J・D・サリンジャーがいた。それに気付いたのは、デスクにもどったあとだった。ああ――わたしは心の中でつぶやいた。ジェリーって、あのジェリーのことなのね。
『サリンジャーと過ごした日々』ジョアンナ・ラコフ著 井上里訳 柏書房(2015)p.45より引用
日本と異なる米国の出版事情

ここで「出版エージェント」とはそもそも何ぞや、ということに触れておきたい。
日本で作家になる正規ルートは、出版社が主催する新人賞を受賞すること、になっている。
一方、米国では出版事情が異なっていて、出版社と作家(書き手)の間に、エージェントが入るのが慣習になっている。
出版エージェントは、作家の著作権などの権利関係や、出版社との交渉を行うなど、実務面で作家をサポートする。
作家の代理人として、原稿を出版社に売り込むのも出版エージェントの仕事だ。
作中でジョアンナは、新米アシスタントの扱いで、担当作家を任せて貰えるようなポジションにはいない。それで、ボスの細々とした雑務を任されているのだが、ジョアンナは担当作家を持つことに憧れている。
ボスが一時的に不在になったあと、その穴を埋めるためにジョアンナは原稿の売り込みも手がけるようになるが、なかなか出版社側に通して貰えず折り合いがつかない。
そんなとき、サリンジャーの過去の記録を会社で見つけ出し、あの「キャッチャー・イン・ザ・ライ」でさえ、一度は編集部に断られていたことに気が付く。
ちなみに、「キャッチャー・イン・ザ・ライ」を売ったのは、まさにこのエージェント会社(ハロルド・オーバー・アソシエイツ)の二代目社長であるドロシー・オールディングで、ジョアンナのボス(フィリス・ウェストバーグ)は、ドロシーの後任者だった。
米国の作家にはこうした著者を影で支える出版エージェントの存在がある。
作家の伝記を辿ってみると、華やかに見える作家生活の裏側には、書き手を献身的にサポートしたエージェントの名前が結構見つかったりする。
「サリンジャーの生涯」に関しては、ケネス・スラウェンスキーがまとめた「サリンジャー 生涯91年の真実」がおすすめだ。
各作品ごとの出版社とのやり取りも細かく記載されているし、謎の多い作家であるサリンジャーの生涯を知る上で、恰好の一冊だと思う。
本書と併せて読めば、米国の「文芸エージェント」がどんなものか、イメージを掴むことができるだろう。
日本では新人賞の選考が「足きり」になっているが、米国ではエージェントに認められないと出版には漕ぎ着けられない。
エージェント経由で打診された原稿は、ある程度の質は担保されたものと考えて、はじめてそこで出版社との交渉テーブルに上がることができる。
作家と二人三脚で組むタイプの出版エージェントは、日本ではあまり例がないみたいだけど、ネットでちらほらそんな話を見かけたりもするので、いつかは出てくるんじゃないかなと個人的には思う。
書くことを諦めそうになっている人に読んで欲しい本

主人公のジョアンナは、「自分の詩を書きたい」ために、大学を出て「タイピスト兼秘書」になったのに、いつの間にかエージェントの仕事に追われ、書くことを遠ざけていた。
ジョアンナの日課は、サリンジャー宛に送られてくる大量のファンレターをシュレッダーに掛け、お決まりの「定型文」を返すこと。
しかし、ジョアンナはファンレターを読むうちに、彼らの心情や人生が打ち明けられていることに気付く。それほどまでにファンの心を掴むサリンジャーの小説とは何なのか。
ジョアンナは学生時代に「サリンジャーを読まなかった」と白状している。「ライ麦畑」も「フラニー」も「ナイン・ストーリーズ」でさえ読まなかった。
そんな彼女のもとに一本の電話が掛かってくる。電話の声の主はよく聞き取れないが、「もしもし」と繰り返している。「ジェリーだ。きみのボスに話があってかけたんだけどね」と言葉は続く。
はじめはサリンジャーに名前を間違えられていたジョアンナだったが、何度も電話を受けるうちに名前を覚えてもらえるようになった。
ある日、ジョアンナはサリンジャーにこう言われる。
「ジェリー」わたしはどなり返した。「ジョアンヌです」
「サリンジャーと過ごした日々」ジョアンナ·ラコフ著 井上里訳 柏書房(2015)p.274
「ジョアンヌか」サリンジャーの声がわずかに小さくなった。いまでは彼のどなり声にも慣れていた。そこまでうるさくも感じない。「君が電話応対をさせられてるのかい?」
「パムが早退しなくてはいけなかったんです」わたしは説明した。
「なるほど」サリンジャーはいった。「電話応対なんかにかかずらわってちゃいけないよ。抜け出せなくなるからな。きみは詩人なんだ」
電話を終えたジョアンナはまるで何かをくぐり抜けてきたあとのように、職場の本棚にあったサリンジャーのペーパーバックをまとめて鞄のなかに放り込んで持ち帰る。
それから、人生で一度も読まなかったサリンジャーの本を息せき切って、読みはじめるのだ。
ジョアンナは自分の本心に気が付き、ともに過ごしていた作家志望の恋人と別れ、エージェントとしての仕事もやめ、ニューヨークから離れ、故郷に戻った。そして、詩人になった。
「僕には静かな感情(get quiet emotional)があるんです」
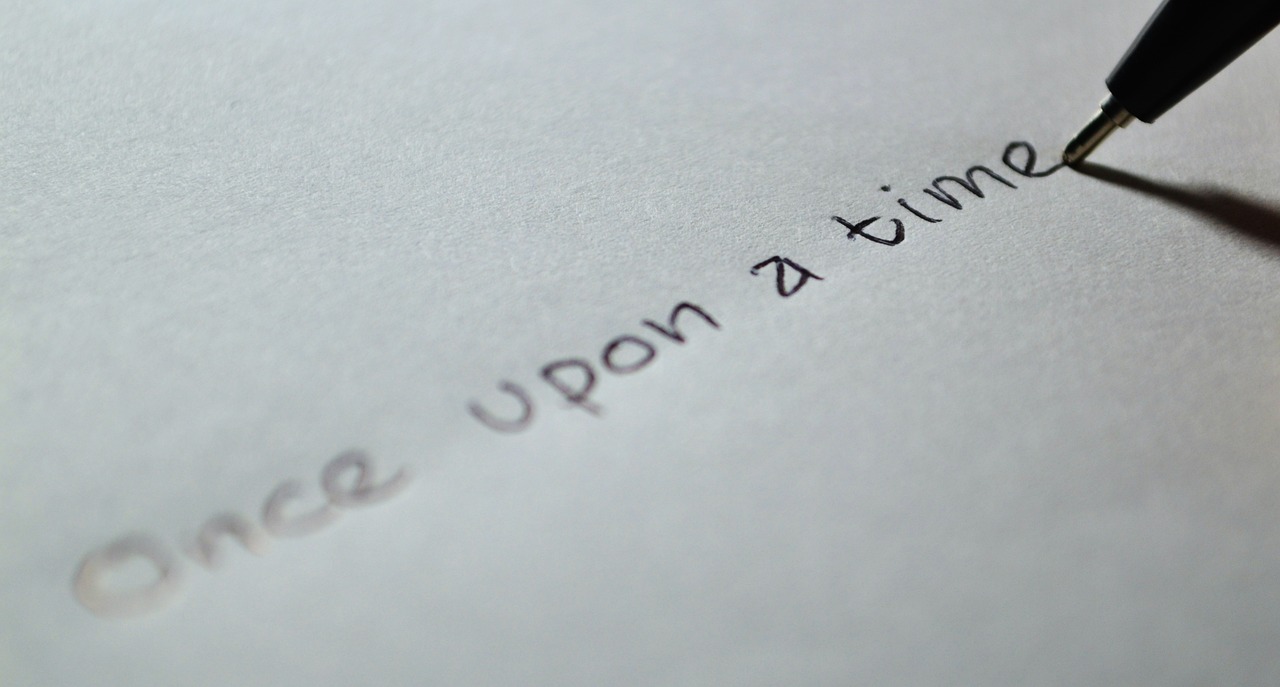
本書のなかでもとくに印象的なシーンがある。それはノースカロライナ州のウィンストン・セイレムから送られてきた一通の手紙で、宛先はJ・D ・サリンジャー。
「ライ麦畑」を繰り返し読んだというこの少年は、手紙にこうしたためている。
ホールデンのことをよく考えます。ホールデンはいきなりぼくの心の目にとびこんでくるんです。そうするとぼくは、彼が年を取ったフィービーとダンスをしたり、ペンシー高校のバスルームの鏡の前で大騒ぎしたりしているところを考えはじめます。いつも、最初はばかみたいににやにやしてしまいます。ホールデンはなんておもしろいやつなんだろうって思うんだけど、しばらくすると、いつも死ぬほど落ち込みます。それは、ホールデンのことを考えるのは、すごく感情的になってるときだからだと思います。ぼくには静かな感情(get quiet emotional)があるんです。
「サリンジャーと過ごした日々」ジョアンナ·ラコフ著 井上里訳 柏書房(2015)p.245
実際には「感情的になる(get quite emotional)」の書き間違いなのだけれど、そのことで却ってこの手紙は美しくなっていると、ジョアンナは言う。この辺りは詩人の感性だと思う。
そう、少年は”静かな感情がある(get quiet emotional)”と書いてきた。”感情的になる(get quite emotional)”ではない。単なる書き間違いだろう。美しく、意味深い書き間違いだ。サリンジャーならこの誤植の価値をわかってくれるはずだ。
「サリンジャーと過ごした日々」ジョアンナ·ラコフ著 井上里訳 柏書房(2015)p.246
晩年のサリンジャーは、「ハプワース16、1924年」の物語を小さな出版社で再版しようとしたとき、ニューヨーカー誌の誤植を直さなかったという。
もしかしたら、それはサリンジャーにとって直す必要がなかった間違いなのかもしれない。彼は、ニューヨーカー誌に掲載された当時と同じ形で出版しようとしていた。
「ライ麦畑でつかまえて」の主人公、ホールデン・コールフィールドは、ある歌の歌詞を覚え間違えている。
「君、あの歌知ってるだろう『ライ麦畑でつかまえて』っていうの。僕のなりたい――」
「ライ麦畑でつかまえて」J・D ・サリンジャー著 野崎孝訳 白水社(2015)p.268-p.269
「それは『ライ麦畑で会うならば』っていうのよ!」とフィービーは言った。「あれは詩なのよ。ロバート・バーンズの」
「それは知ってるさ、ロバート・バーンズの詩だということは」
それにしても、彼女の言う通りなんだ。「ライ麦畑で会うならば」が本当なんだ。ところが僕はそのときはまだ知らなかったんだよ。
「僕はまた『つかまえて』だと思ってた」と、僕は言った。
サリンジャーらしいエピソードが垣間見えるストーリーだ。
映画「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」と併せて、原作「サリンジャーと過ごした日々」を読むと、より一層楽しめます。
2024/02/02 16:48
kazuma
僕がnoteに連載している「ポメラ日記62日目」では、「マイ・ニューヨーク・ダイアリー」について取り上げています。映画版のレビューを知りたい方は、こちらもどうぞ。