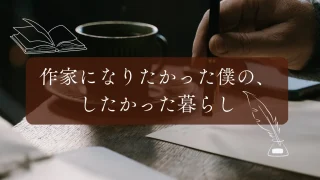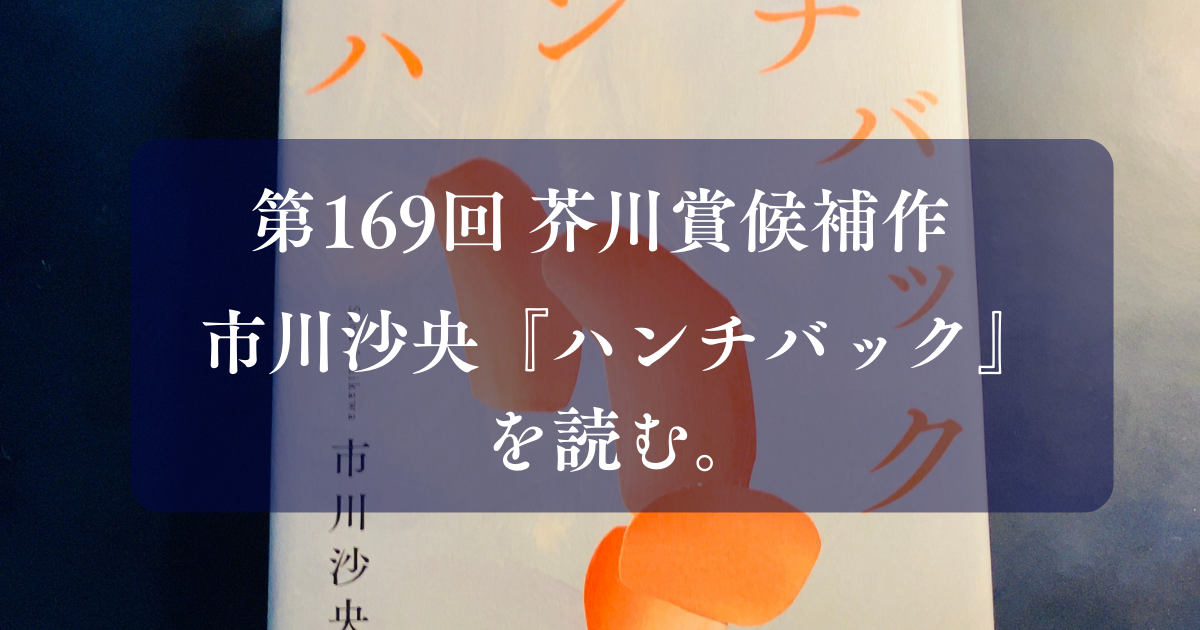少年と魔術師のマジックリアリズム──呉明益『歩道橋の魔術師』を読む。
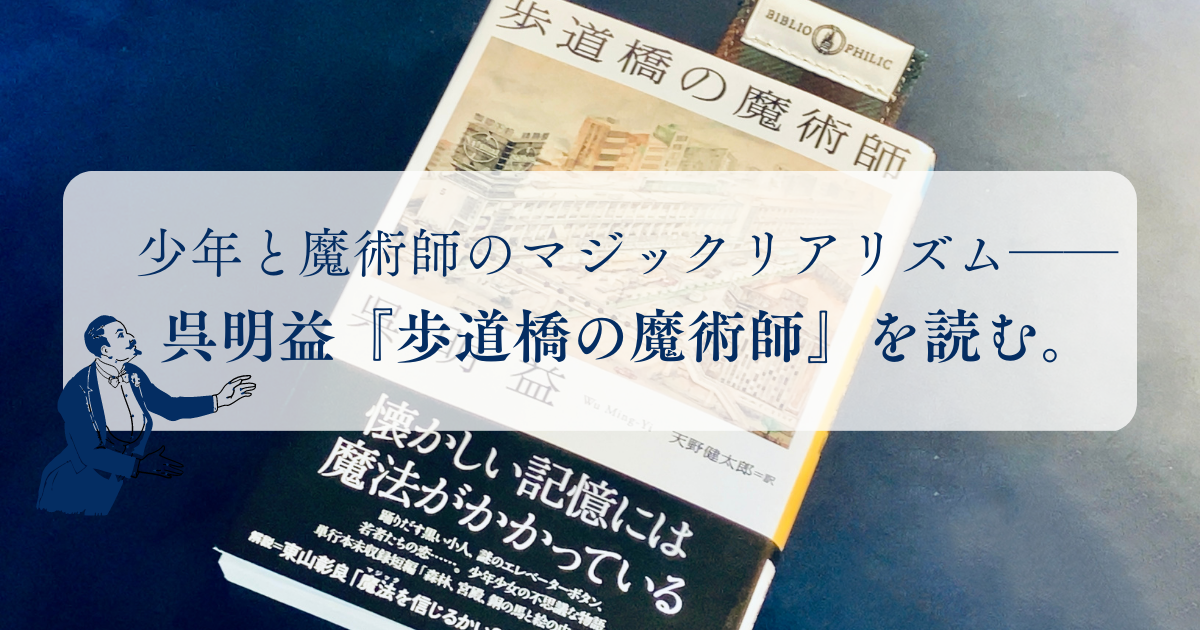
最近、持ち歩いていた本。呉明益の『歩道橋の魔術師』
こんにちは、もの書きのkazumaです。最近、持ち歩いて読んでいる本があって、それが『歩道橋の魔術師』です。これは呉明益(ウー・ミンイー)という台湾の作家が書いた短編集で非常に面白かったので、今回、ブログで取り上げて紹介することにしました。
この本は数年前に単行本で買っていました。古本屋さんで状態がいいものが売られていたので、つい手に取って積んでいた本です。
しばらく置いていたのですが、自分が短編を書きはじめていたこともあって、現代の海外作家はどんな風に短編を書くのだろうと思って、読みはじめました。文庫版が出ていたので、もういちど新刊書店で買い直しています。
冒頭のエピグラフで南米の作家ガルシア=マルケスの言葉が引用してあるのが気になったので、ここでちょっと載せておきます。エピグラフは大抵の場合、物語全体のキーポイントになっていたりします。
わたしが本当になりたかったのは魔術師だった。でもマジックをするとき、すごく緊張してしまうので、仕方なく、文学の孤独に逃げ込んだ──G・ガルシア・マルケス
『歩道橋の魔術師』呉明益著 天野健太郎訳 河出書房新社(2021)文庫本 p.6より引用
僕はとりあえず表題作の『歩道橋の魔術師』と、その次の『九十九階』を読み終え、そして『石獅子は覚えている』の章を読みはじめたところなのですが、この短編集は久々の『当たり本』だと思いました。
『歩道橋の魔術師』はどうも連作短編集のようで、ひとつの話に出てきた人物や場所が、別の章でも登場していたりします。その核となる話が冒頭の『歩道橋の魔術師』で、舞台は中華商場という台北に実際にあった場所がモデルとなっています。単行本版のカバーにはイメージ写真が映っていますね。
表題作の主人公はまだ年端のいかない、小学生の少年で、彼が歩道橋で物売りをしている魔術師に魅せられたことからはじまります。
少年は親から小金を稼いでくるように言いつけられ、中華商場にいくつかある歩道橋の内で、「愛」棟と「信」棟のあいだに掛かっている歩道橋の上で、同じようにもの売りをはじめます。
少年の家は靴屋なので売っているのは靴の中敷きなのですが、幼い少年の目は歩道橋の上を通り過ぎていく人々や、そこで売られている様々な品物に注がれていきます。
偶然にも少年の目の前にいたのは怪しげな魔術師で、少年は徐々にこの魔術師の手品に惹かれていくことになります。
中敷き売りの少年の『幼さ』が物語の鍵
語りは幼い少年の視点で書かれているのですが、この「幼さ」というのがひとつ、小説のポイントとしてあるなと思いました。
台北に住んでいる大人たちにとっては見慣れた中華商場の歩道橋も、子どもの目線で見ればそこは未知の世界です。
中敷き売りの少年は純真そのもので、歩道橋を通りがかった通行人が皆知っている魔術師の手品のタネを、子供心ながらに信じ込んでしまったり、魔術師から教えて貰った手品を浮き足立って兄に披露すると簡単に見抜かれてしまったりと、あどけなさが残る少年です。
新公園(台北駅の南にある)よりも遠いところには行ったことがない、と打ち明けている通り、この少年は自分が住む世界がどんなところだか、まだ知りません。
魔術師から手品の道具を買ってそのタネを教えて貰うと、少年はこんなことを語ります。
そういうことか! 紙に書いてある手書きの文字を読んで、「そういうことか」と言いたくなった。ぼくはこのとき、マジックのすべてを知ってしまったんだと思った。十一歳になって同級生に片思いしたとき、自分は愛のすべてを知ってしまったんだと思ったのとまるで同じように。
『歩道橋の魔術師』呉明益著 天野健太郎訳 河出書房新社(2021)文庫本 p.12より引用
幼いけれど、少年の視点が鮮やかに現れている、いい文章だと思います。原文は読めないので分かりませんが、これについては訳者の天野健太郎さんの訳が優れていて、この物語の驚きを損なうことなく、うまく伝えている文章ではないかと思います。
海外文学を読むときに、作品世界に没入できるかどうかは訳者の技術的な力量によるところが大きく、僕はこの訳文ならすんなり入り込めると思いました。
話を作品に戻すと、この少年の幼さというのは、大人達にとって見れば、簡単に手品に引っかかってしまう、騙されやすさと繋がっていますが、一方で、この中敷き売りの少年は幼いゆえの好奇心に満ちていて、魔術師の秘密を探ろうとします。
歩道橋の魔術師というのは、その場を通り過ぎる大人達にとっては、子どもに向かって手品のタネを売る、インチキっぽい詐欺師です。
魔術師のことをほんとうに魔術師だと思っているのは、世界でただひとり、この中敷き売りの少年だけです。
少年は魔術師と少しずつ親しくなり、手品の売り場を任されるようになって、紙でできた黒い小人の人形に魅せられていきます。
雨が降ってその黒い小人がぺしゃんこになったとき、少年はまるでほんとうにひとが一人死んでしまったかのように、雨の中で「小人が死んじゃった!」と絶叫します。
もちろん、周りのひとにとってはただの紙でできた、仕掛けのわからない人形です。でも少年にとってそれは、ほんとうに魔法の人形だったのです。
この周囲の大人達の客観的な現実と、まだ小学生の少年にとってのリアルな主観、その間に揺さぶりを掛け、魔術師は奇妙な世界に少年を誘っていきます。
言ってみれば「歩道橋の魔術師」というのは、この物語内において、ハーメルンの「笛吹き男」と同じ役割を持った人物なのです。
もうすっかり成長してしまった兄は、弟が魔術師に連れ去られてしまうのではないかと危惧して、商場に行かせないように母に告げようとします。
兄から見れば、この弟は簡単な手品も見抜けない、手の掛かる弟です。また魔術師に騙されて、今度はほんとうに弟が怖い目に遭うのではないかと考えているのです。
中敷き売りの少年が見ている魔術師のマジックは、ただの仕掛けのある手品なのか、それともほんとうの魔術なのか――。
魔術師が仕掛けた魔術の相手は誰か? マジックリアリズムの秘密
ここで冒頭のガルシア・マルケスの引用が思い起こされます。ガルシア・マルケスの十八番と言えば、マジックリアリズムです。
現実の世界のなかではあり得ないことが、小説の世界のなかではごく当たり前に起こってしまう。それがマジックリアリズムです。
この『歩道橋の魔術師』という作品は、まさにマジックリアリズムのお手本のような作品です。
読者は、この幼い少年の視点に『慣らされ』ていて、魔術師を疑ってかかる大人のような視点から、そんな魔術を信じてしまう少年の視点にスライドするように、あえて一人称で書かれています。それも中華商場を生き生きとした目で眺める子どもの語りで。
たぶん理性の冷めた目で見てしまっては、このマジックリアリズムは、ほんものの「マジック」にはならないのです。
でも、魔術師の手品がほんとうの魔術だと思い込めるように書かれてあったとしたら、それは「マジック」になります。
読者にとっては、この「少年の目線=読者の目線」になるように仕組まれていて、この歩道橋の魔術師は、少年の目を奪うことで、それと同時に読者の目も一緒に奪っているんです。
客観的な大人の目で見れば、紙人形がタネや仕掛けもないのに動く、なんていうことはありえません。起こりうるはずがないと思っている。
でも小説の世界のなかでは、そういうことが起こりうると錯覚する。その錯覚した世界で見える面白さが、マジックリアリズムの面白いところで、言ってみればそれはいままで見えていなかったものの見方を、フィクションを通して獲得することでもあるんです。
それが新鮮に見えれば見えるほど、マジックリアリズムは面白いんです。これは視点が揺れる(動く)のを体験する面白さです。
普段僕らが見ているのは、手品のタネも仕掛けも分かってしまった、そういうしらけた世界です。
でも、子どものころにはそうではなかった、そう見えてはいなかったはずです。
まだ子どもの頃は、商店街を歩くだけでも冒険だったし、手品のタネもわからないし、誰かを愛することも知らない。この世界の仕掛けやからくりなんか、ひとつも知らない。
でも、そんな頃に見たものを、大人になってから見ると、ずいぶん違って見えると思うんです。
誰だって最初は自分が世界の真ん中にいると思い込むものだし、そこからべつの誰かの目を取り込んでいくことで、客観的な視点を(擬似的に)獲得したつもりになって、段々と目の前の世界が、昔思い描いたような世界ではなかったことに気が付いていきます。
言ってみれば少年の目を失っていく。そんな大人の世界で不思議なことはもう「起こりえない」。
大人の目で見れば「起こりえない」、でも子どもの目で見れば「起こりうる」。その落差をうまく使って読者にマジックを掛けているのがこの作品です。
中敷き売りの少年は結末で、魔術師の秘密を知ることになります。そこでは「起こりえない」ことが「起こって」いて、読者は「起こりえない」世界から、「起こりうる」世界へと一瞬で連れて行かれます。
歩道橋の魔術師が魔術を掛けている相手は少年なのですが、その少年の視点に憑依して読むのは僕たち読者なので、読者は少年と一緒に視点ごと持って行かれてしまう、という構造になっています。
作者は魔術師か? もうひとつの「タネ明かし」
僕がこの短編を読んだときに、これは少し「タネ明かし」になっていると感じた文章があって、あとで読み返したときにどうも気にかかった箇所があったので、引用しておきます。
魔術師が少年に向かって小人の魔術について語るシーンです。
「子供のころ、チョウを捕まえて標本にすれば、チョウが自分のものになると考えていた。長い時間をかけてやっと、チョウの標本はチョウではないってことに気づいた。わたしはそれを見抜いたから、黒い小人のような本当のマジックが使えるようになったんだ。頭のなかで想像したものを、お前たちが見えるものに変えるだけだ。わたしはただ、お前たちの見ている世界を、ちょっと揺らしているだけなんだ。映画を撮る人間がすることと何も変わらない」
『歩道橋の魔術師』呉明益著 天野健太郎訳 河出書房新社(2021)文庫本 p.27より引用
これって魔術師の言葉、ということになっていますが、何となく、マジックリアリズムを小説の中で使えるようになった作者の言葉でもあるように見えるんですよね。僕にはこれがわざとやっている自白のように見えます。
いくら本を読んでも、たぶん小説のなかで「マジック」が使えるようになるわけじゃないんです。
小説のなかでマジックが使えるようになるには、想像の中で見たり、聞こえたりしたものを、相手(読者)にもそれが見えるように言葉で置き換える技術が必要になります。
それは本や小説を標本みたいにいくら集めても身につくものではありません。書きながら身につける技術です。
とりわけマジックリアリズムは、その読者の視点すらもうまく操って、いま読者や僕たちが信じている目の前の世界に揺さぶりを掛け、それとはべつのもうひとつの世界を丸々ひとつ、文章でこしらえなくてはなりません。
そして読者を、そのこしらえた世界にほんとうに連れ込めるかどうか、それがマジックリアリズムがうまくいくかどうかの、「分かれ目」です。
文章で読者を巧みに連れ込んで、書かれてあるような不思議なことがほんとうに起こりうる、と信じ込ませることができたら、それはマジックリアリズムになります。
でも、そういう境目を越えるところまで読者を誘うことができなければ、ただヘンテコなことばかり起こるよくわからないお話、で終わってしまいます。
なんとなくこれは小説というマジックを使えるようになった作者の言い分が浮かんでいる気がします。
わざとやっているのか、知らずにやったのかはちょっと判断が付きかねますが、たぶん僕はわざとだと思うんですよね。ガルシア・マルケスを引用してくるくらいなので、少し勘がいい読者なら、マジックリアリズムの話だとすぐに気が付くし、だったらあえて作者が表に出てくることくらい、やりかねないなと思っていて。
物語としても、作品の構造も、そこに仕掛けられた魔法も、どれもみな鮮やかな手並みで美しいので、おすすめの短編集です。ぜひ一度、手に取ってみてください。
kazuma
noteで最近、もの書きの暮らしについて考えたことを綴りました。Panasonicとnoteが主催のコンテスト『#どこでも住めるとしたら』に応募した記事です。よかったらスキで応援よろしくお願いします。