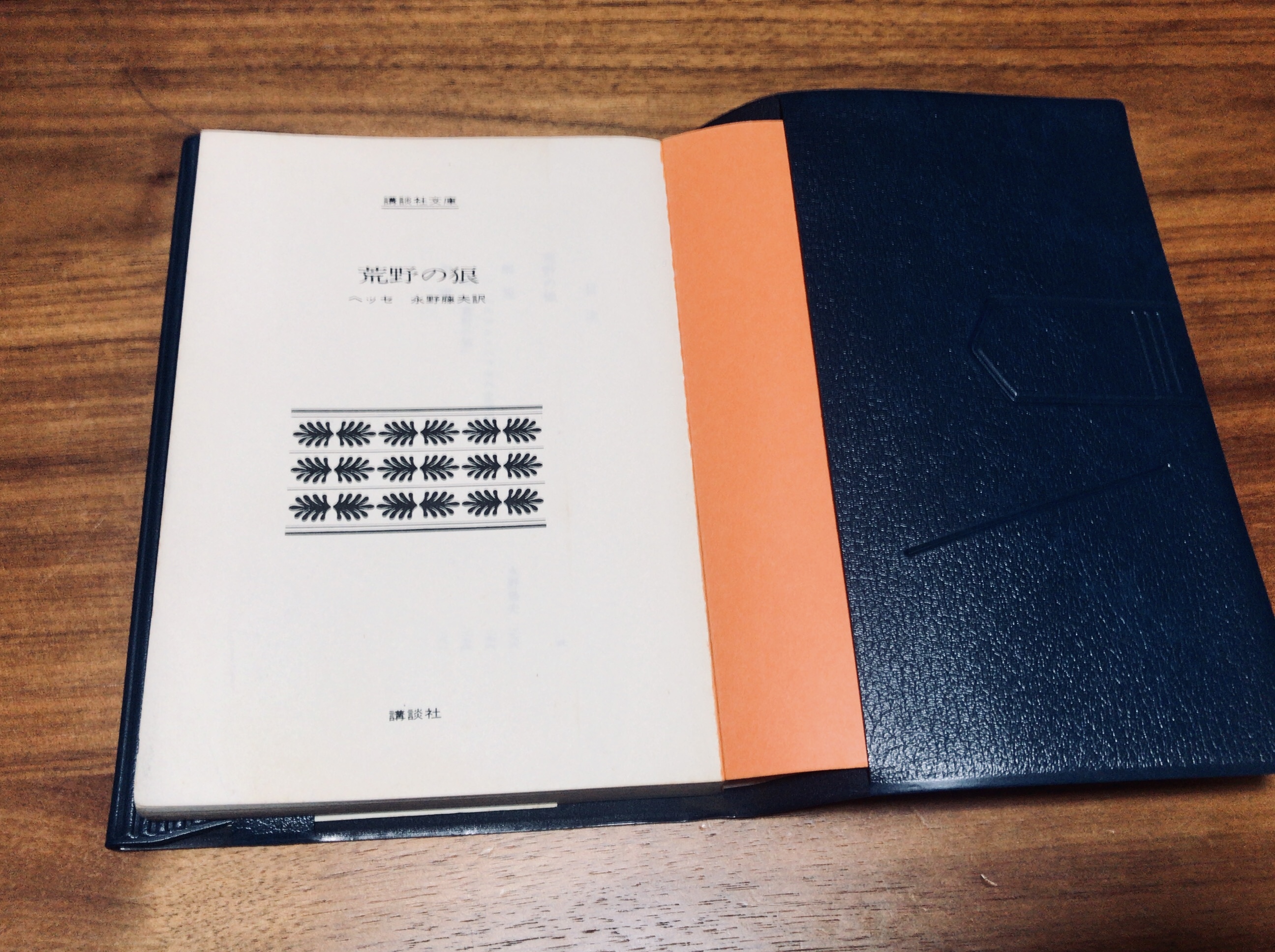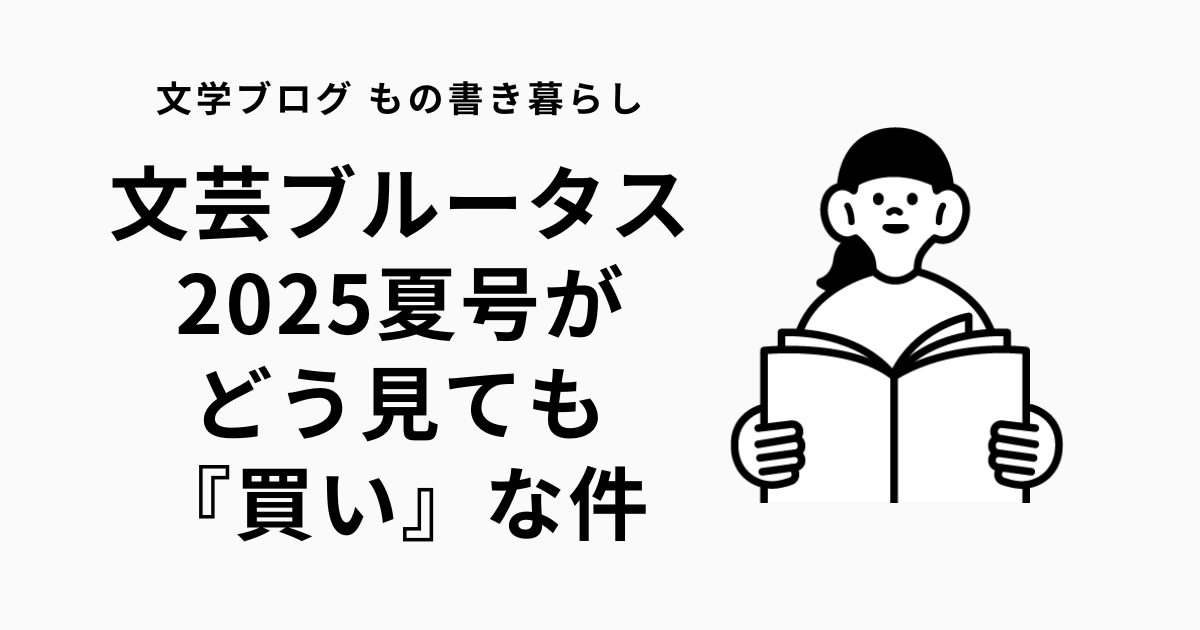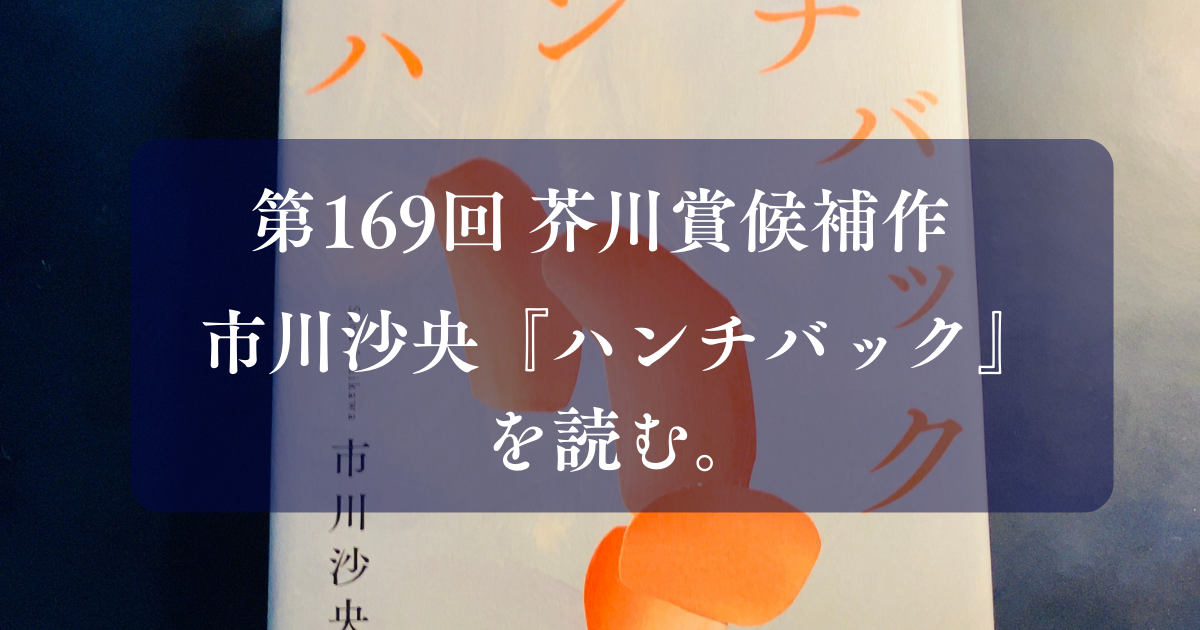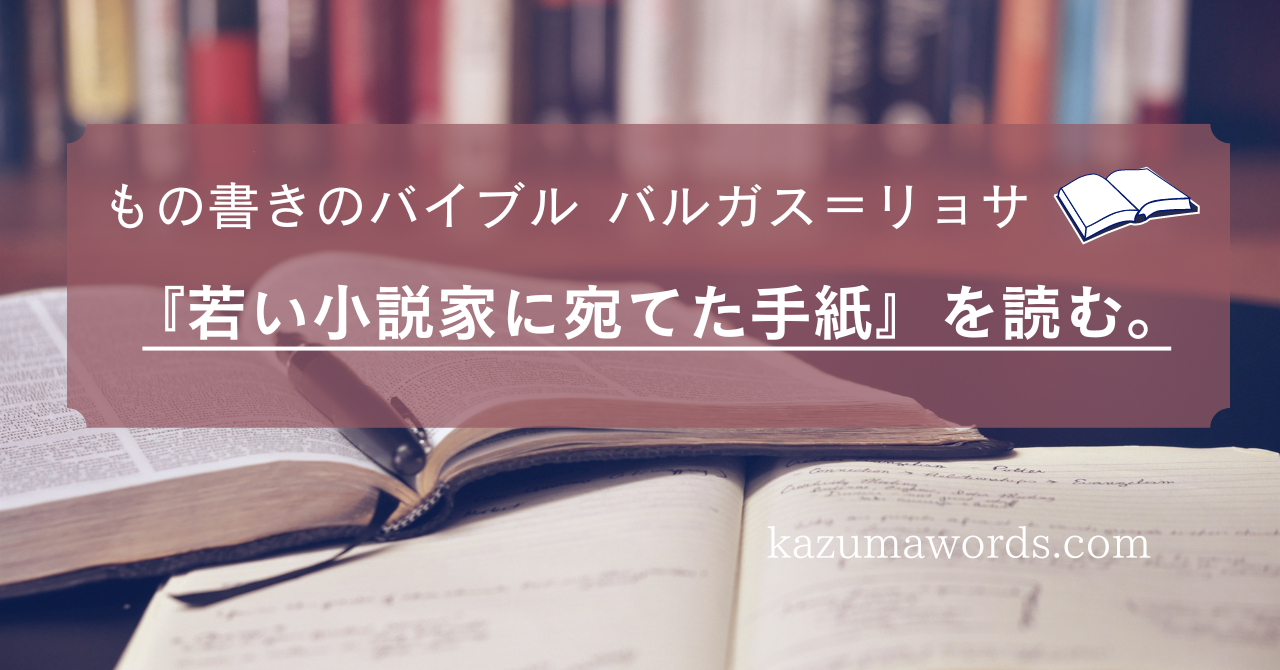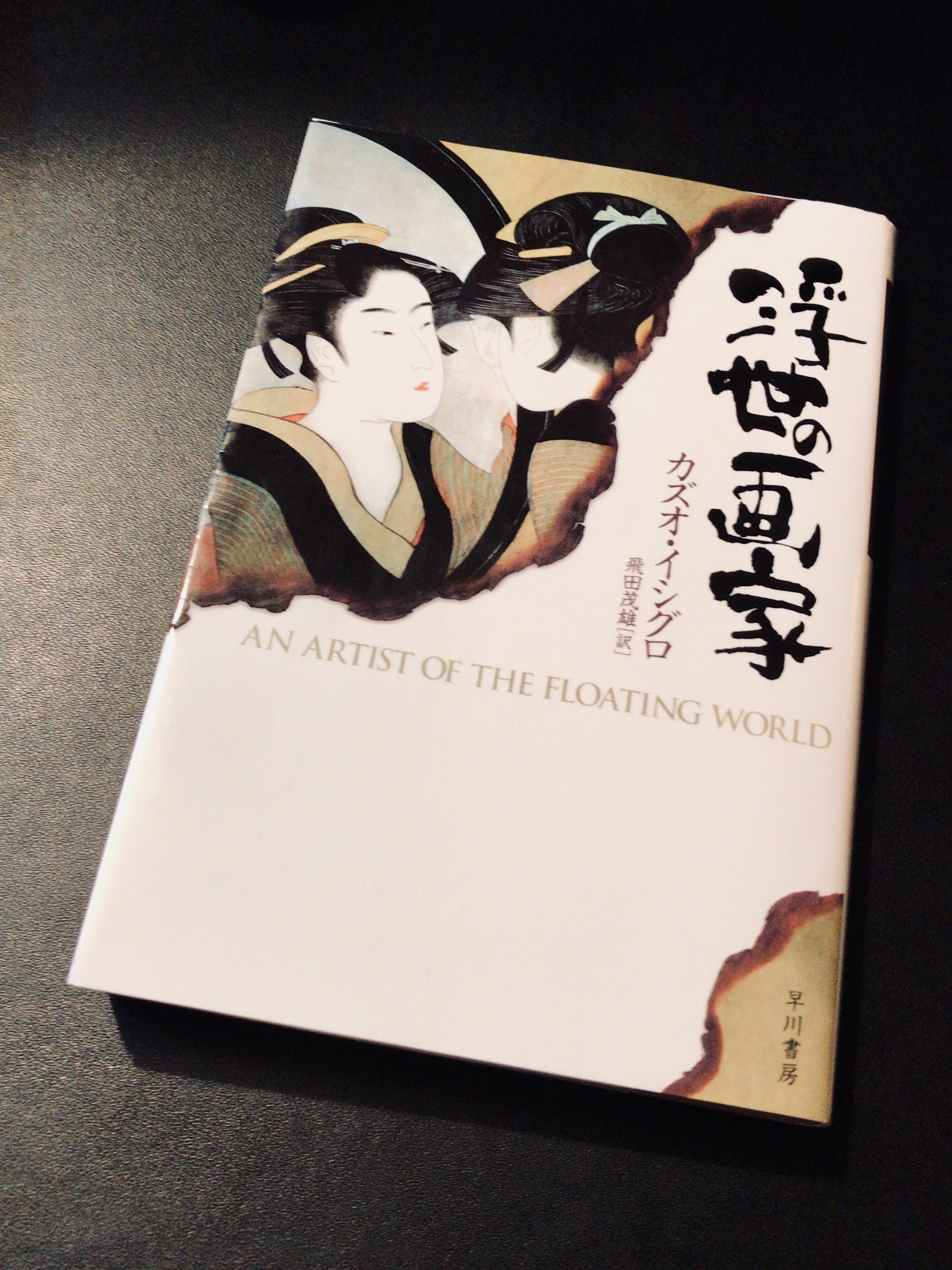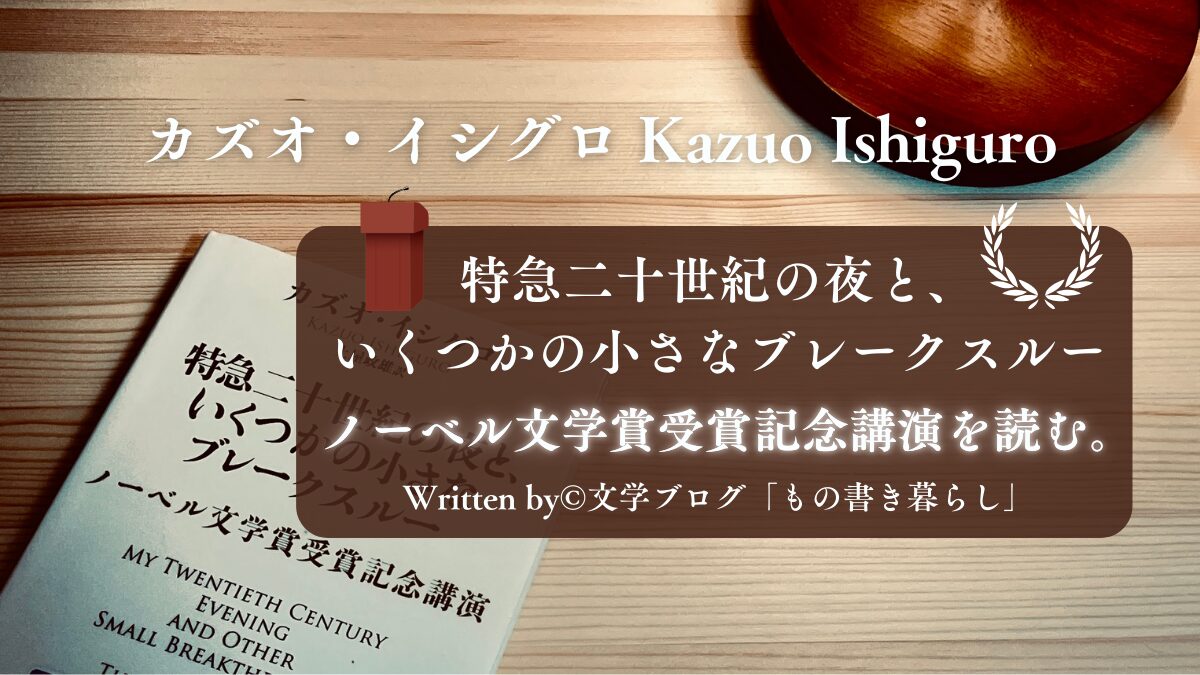【文学都市伝説】「ライ麦畑でつかまえて」の怖い読み方

J・D・サリンジャーの代表作に「ライ麦畑でつかまえて(The Catcher in The Rye)」があります。
日本でも白水社から刊行されている野崎孝さんの邦訳(1964年)が有名で、半世紀以上にわたって若者世代に読み継がれてきました。

2003年には村上春樹さんによる新訳版の「キャッチャー・イン・ザ・ライ」が出ていて、近年では、新海誠監督作品による「天気の子」でも主人公の帆高の愛読書として村上版の「キャッチャー・イン・ザ・ライ」が作中に登場し、リバイバル・ヒットするなど話題に事欠かない一冊です。
ですが、一方で「ライ麦畑でつかまえて」には「曰く付き」の面があることをご存じでしょうか?
たとえばジョン・レノン射殺事件の主犯となったマーク・チャップマンが犯行現場で「ライ麦畑」を読み耽っていたり、レーガン大統領暗殺未遂に関わったジョン・ヒンクリーも愛読書として「ライ麦畑」を持ち歩いていた、といいます。
しかし、「ライ麦畑でつかまえて」の作品のなかで、主人公のホールデン・コールフィールドが誰かを実際に撃つシーンや、あからさまな暴力に訴えて不満を持つ相手を打ち倒すシーンはありません。
にもかかわらず、なぜこれほどまでに「ライ麦畑」の熱狂的な愛読者の一部が事件を引き起こすようになっているのか?
今回は【文学都市伝説】として、「ライ麦畑の怖い読み方」に迫っていきましょう。
【文学都市伝説】ライ麦畑の怖い読み方
評価が真っ二つに割れる「ライ麦畑」の熱狂と拒絶

「ライ麦畑でつかまえて」は、読む人によって評価が真っ二つに割れる作品として有名です。
ある人にとっては「ホールデンほど自分の気持ちを代弁してくれているやつはいない」と感じたり、ある人にとっては「ただ若者が延々と文句を言っているだけの現実逃避でしかない作品」とみなしたりします。
初見では、だいたいこのどちらかになることが多く、熱狂的に迎え入れるか、あるいは冷淡な目で拒絶するか、という意見が多いようです。
もう少し距離を置いて何度も読み直していくと、そのどちらでもない読み方に近づいていくところがあります。
「ライ麦畑でつかまえて」のあらすじ

「ライ麦畑」のあらすじをざっと簡単に話しておくと、ホールデン・コールフィールドという16歳の高校生の男の子がペンシルヴァニア州にある高校(ペンシー高校)を退学し、当てもなくニューヨークの街をさまよい歩く三日間を描いた物語です。
ホールデンは出会った大人達の矛盾や嘘(インチキ)を見抜いて、矢継ぎ早に罵倒していきますが、最後の最後までホールデンは大人達の論理を受け容れることができません。
年齢的にはあと一歩のところでホールデン自身も成人なのですが(アメリカでは16歳で車の運転が認められ、大人の仲間入りをする慣習がある)、ホールデンは大人の「矛盾や偽善に満ちた振る舞い」を受け容れられず、学校を飛び出した先の、ニューヨークのどこにも自分の居場所を見つけられないでいます。
やがてホールデンは、恋人のサリー・ヘイズに、友人から車を借りてニューヨークを離れ、マサチューセッツやヴァーモントのような小川のあるところで二人で暮らそう、という非現実的な提案(ホールデンの所持金はたった180ドル)をしますが、もちろん断られます。
学校からの放校処分のあと、身近な教師、友人、元恋人、街中のピアニスト、エレベーターボーイ、娼婦、尼僧など、沢山の人たちと出会っては幻滅を繰り返し、どこにも居場所を見つけられなかったホールデンは、結局、実家へ戻って妹のフィービー・コールフィールドに出会います。
この作品のなかで唯一といっていい、ホールデンの理解者はこの小さな妹、フィービーだけなのですが、当然、実家には両親がおり、ホールデンの放校処分をよく思わないことは明らかで、ホールデンは落ち着いて家にいることさえできません。
妹のフィービーのためにホールデンはレコードを手に入れ、プレゼントしようとします。
このレコードをホールデンは道中でうっかり「落として」しまい、レコードは砕けてしまいます。(この物語では「落とす」ことと「拾う(キャッチする)」ことが重要な鍵になっています)
けれども、フィービーは兄の気持ちをよく分かっていて、そのかけらをちょうだい、と言ってナイトテーブルの引き出しにしまいます。
そして、フィービーは、「兄さんは世の中に起こることがみんなきらいなんだわ」と、ホールデンの心情を見抜き、何か好きなもの、なりたいものを言ってよ、と兄にお願いします。
そこでホールデンは、「ライ麦畑の崖から落ちていく子どもをつかまえる」という理想を、妹であるフィービーに語って聞かせます。
かなり端折っていますが、大筋としてはこんなところです。
ホールデンは「大人になれない若者の象徴」?

熱狂か拒絶か、どちらかに割れやすいのは、おそらく主人公のホールデン·コールフィールドへ抱くイメージが関係していると思われます。
ホールデンはいわば「大人になれない若者の象徴」として読まれやすいところがあります。
たとえば、彼は社会にいる大人達の胡散臭さの急所を突くように文句を並べ立てているのですが(それも見事なまでに)、結局のところ、ホールデン自身がこの物語でやったことは延々とニューヨークの街で「居場所がない」と嘆いて、放浪しつづけることです。
もちろんそれは若者の特権というべきところでもあるし、彼の年齢から言うと妥当なラインなのですが、この先もずっとそれでいくと、社会生活は成り立たなくなってしまう。そのぎりぎりの年齢にホールデンは立っています。
ただホールデンにとっては、そんな現実の規範や大人の常識なんかはどうでもよく、自分にとっての理想(すなわち、無垢な子どもの世界が守られること、大人の嘘や欺瞞とは無縁=イノセントでいること)を最優先に生きようとしているわけです。
この物語の悲劇的なところは、ホールデンの理想は人間には叶えられないことで、なぜかというと、彼自身は年を取るにつれて子どもではいられなくなり、やがてホールデン自身も無垢な存在ではなくなってしまうからです。
無垢な子どもを守れる可能性があるのは、無垢ではない大人達なのですが、ホールデンは子どもの側に軸足を置こうとしたまま、子どもたちの居場所を守ろうとしています。
自分が無垢なままで子どもたちの世界を守れる場所=ライ麦畑をホールデンは探しているのですが、そんな場所はこの世のどこにもありません。おそらくそれは死んだ弟のアリーや、学校の窓から飛び降りたジェームズ·キャッスルのように無垢なままで時間の停まったところにしかありません。(だからホールデンは展示物がちっとも変わらない博物館を好みます。)
つまり、ホールデンはこの世にはぜったいにない理想の場所を探し求めている少年なのです。
作中でホールデンは、酒を飲もうとしたり、煙草を吸ったり、娼婦を部屋に呼ぶことさえしているわけですから、もう子どもと呼ぶのは難しいところに足を踏み入れています。
日本社会で「ホールデン・コールフィールド」の物語が受け入れられにくい背景

「子どもではないが、大人でもない」モラトリアムを抱えた青年というのは、大人から見れば「もどかしい」「痛々しい」存在に見えるものなのではないでしょうか。
とくに日本社会では、「建前文化」もあって、建前を抜きにしてしらふで本音を話すことを毛嫌うところがあると思います。
ホールデンがつねに本音を喋っているわけではないのですが、「学生である」という建前(通過すべき儀礼)を抜かして、喋っていることは明らかなので。
また過度に「大人になること」「社会に適応して生きること」が奨励されている面もあり、社会の責任を負わない子どもに対しては人格を認めないところがあります。
一人だけ無垢のままでいようとするホールデンを「幼い」「ずるい」「そんなものは恥だ」と切り捨てられることが、大人であることの証明のように思われている。
そんなつまらない先入観で「ライ麦畑」を読んでしまうと、この小説のいちばんいいところを取り逃がしてしまうのですが。
「ライ麦畑」をよく読まずに拒絶する派の意見としては、「ホールデン」がいわば大人になる上で乗り越えるべき「踏み絵」になっています。
「こんな理想ばっかり言って何もできていないやつは駄目だ、おれは(わたしは)こんな生き方はしないし、現実にいたら認めないぞ」という意見が大勢(たいせい)かなと思います。
また発刊(邦訳)当時は、反響が大きかったこともあり、いわば流行書のようになっていた「ライ麦畑」に対して、浮かれたように読み耽っている同世代の若者たちにうんざりした、という時代背景も重なっているかもしれません。
次は、熱狂する側の視点で「ライ麦畑」を見てみるとどうなるでしょうか?
「ライ麦畑」の最も怖い読み方は「ホールデンを英雄視」すること

「ライ麦畑」に熱狂する世代としてすぐに思い浮かぶのは、やはりホールデンと同年代の「大人でもなく、子どもでもない」ティーンエイジャー(ハイティーン)でしょう。
彼らにとってホールデンは、モラトリアムを抱える世代の胸中を代弁し、大人達を相手に胸の空くようなことを言ってくれるので、「ライ麦畑」は長い間、若者達のバイブルと呼ばれてきました。
とくに子ども時代に子どもらしくいることを許されず、大人と呼ばれる年齢になっても違和感を感じ続けるアダルトチルドレンの場合、大人に向かって言いたくても言えなかったことを、ホールデンが清々しいまでにののしってくれることで、カタルシスを得る面もあるかと思います。
問題となるのは、感情移入しすぎた読者がホールデンをまつりあげてしまって、自分もホールデンのようになろうとすると、かなり困った事態が生まれます。
なぜかというとホールデンは作中で「変わらない存在」でいようとするからで、フィクションのなかの極めて限定的なシチュエーションのなかでのみ成立する人格だからです。
「ライ麦畑」はホールデンが16歳でなければ成立しない物語

たとえばホールデンが16歳でなかったとしたら、ライ麦畑の話って成立しないんですね。
16歳のホールデンが幼いフィービーをメリーゴーランド(回転木馬)に乗せて遊ばせているシーンでこの話は終わりますが、あれが美しく見えるのは、彼らがまだ子どもの側に立っているからです。
年を倍にして32歳のホールデンと20歳のフィービーがいるとしたら、ホールデンが大人たちを罵倒する意味も変わってきてしまう。
フィービーがいつまでも兄の理解者でいるとは想像できません。おそらくそれは歪んだものに近づいていくでしょう。
(もちろん自分たちなりのイノセントを守るという話にすることはできるかもしれませんが、そうなるとライ麦畑の話はどこかへ行ってしまう)
成長を拒むホールデンを、現実で模倣することの危険性

「ライ麦畑」ではホールデンに成長というものはほとんど見られないのがひとつの鍵になっています。
確かに青少年期の「地獄めぐり」は済ませたけれど、だからといってホールデンが「アントリーニ先生。もうライ麦畑の子どもたちなんてどうでもいいんです、理想を探すのは疲れちゃった。そろそろニューヨークへ戻って学校に行って働きに出ます。さよなら、フィービー。おまえもちゃんと学校へ行くんだよ」っていう風にはならないと思うんです。
「ライ麦畑」というフィクションのなかでは美しく見える態度も、現実にそのままぽんと取り出してしまうと、怖い読み方になります。
具体的には、まったく成長しないことを善しとし、自分でさえ子ども達を崖から落としかねない側の大人に近づいているにもかかわらず、その自己矛盾には一切気が付かず、一方的に大人の社会を攻撃しつづける精神性を獲得することになります。
どうしてこういう視点が生まれるかというと、すべて主観のみでものごとを見てしまっていて、なぜか自分だけが「無垢やイノセント(無罪)のままでいられる、だからインチキな連中が集まった大人達の社会には何をぶつけても許される」と勘違いをしてしまう。
それを訂正しうるのは周囲の人間との関わりなのですが、もともとの生い立ちで人間関係が絶たれていたり、思い込みが強度になっていくと、あえて関わろうとするひともいなくなり、幼い精神性が維持されたままになってしまう。
マーク・チャップマンやジョン・ヒンクリーの事件当時はおそらくこのパターンで、彼らは「ライ麦畑」を誤読したために、銃撃犯にまでなってしまったと言われています。
正確に言うと「ライ麦畑」は引き金になっただけであって、もともと彼ら自身の現実生活に問題があった、というのが実情と言えそうですが。
誰もライ麦畑のホールデンにはなれないし、永遠に16歳のまま年を取らないでいられるのは本のなかだけです。
「ライ麦畑」を見つけられなかったひとはどこへ行く?

ホールデンを模倣して、マーク・チャップマンやジョン・ヒンクリーの方向へ行かなかった場合、行き先はいくつかあるんですが、作者のサリンジャーはコーニッシュの田舎に自宅を建てて塀を作り、家族は離散しました。
ホールデンが言った「とりあえずニューヨークを離れて、誰も自分のことを知らない西部の田舎に小屋でも建てて、そこで耳も聞こえず、目も見えない人間の振りをしていよう。そうすれば、誰とも口を利かずに、向こうの方でも自分を放って置いてくれるだろう」(要旨)という考えをサリンジャーは地で行ったことになります。
実際には、田舎の街中の喫茶店に顔を出したり、近所のひとには気さくな住人として知られている一面もあり、世の中で思われているほどまったくの「世捨て人」ではなかったわけですが。
他の行き先は、ホールデンのようにサナトリウム(すなわち精神病棟)へ行ってしまうか、社会とは距離を置いた生き方を志向することになります。
ライ麦畑の物語が響くひとってたぶんみんな相当な生きづらさを抱えたひとばかりだと思います。
やっぱり生い立ちや境遇、精神的な気質を含めて、どうしても世間に馴染むことができないひとっていると思うんです。
そういう人のための居場所って社会のなかではほとんど想定されていなくて、レールから外れてしまったのは自己責任だよねという風になってしまっているのが問題かなと思います。
ほんとうは個人の努力とか選択とか、そういうものではどうにもならないところで生きづらさを抱えているのに、社会の側はそんなものは乗り越えて当たり前、という顔をしている。すべての人が同じ条件やハンデを背負っているわけではないのに。
それでマーク・チャップマンやジョン・ヒンクリーのような事件が起きてから、一斉に騒ぎ出してこれは異常な犯人のせいで、我々とは一切関わりがない人物が起こしたことだから、と溜飲を下げているのですが、マーク・チャップマンもジョン・ヒンクリーも生まれつきでそうなったとはどうも言い切れない。
社会に馴染めない人の居場所を奪っていき、社会と距離を置くニッチな生き方もまったく容認しないとするならば、構造的に言って第二・第三の銃撃犯は生まれてくるし、それはもう実際に生まれていますよね、という話になります。
そういうひとの心情に寄り添ってくれるものって、現実の中で見つけるのは難しいですよね。
生い立ちや環境、人間関係に絶望したり、ぽっかり空いてしまった空洞をどうにかしようとして、手を伸ばした先にあったのが、たまたま「ライ麦畑でつかまえて」だった。「これはおれのことが書いてある」。そう思うのも無理はありません。
でも、もし彼らが「ライ麦畑」に出会う前に、たとえ世の中のひととは違う生き方でも、自分の居場所を見つけられていたら、結果は違っただろうと思うのです。
自分がいま立っている場所が生きるに値する世界だと分かったら、「おれ」と「ホールデン」の間には区切りが生まれて、フィクションと現実の人生をくっつけなくても生きていけるはずだから。
そうすれば「ここには確かにおれの理想が書かれていた、でもおれはホールデンにはなれないし、なる必要もないんだ」と分かって、大事なレコードをナイトテーブルの引き出しにそっと入れるように、この物語を胸の奥に仕舞っておけただろうから。
2024/07/20
kazuma
お知らせ:
文学ブログ『もの書き暮らし』の公式アカウントとしてX(Twitter)を再開することになりました。
よかったらフォローで応援してくださると嬉しいです。
最新記事の告知などを行います、中の人(kazuma)もときどき呟くかも。
「もの書き暮らし」X公式アカウントはこちら(@kazumawords)
久しぶりの方も、初めましての方も、どうぞよろしくお願いいたします。