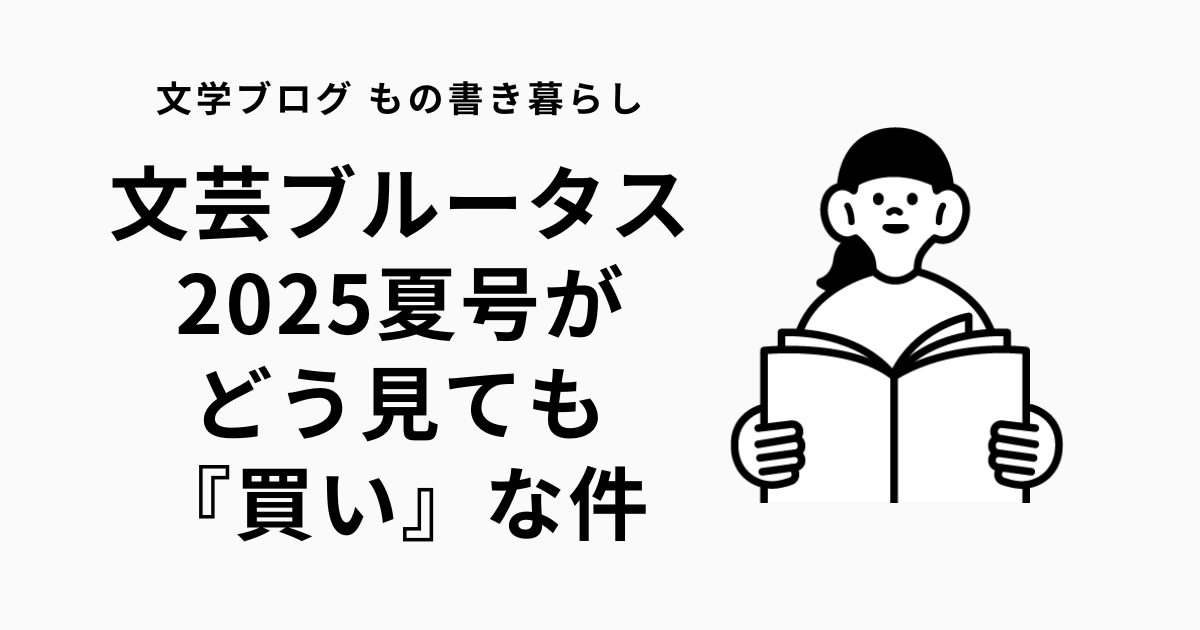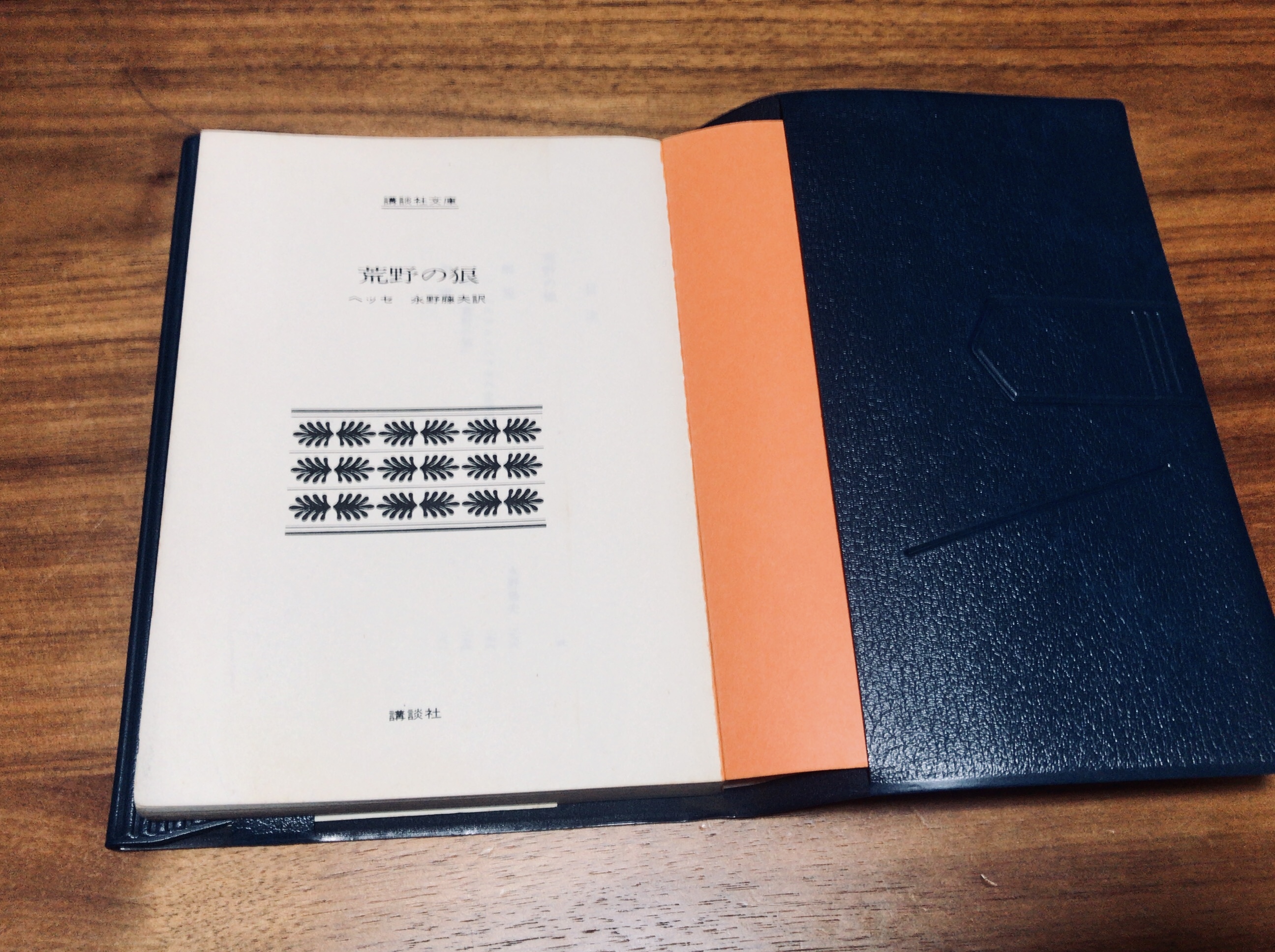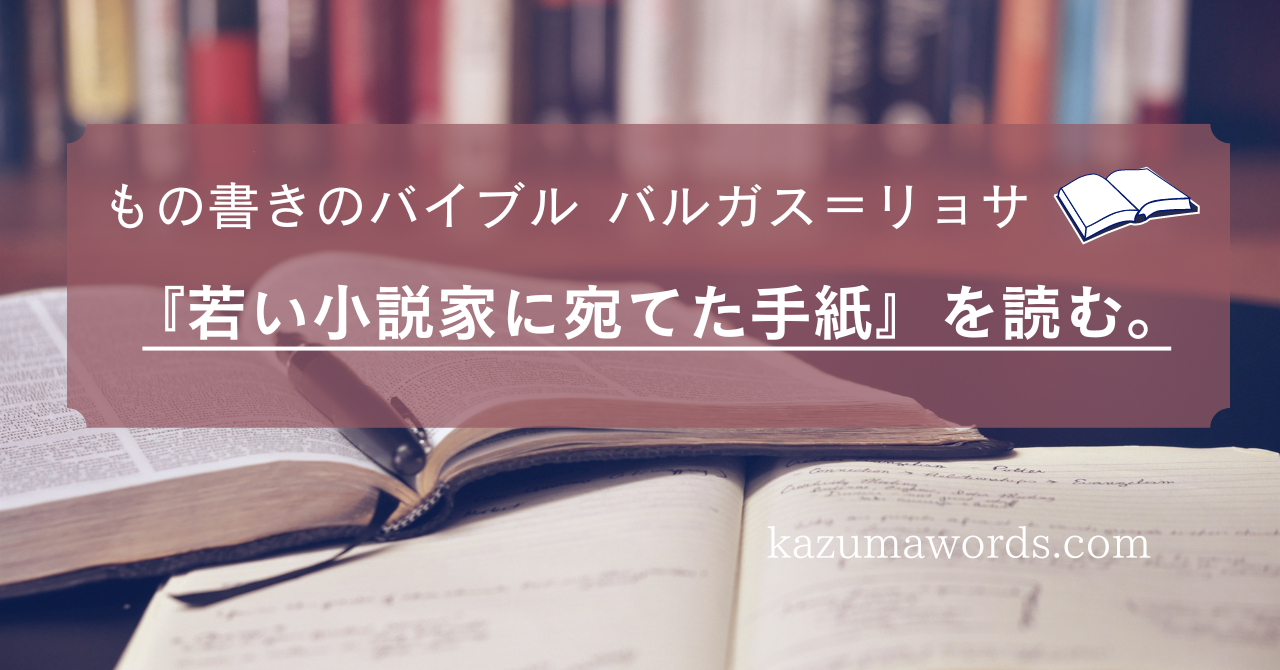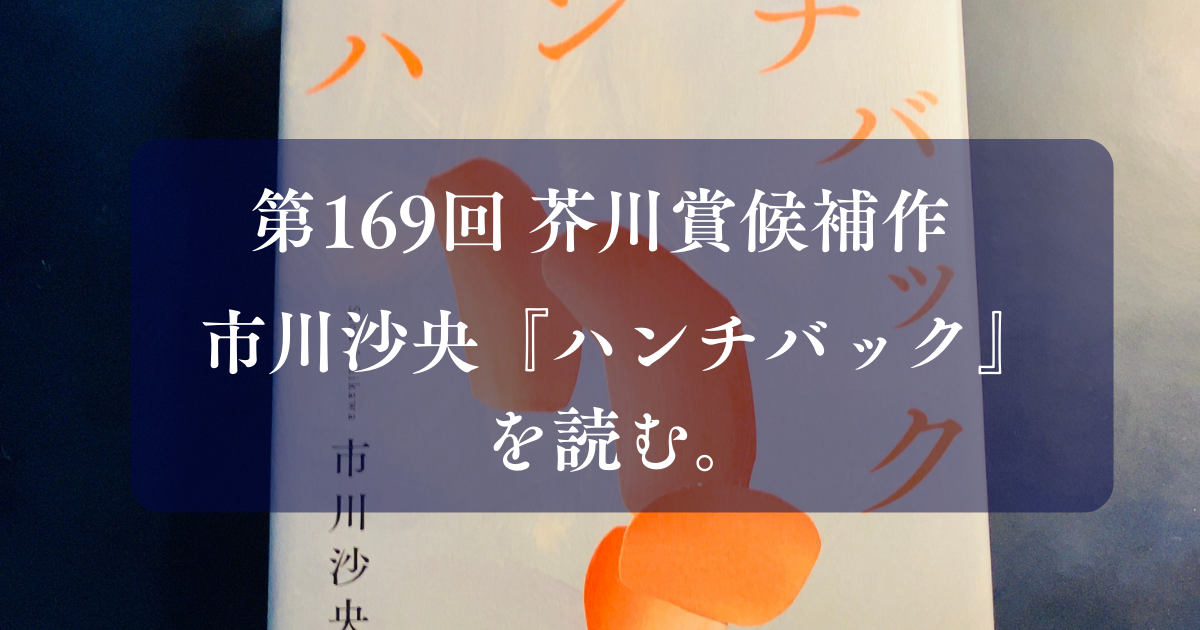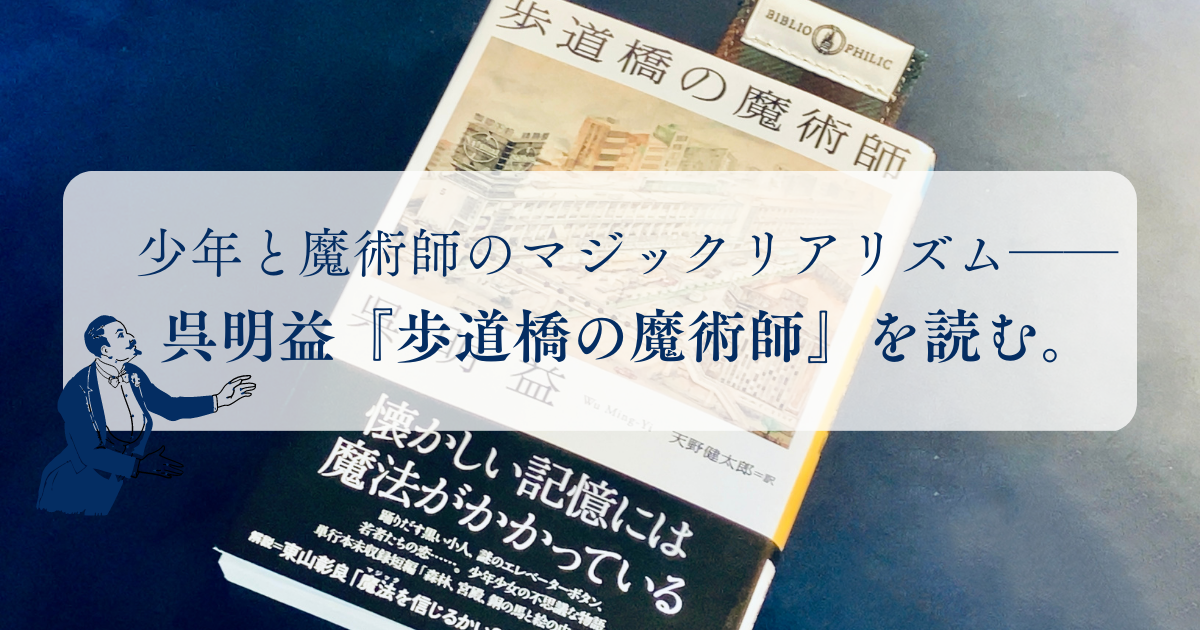カズオ・イシグロ『特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー(ノーベル文学賞受賞記念講演)』を読む。
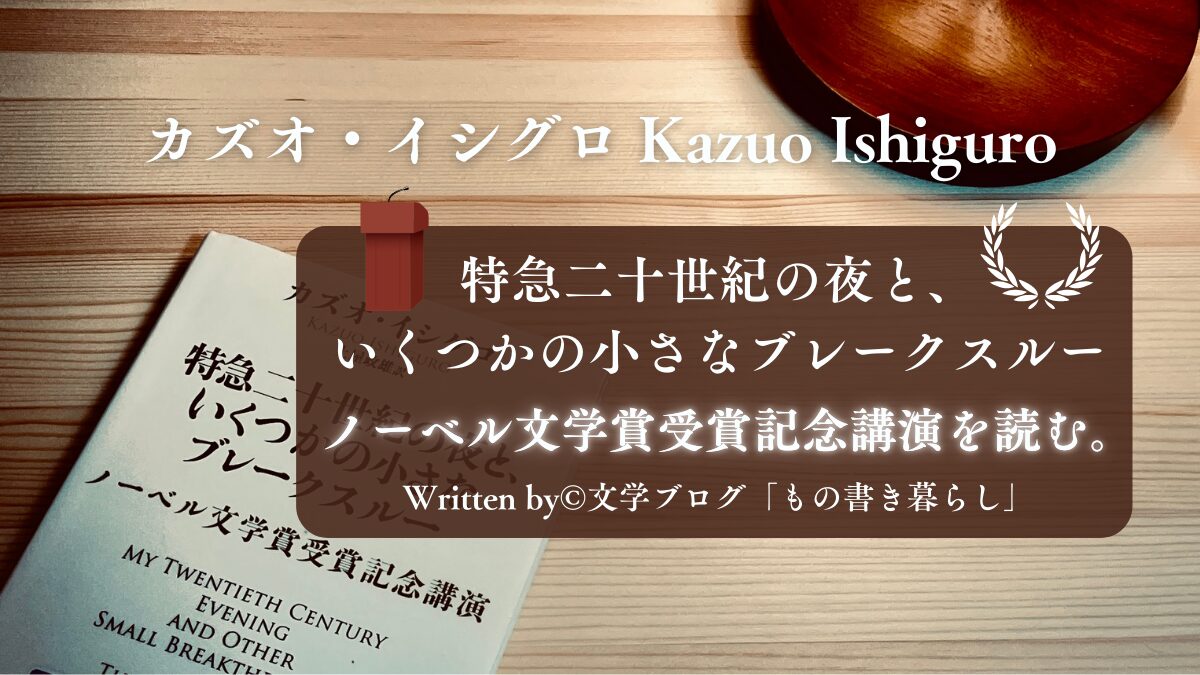
図書館で借りた、カズオ・イシグロのノーベル文学賞受賞記念講演

この間、市内の図書館に寄る機会があり、棚をいくつか見て回った。もともとは「喫茶店文学傑作選」に出てくる、北園克衛の詩集を探していた。
偶然、海外文学の棚を通りかかると、書店で買えなかったカズオ・イシグロのノーベル文学賞記念講演の本を見つけた。
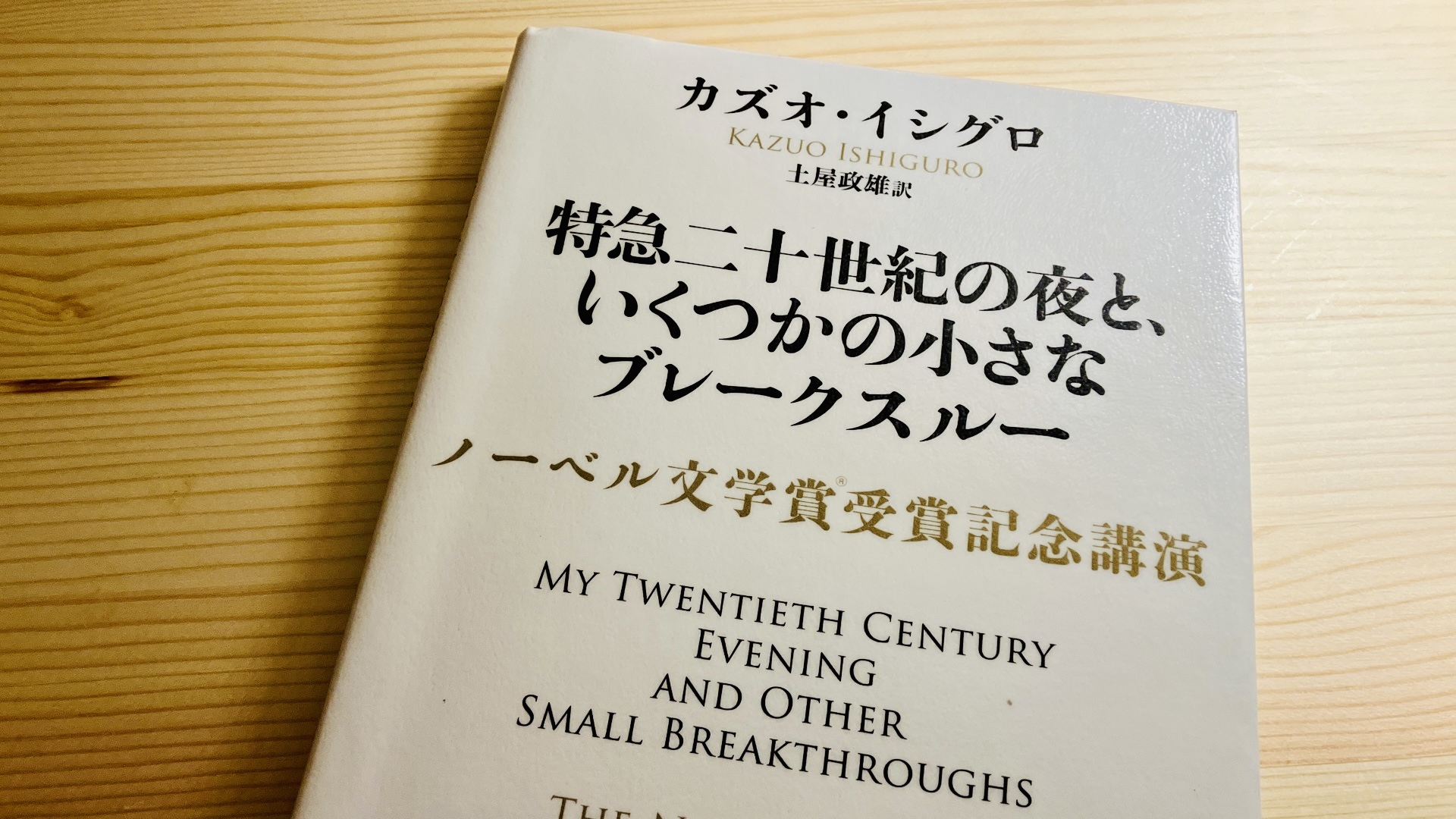
ちょうど買うか買わないか迷っていて、一度は見送った本だったのだけれど、図書館に置いてあるとは思わなかったので、つい棚から引き抜いて借りてしまった。
「ノーベル文学賞受賞記念講演」という堅めのタイトルが付いているが、カズオ・イシグロが壇上で何を喋ったのか、ちょっと興味があったので、昨晩に一読してみた。
内容をざっくり言うと、「カズオ・イシグロがどのように小説を書きはじめたか?」ということと、「これまでの作品を書くに至ったアイデアは何なのか?」というところをわりと詳しく語っていた。
今回は、カズオ・イシグロのノーベル文学賞受賞記念講演「特急二十世紀の夜といくつかの小さなブレークスルー」を読んだことがない人に向けて、簡単なダイジェストと、感想を述べてみようと思う。
カズオ・イシグロが小説を書きはじめたきっかけとは?

カズオ・イシグロは、ミュージシャンを目指していた話を知っているだろうか? 元々は作家志望ではなく、ギターをひっさげていたシンガーソングライターだったというエピソードがある。
最初のところからちょっと引用すると、
その秋、私はリュックを背負い、ギターとポータブルタイプライターをぶら下げて、ノーフォーク州バクストンに到着しました。イングランドの小さな村で、古い水車場があり、その周囲に平らな農地が広がっています。なぜそんなところに来たかと言えば、イーストアングリア大学大学院の創作科という1年間の過程に受け入れてもらえたからでした。
「特急二十世紀の夜といくつかのブレークスルー」カズオ・イシグロ 土屋政雄訳(2018)早川書房 p.7より引用
元々、若い頃は二十歳までにロックミュージシャンになりたい、という願望があり、実際にギターで弾き語りもしていたようだが、ミュージシャンの道は断念している。
カズオ・イシグロの作家としての転機になったのは、大学院の創作課程に入ったこと。
試しにGoogle Mapでノーフォーク州バクストンがどこにあるか調べてみると、イギリスの中心街ロンドンからは遠くかけ離れた北東の外れにある、どう見ても田舎としか言いようのないところに越していっている。
なぜカズオ・イシグロがそんなへんぴな所にわざわざ行ったのかというと、大学院で創作科の課程を取っていたからというのが事情らしい。
大学のあるノリッジまで出るバスは日に三本ほどしかなかったという。
そこでカズオ・イシグロは小さな家の一室を大家から間借りして暮らしていたそうだ。
実際、私の小さな部屋は、「作家の屋根裏部屋」という古典的な通念とさほど違わなかったでしょう。天井の傾斜は閉所恐怖症を誘いそうなほどでしたが、爪先立ちすれば、1つだけの窓から外が覗け、耕された畑が遠くまで広がっているのが見えました。小さなテーブルはタイプライターと卓上スタンドを置くと、ほぼいっぱいになりました。
「特急二十世紀の夜といくつかのブレークスルー」カズオ・イシグロ 土屋政雄訳(2018)早川書房 p.9-11より引用

カズオ・イシグロはこの小さな部屋で、創作をはじめたらしい。
ちなみにカズオ・イシグロはポータブルタイプライターを執筆に使用していた。
何となく「ポメラ」を使っているので、勝手に親近感を感じてしまうのは僕だけだろうか。
話が逸れたけれど、テーブルにはそのタイプライターと卓上スタンドの他には何も置かれていなかった。
カズオ・イシグロが創作課程に所属していたのは二十三〜二十四歳頃の話。
入学前は英国放送のBBCにラジオドラマの原稿を送って突き返された経験があるらしい。その落とされた原稿を、創作課程の願書に添えて提出したという。
大学院の創作課程への入学許可が降りたことが分かってから、カズオ・イシグロは短編を書きはじめたそうだ。
1つ目と2つ目の短編もうまくいかず、短編をいくつか作っていたようだけれど、その小屋に住みはじめて4週目を迎える頃に、取り憑かれたように書くアイデアに出会った。
それが、カズオ・イシグロにとっての幼い記憶とイマジネーションの中の「日本」の話だった。
1979-80年の冬とそれにつづく春、ほとんど誰とも口を利かずに書いていたと思います。例外は、クラスメートと、村の食糧品店の主人(なにしろ、この店で買う朝食用シリアルと子羊の腎臓で生き延びたようなものですから)、そして隔週末に訪ねてくるガールフレンドの(現在の妻の)ローナだけでした。とてもバランスのとれた生活とは言えませんが、とにかく4、5ヶ月もその生活をつづけ、最初の長編小説である『遠い山なみの光』の半分を書き上げました。
「特急二十世紀の夜といくつかのブレークスルー」カズオ・イシグロ著 土屋政雄訳(2018)早川書房 p.19より引用

カズオ・イシグロの生まれは1956年の11月8日。日本の長崎で生まれている。5歳(1960年)で渡英していて、海洋学者の父親の仕事の関係でイギリスへ渡った。
1979年-1980年の冬に「遠い山なみの光」の原型となる作品を書いている。生年で計算すると、23-24歳頃の話になるだろう。
バクストンの片田舎の小屋で、ほとんど誰とも口を利かずに書いていたという。
なぜ、彼にとって、幼い頃に離れた日本の小説を取り憑かれたように書いていたかというと、自分の中にある「日本の記憶」が消えてしまう前に「保存したい」衝動に駆られていたからだという。
カズオ・イシグロの一家は、1960年の渡英後も、両親はいつかカズオ・イシグロを日本に連れて戻るつもりであったらしい。
「翌年には日本に帰るかもしれない」と思いながら、結局は、11年以上も日本に戻ることは無かった。
カズオ・イシグロの手元には、日本から送られてきた小包があり、そのなかには月遅れの雑誌や漫画、教育本などが入っていた(祖父から送られてきたもの)。
つまり十代の頃に、当時の日本のサブカルチャーに触れていて、当人曰く「貪るように読んでいた」という。

しかし、実際にはカズオ・イシグロは日本に帰国することはなかったわけだから、彼の言う「私の日本」とは、5歳までの「日本」の幼い頃の断片的な記憶。
それと、祖父が送ってくれた小包のなかに入っていた「漫画や雑誌などの印刷物」から想像した、十代のカズオ・イシグロのイマジネーションのなかの「日本」である。
そして、それは現実の日本の風景とはもう一致せず、時間が経てば経つほど、カズオ・イシグロの記憶のなかからも失われていくものだから、彼はこれが自分のなかから消えてしまう前に、小説という装置を使って「保存しておきたかった」のだという。
だからこそ保存が必要でした。20代半ばに達するころの私は、明確に意識することはなくても、ある重要な事実に気づきはじめていたのだと思います。つまり、「私の」日本は、たぶん、現実に飛行機で行けるどの場所とも一致していないだろうということ。両親の話から想像でき、私自身の幼いころの記憶にもある暮らしぶりは、1960年代から70年代にかけてほとんど消え失せているだろうということ。そもそも、私の頭の中にある日本は、子供が記憶と想像と憶測から作り上げた感情的産物にすぎないのかもしれないということ……。
「特急二十世紀の夜といくつかのブレークスルー」カズオ・イシグロ著 土屋政雄訳(2018)早川書房 p.37より引用
「私の」日本は、現実に飛行機で行けるどの場所とも一致していない……。
カズオ・イシグロが取り憑かれるように書けたのはなぜ?

カズオ・イシグロにとって、最初に作ったいくつかの短編はうまく行かず、「途中で書く気が失せてしまった」と話している。
なぜ処女作の「遠い山なみの光」の原型のモチーフに関しては、取り憑かれたように書くことができたのか? という問いがある。
マリオ・バルガス=リョサの「若い小説家に宛てた手紙」という本がある。
この本のなかで、「作家がテーマを見つけるのではなく、テーマの方が作家を見つける」と書いてある箇所がある。
おそらくカズオ・イシグロが創作課程にいた最初の頃に書いたものは、入学時にクラスメイトに見せるための、半ば強制的に引っ張り出してきた、間に合わせのテーマであったと思う。
一方で、カズオ・イシグロが自分の記憶のなかにしかない「日本」の情景や、想像のなかで考えていたことのすべてを保存するために書きたいと語っていたのは、「必要に迫られて」書いているように見える。
加えて、その内容は、カズオ・イシグロ自身が語りはじめなければ「その話はなかった」ことになり、他の誰も語ることができないような内容だった。
どうすれば書きたいもの(というより本人が書くべきと感じるもの?)を見つけられるかは分からないが、「本人が語らなかったらその存在が消えてしまうもの」が作家自身のなかに見つからないかぎり、物語にするのは難しいのでは? と思ったりする。
ただ待っているだけでは見つからないような気もするので、とりあえず書く技術を身に着けるために、習作をいくつか作ってみるのはありだと思う(すべての人が最初からノーベル文学賞作家のように書けるわけではない)。
結果的に、その作家の代表作として残るようなものは、「物語らざるをえない」切迫したものが作家自身の動機に含まれているのではないか?
日本の作家でも新人賞のデビュー作などを読むと、「やむにやまれず書かれた」ような初期衝動の塊が垣間見える作品が多い。
タイトルにもなっている「ブレイクスルー」は、作家自身が書かざるを得ないと感じるものに直面し、それを書き残したときに産まれるのではないか?
それに出会うのは、いつになるかは分からない。
カズオ・イシグロのように早熟であれば二十代半ばに短編をいくつか書いて見つけてしまうものかもしれないし、あるいは十年、二十年と下積みを続け、人生も半ばをとうに過ぎた頃にようやく見つかるのかもしれない。
あるいは、一生をかけても見つからないで終わる可能性も十分にある。
でも、共通しているのは、書き続けなければそのチャンスも巡ってこないことだ。
カズオ・イシグロは二作目の「浮世の画家」や三作目の「日の名残り」、2005年に出版されブッカー賞にも選ばれた「わたしを離さないで」などのアイデアを得たきっかけについて、この講演のなかで語っている。
どの作品もやみくもに書かれてできたものではなく、カズオ・イシグロ自身に次のタイトルではこういうものを描きたい、というイメージや確信がはっきりあって、その上で文章を書いている。
一作ごとに自分の作品の書き方(こう書けばもっとよくなるはずだというアイデア)に気付いていく、という「小さなブレークスルー」の積み重ねが、カズオ・イシグロの重厚な語り口を生んでいる。
はじめのうちは「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」という方式で書いていってもかまわないかもしれないが、何のアイデアもなく、語るべきことも自分の中には見つけられないまま書いていくと、どこかで作家として「詰んで」しまうのではないか?
もうここから先は行き止まり、これ以上この書き方をしていては駄目だ。
その「詰んだ」地点からはじめてその作家の創作の地平がはじまるのではないかと思ったりした。
ものを書く人なら、多くのヒントを得られる本だと思います。
作家のことは、作家自身が話す言葉から辿っていくのもいいかもしれない。
2024/12/17 18:16
kazuma
余談 ポメラ日記、100日目に向けて連載中。
noteではもの書きの日常を綴る「ポメラ日記」を連載中です。最新話は「ポメラ日記98日目 詩人の目線はいずこ?」になります。

書店でやっていた谷川俊太郎さんの追悼特集で手に取った『二十億光年の孤独』の話。
北園克衛や中原中也、谷川さんといった詩人が見ている世界は文字通り違うものを見ているのではないか、という話をしています。
kazumaの日常周りの文学トピックはnoteで発信しております。
100日目に向けて更新中ですので、記事を読んでよかったら「スキ」や「フォロー」で応援いただけると嬉しいです。
(了)