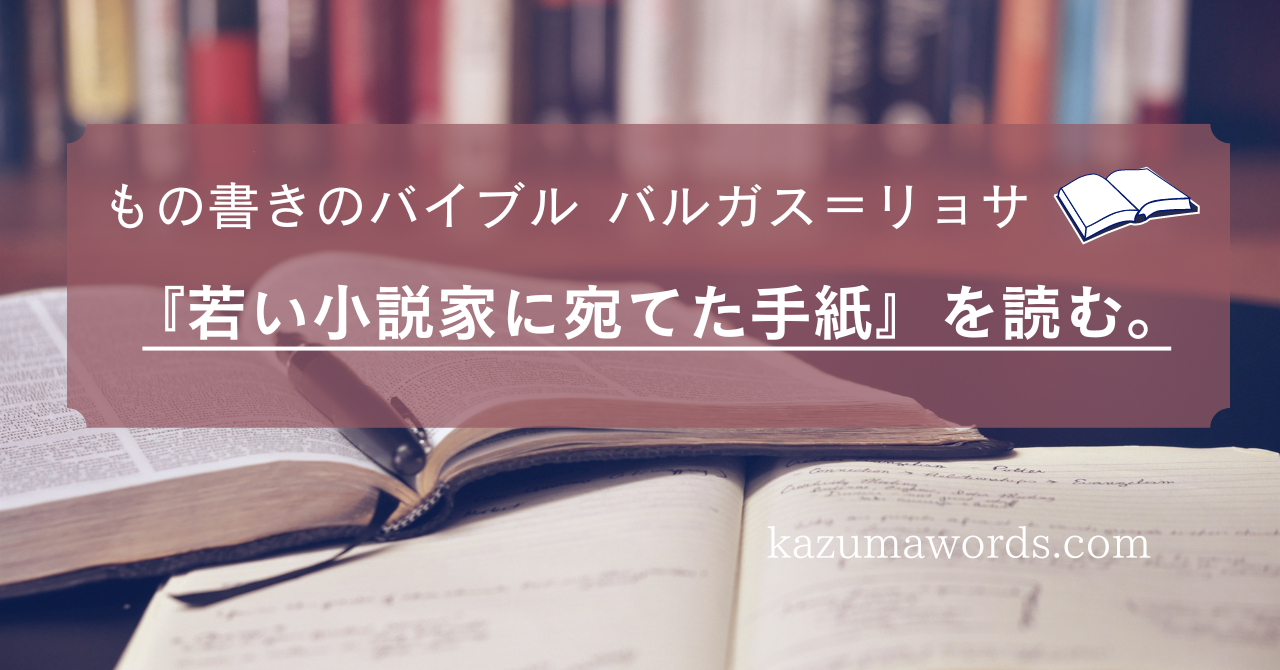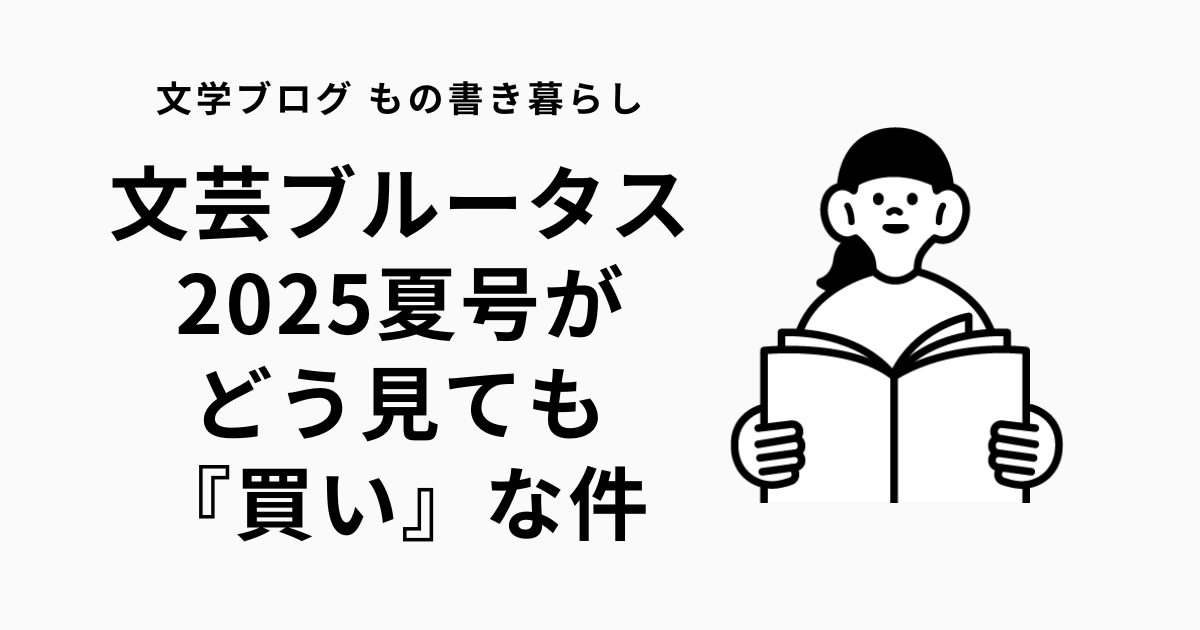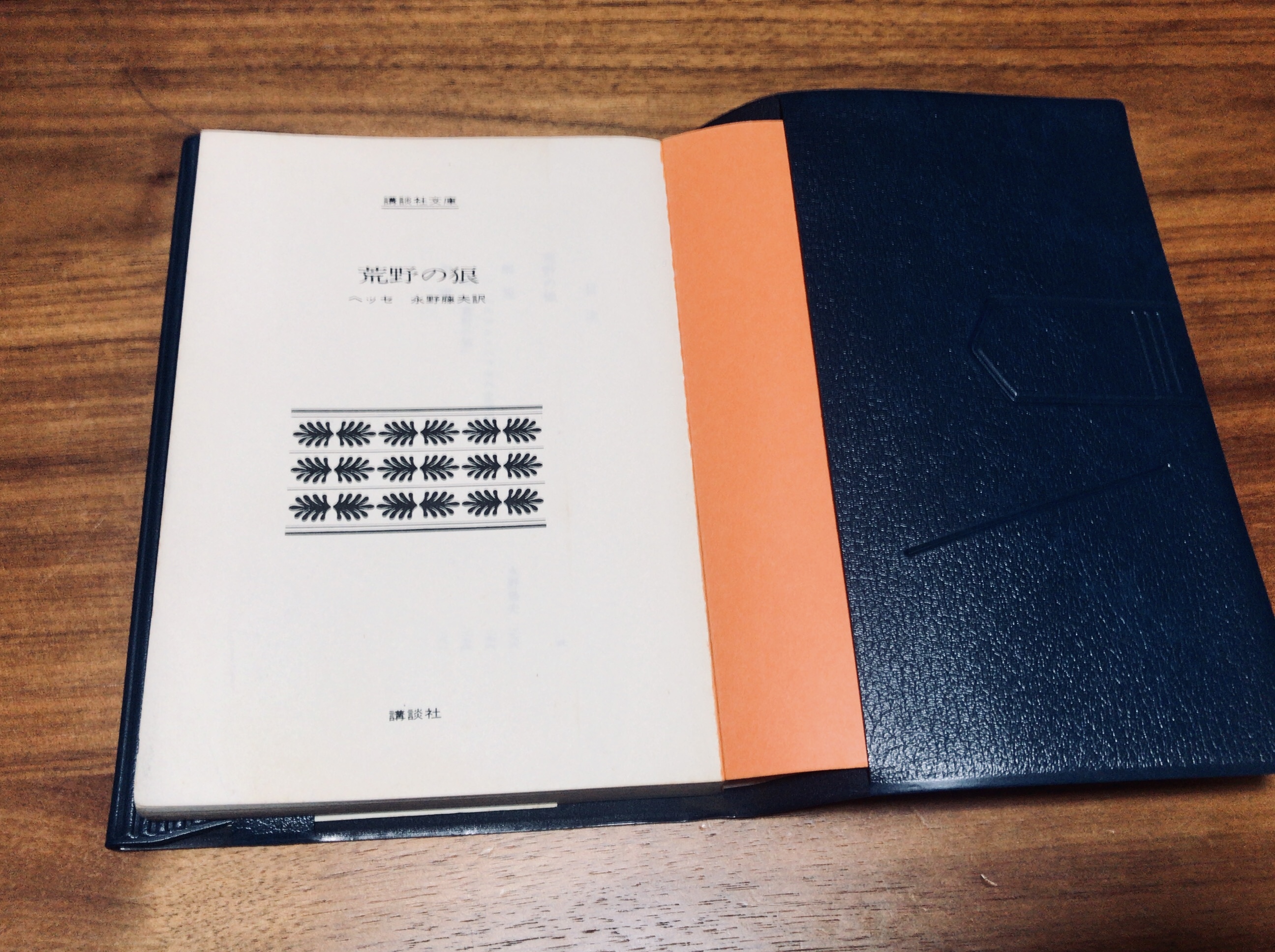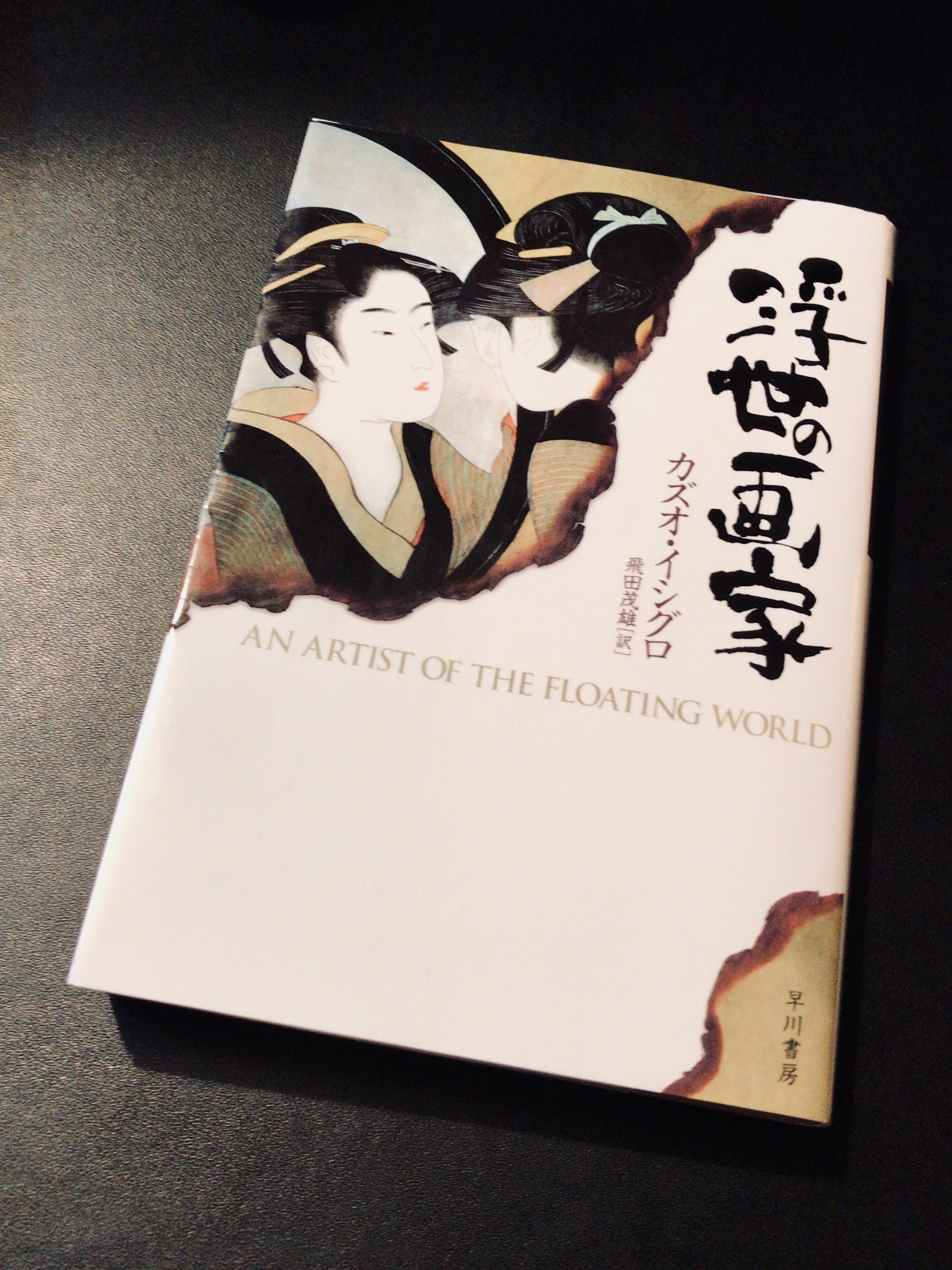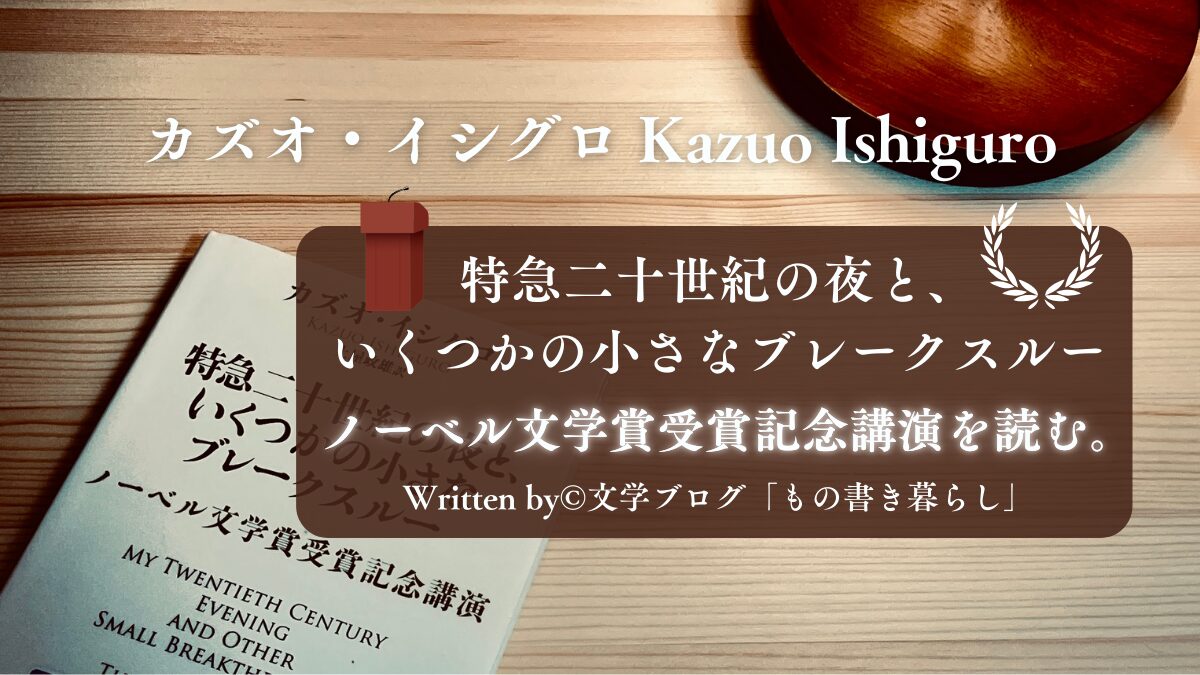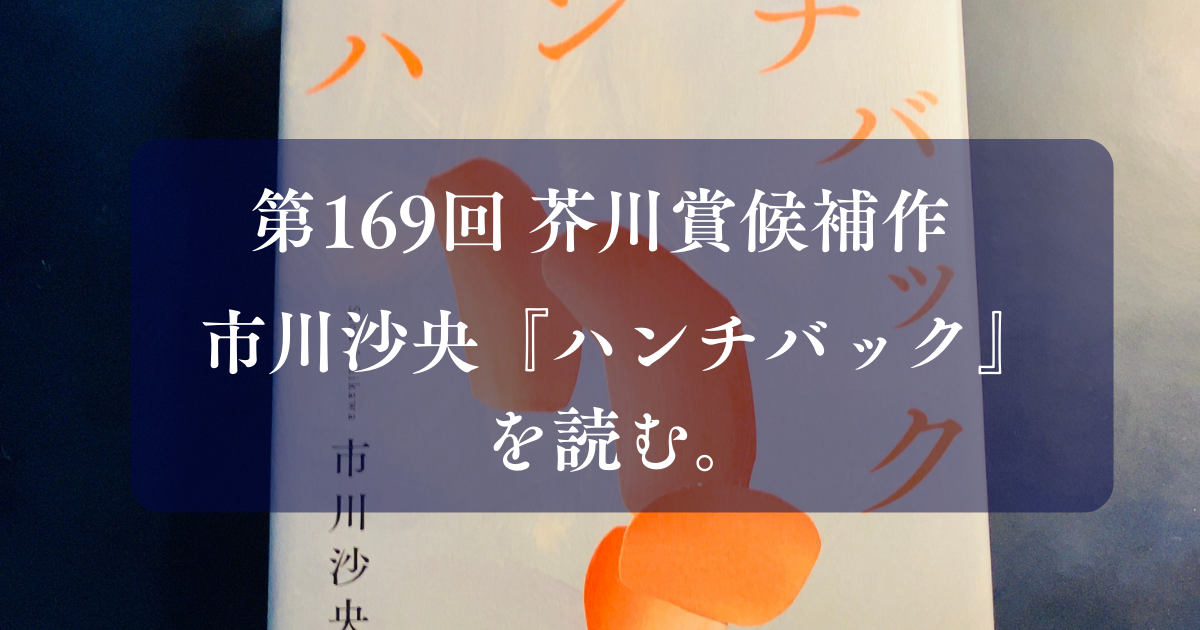「夏目漱石の『門』を読み終えて」

夏目漱石の「門」を読むことになったいきさつ
こんにちは、もの書きのkazumaです。今日の昼頃、漱石の「門」を読み終えた。簡単な感想をここに述べておこうと思う。
まずどうして『門』を読んでいたのかについて。これについては偶然だった。何ヶ月も前に友人と一緒にショッピングセンターを歩いていたことがある。そこで僕と友人は文豪ポーチのガチャガチャを見つけて、回して最初に出てきたのが漱石の『門』だった。
せっかくポーチが出てきたんだから中身がないとだめでしょう、ということになって、同じ施設内にあった書店に足を運んで『門』を手に入れた。去年の暮れは忙しかったのでそのままうっちゃっておいたんだけれども、興味がないわけではなかったので、ずっと鞄に入れて持ち運んでいた。
「門」を読んだのは日本文学を通過しておく必要性を感じたから
僕は学生の頃、近現代の日本文学をあまり通過していない事情がある。当時は単純に海外文学がやっていることの方が面白そうに見えたからだ。でも海外文学というのは、元はみんな外国の言葉で書かれているものだ。だから僕が読んできたものはほとんど翻訳もので埋め尽くされてしまっていた。日本の文学がどんな系譜で成り立ってきたものなのかということについても疎かった。
転機になったのは、詩が書けなくなった友人から梶井基次郎の『檸檬』を勧められたことだった。『檸檬』の文章は、その話の内容もさることながら、並べ立てられていく言葉の流れそのものが美しかった。日本語っていうのは、こんなに綺麗に、鮮やかに書くことができるものなのかと思って、それで僕はようやく日本文学を通過しておく必要性みたいなものを感じた。
そんなときに文豪ポーチの縁があって、角川のシリーズで近代日本の古典文学を読み直そうと思った。それではじめに漱石の『門』に取り掛かった。
『門』っていうのは実は三部作で、本来は『三四郎』、『それから』、最後を締めくくる物語が『門』だ。
『三四郎』については昔、手を出したのだけど、なぜか途中で読めなくなって止めてしまった記憶がある。したがって『それから』にも手が伸びなかった。
つまり僕は何の予備知識もないままに最終巻にあたる『門』から読むことになり、けっこう事情が分からないままに読み進めることになった。結果的に『門』はそれ単体で成立しうる作品だと読み終えたときに分かった。
夏目漱石「門」についての解説
話の流れは、暮らしに困っている二人の夫婦の会話からはじまる。
宗助は、手紙を書こうとして「近江」の「おう」の字が分からないと言って妻であるお米(よね)に尋ねている。
あまりに会話が噛み合わないので、宗介は神経衰弱じゃないかしらと妻に言われてしまうが、その原因らしきものがどうもまったく描かれないでいる。
弟の小六は宗助の年の離れた弟なのだが、育てていた叔父が亡くなったために、学資に困り、いまでは宗助を頼るよりほかに道はなくなっていた。
兄のもとへ訪れては、元々いた佐伯の家にどうにかお金の都合を付けて貰えるよう、手紙を書いてくれないかと言われるのだが、宗助は休日に散歩に出かけていって取り合わない。なぜ宗助が佐伯の家に行くのは気が進まないのかは、のちに分かる。
前半部は取りとめのない夫婦の暮らしの掛け合いが続く。弟の小六の金の工面をどうするか、亡くなった叔父に預けていたはずの家財道具はどうなった、新しい外套をこさえたい(月賦で作れば?)、など一見すると現実的すぎてつまらない話だが、実生活上では決して逃れることのできないエピソードが次から次へと放り込まれる。
漱石はどうして宗介とお米の夫婦生活を延々と描き続けたのか?
読んでいる間に僕は段々と不安になっていった。漱石ほどものが書ける人間がどうしてこれほどまでに執拗に宗助とお米の生活を描くのか、その目的がまったく見えてこなかったからである。
こんな取りとめのない話を最後まで続けるのが『門』なのか? こんな風に話を転がし続ける漱石はいったいどうやってこの物語を畳むつもりでいるのか?
そういう疑問が僕のなかで浮かび上がって、不安は徐々に「この話の畳み方を知りたい」という、不純な動機に変わっていった。
延々と夫婦の貧しい日常の描写が続くかと思われた矢先、宗助とお米が出会うことになった過去が語られ、その部分を読んだ瞬間に、なぜここまでつまらないような日常生活が描かれ続けたのかが氷解した。
宗介はすべてを投げうってお米との暮らしを選んだ
宗助とお米はかつての友人である安井を裏切って夫妻になったのだということが物語の後半部で明かされる。
宗助と安井は学生時代の友人同士だった。京都の街並みを歩いて、まだこの街に不案内であった宗助に一通り手ほどきをして回る。
しかし夏を過ぎ、郷里に帰って別れていたうちに、安井はいつの間にか京都に家を借りて暮らすようになっていて、そこになぜか一緒にいたのがお米だった。
宗助は少し見ない内に安井の顔に変化が訪れているのを目の当たりにした。安井はお米のことを妹だといって紹介するが、どうにもそのようには思われず、安井は適当な嘘を言っていて、宗助はお米のことが気に掛かりはじめている。
その微妙な三角関係のなかで、幸福であった学生時代が瓦解する。詳細は省かれているが、何が起こったかは想像に難くない。
宗助は学校を中途で退学し、安井からお米を奪って、二人は世間に背を向けて暮らすようになった。その果ての生活が描かれていたのが『門』の前半部であったのだと思い至った。
宗助はお米との生活のためにすべてを投げ捨てた人物だった。
暴露の日がまともに彼らの眉間を射た時、彼らはすでに徳義的に痙攣の苦痛を乗り切っていた。彼らは蒼白い額を素直に前に出して、そこに炎に似た烙印を受けた。そうして無形の鎖でつながれたまま、手を携えてどこまでも、いっしょに歩調をともにしなければならないことを見いだした。彼らは親を捨てた。親類を捨てた。友だちを捨てた。大きく言えば一般の社会を捨てた。もしくはそれらから捨てられた。学校からはむろん捨てられた。ただ表向きだけはこちらから退学したことになって、形式のうえに人間らしいあとをとどめた。
これが宗助とお米の過去であった。出典:『門』夏目漱石著 角川文庫 昭和二十六年刊(令和三年改版)p.169より引用
そういえば、これが文豪ポーチの内側に抜粋で書かれていた文章だった。これが気に掛かって僕はこの小説に惹かれたのだ。
仕組みが分かっても開くことのできない「門」
宗助は自らの不義の罪と、弟の小六の経済的問題にぶちあたって、もうにっちもさっちもいかなくなっていた。
そこへ、近所で懇意になっていた坂井と話しているときに、安井らしき人物のことが話題に上りはじめた。いずれ近いうちに、二人の人生から消えていたはずの安井が、坂井の邸宅へやってくると聞く。
宗助は、このどん詰まりからの救済を求めて、職場の同僚から聞いた禅の寺の門を叩くことになる。
このタイトルにもなっている「門」は、ここではじめて現れる。
宗助は約十日間の間、この鎌倉にある寺に籠もって、禅の公案に取り組むことで、この窮地を何とか回復しようとするのだが、どうにも後に置いてきた俗世の悩みを断ち切れず、悟るような境地に達することもなく、失意の中で鎌倉を後にする。
自分のなした罪とがが、身からは決して抜け得ないことを知るのである。
そうして禅の寺の門を眺め返す。自分はこの行き詰まった生活から別の道へと通じる門を開けて貰いに来た。しかしこの門は叩いても、内側から開けてもらえない。入りたければ自分のちからで開けて入れという。
門には閂(かんぬき)が掛かっていて、どうやってもこじ開けられない。門を開く方法をあれやこれやと頭の中でこしらえてみることはできる。
しかしこの門は開けない。仕組みが分かっていても開かない門が宗助の前にある。
自分はただこの門の下に佇んで時間だけが過ぎていくよりしようのないことを彼はそこで悟るのだった。
まとめ 「門」は人間にはどうしようもない運命について綴った小説
「門」は人間のどうしようもない運命について書いた小説だと僕は思う。僕たちは理屈で何でもわかったような気になる。どんな道でも開けているように勘違いをする。
でも実際には人間はほとんどの場合において無力で、閉ざされた門の下で日が暮れていくのを待っている。
もちろん、そんな門について考えないで、さっさと素通りしていく人もいる。
しかし宗助の人生はそういう類いのものではなかった。自分を拒み続け、開くことのできない門の前に連れ出された因果な人生だった。
彼は自分はどこにも行けない人間だと分かっている。いずれ寿命の方が先に尽きてしまうであろうことを分かっている。それらがみんな分かった上で、お米との細々とした暮らしを何とか保とうとしていたのである。
だからあのつまらないように見えた暮らしが、一転して宗助とお米が命がけで守ろうとしたものだと分かるようにできている。漱石のその手並みに、どうやら僕は脱帽するほかないようだ。
2023/01/29 18:49
kazuma