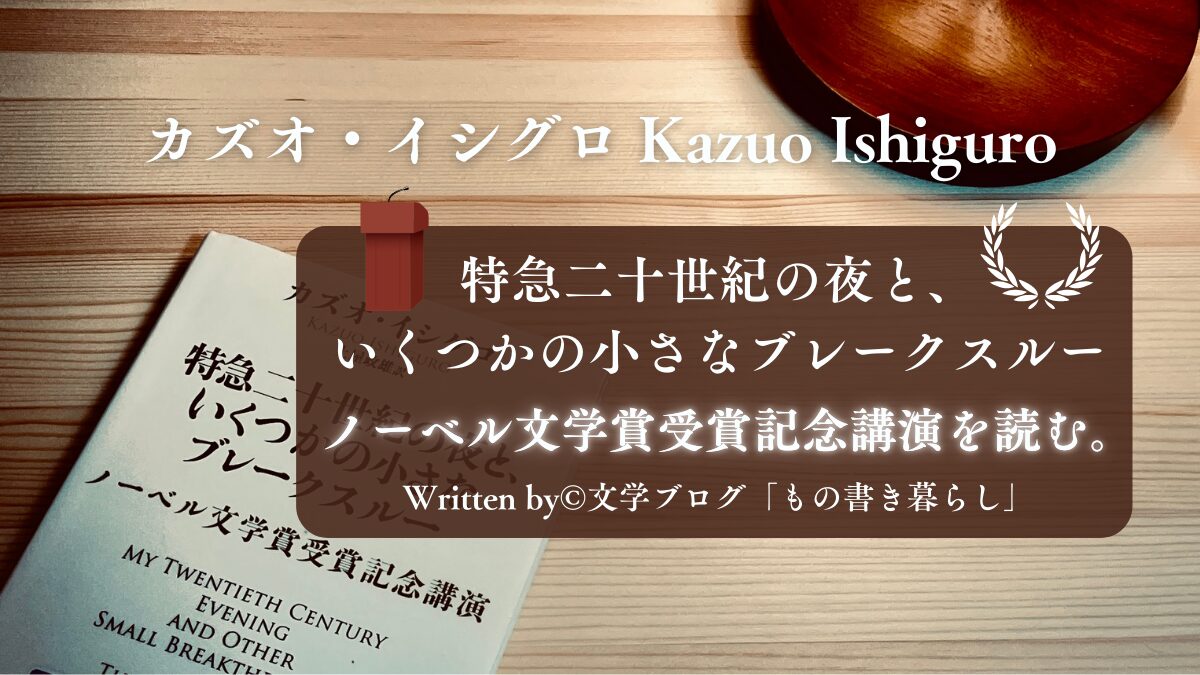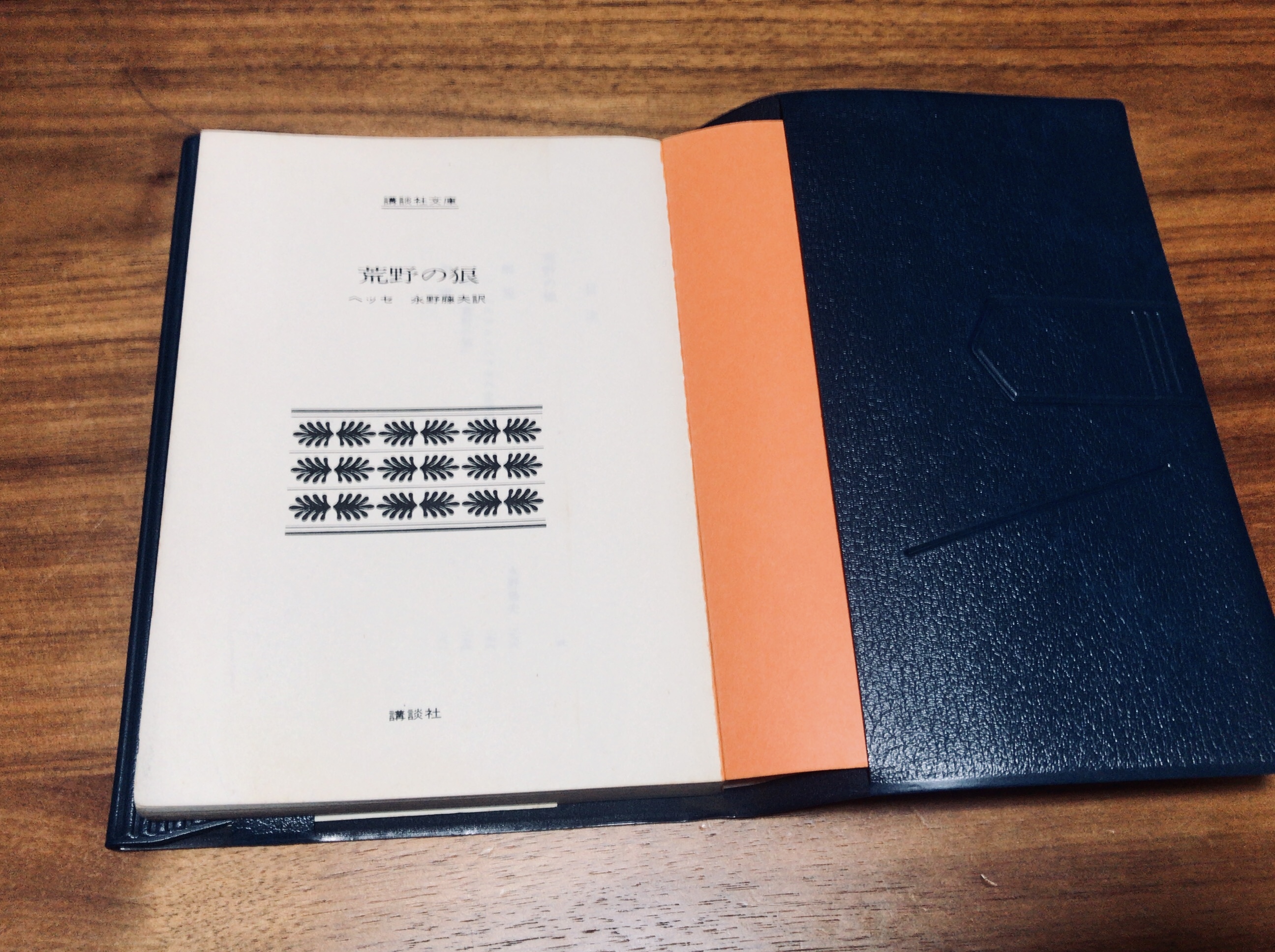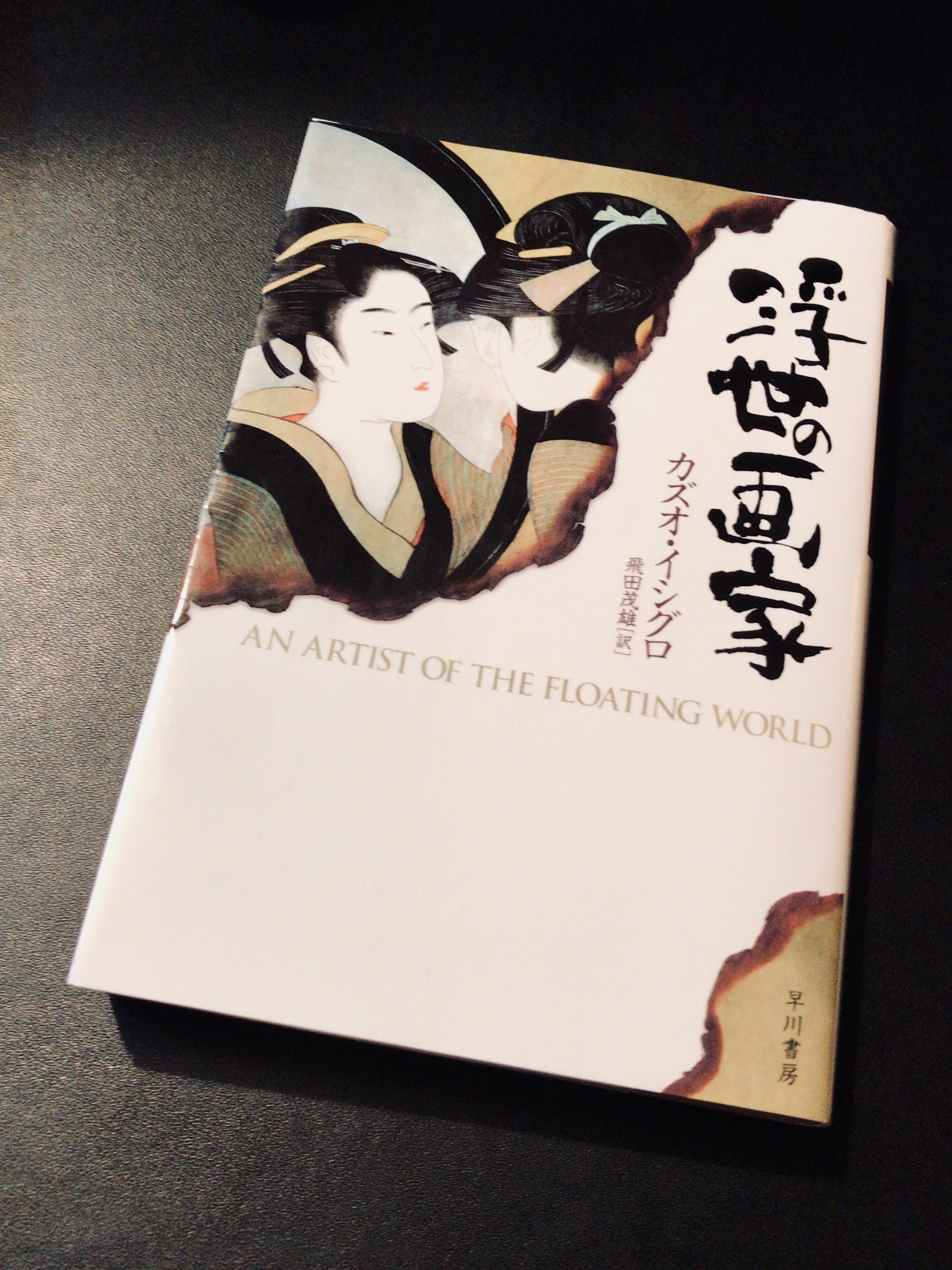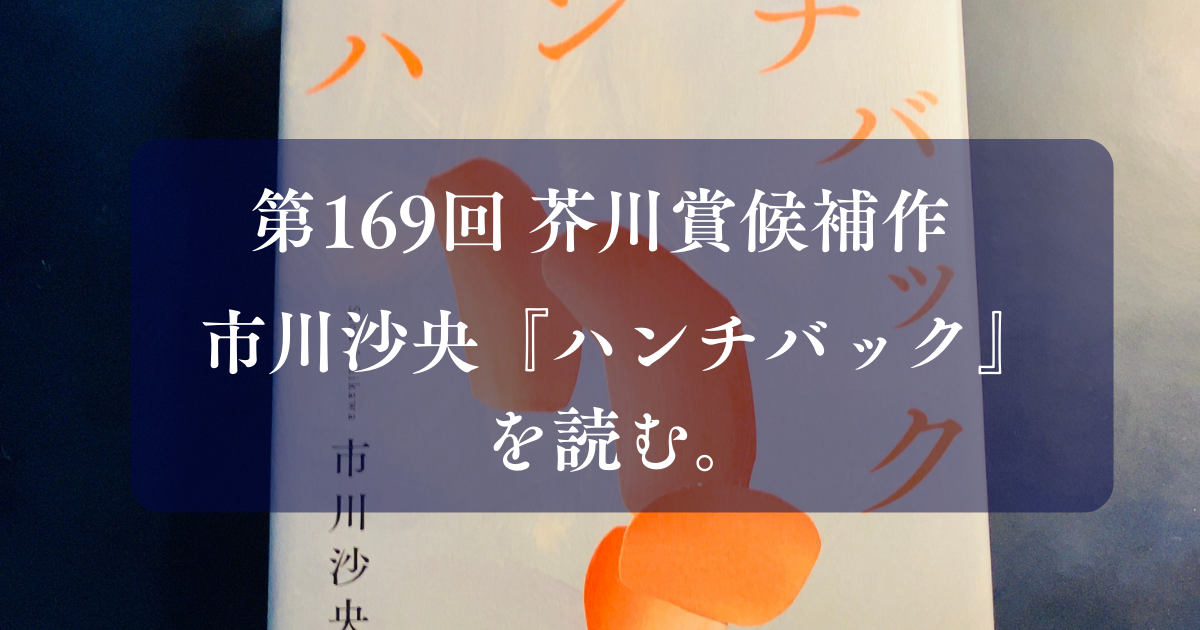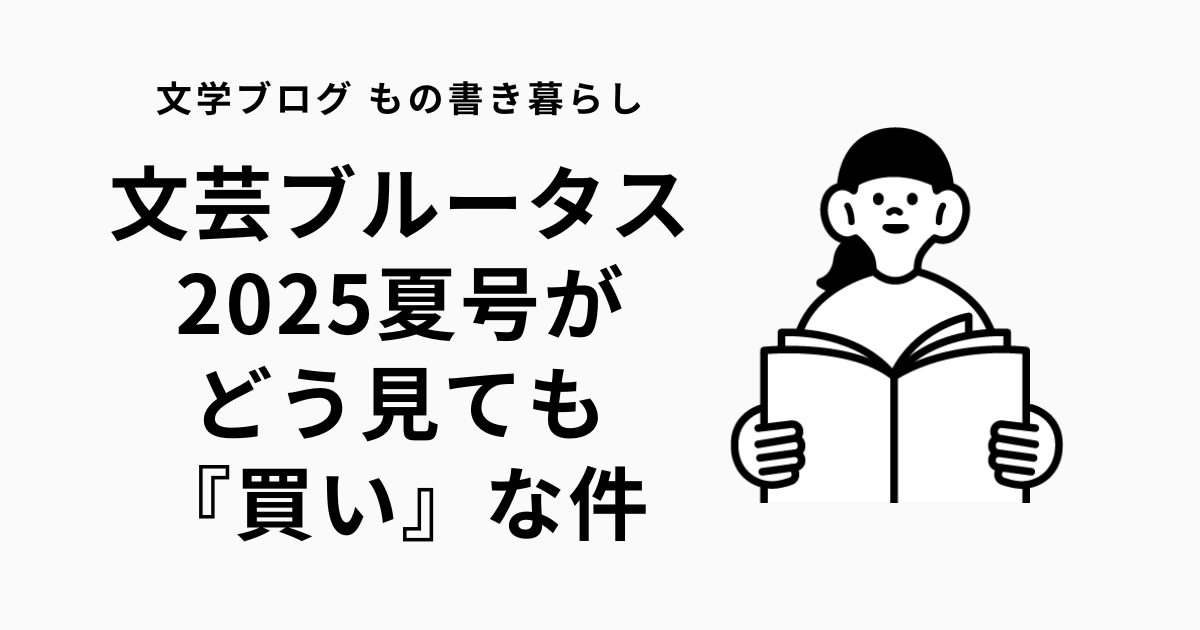もの書きが読み解く、トルーマン・カポーティ『無頭の鷹』

1946年11月号のハーパーズ・バザーに掲載された『無頭の鷹』

トルーマン・カポーティの『無頭の鷹』という短編をご存知でしょうか。
原題は『The Headless Hawk』で、1946年11月号のハーパーズ・バザー誌に掲載されたこの短編は、読み手に不思議な感覚を抱かせる、ミステリアスな小説です。
1946年というと、カポーティが弱冠22才前後の頃(トルーマン・カポーティの生まれは1924年9月30日)にあたります。
既に前年(1945年)には『ミリアム』という傑作短編を書いていて、デビュー当初から才気に溢れた作品を世に送り出していました。
『無頭の鷹』は日本では、川本三郎さんが訳した「夜の樹(新潮社)」というカポーティの短編集や、作家の村上春樹さんが訳した「誕生日の子どもたち(文藝春秋)」に収録されています。
どちらの訳も優れているのですが、今回は村上春樹さんが訳したバージョンを底本に、カポーティの「無頭の鷹」を読み解いていこうと思います。
『無頭の鷹』を描いているカポーティの「不穏」な目
カポーティの文章は作品によって七変化するのだけど、とくに「無頭の鷹」に関しては、このひとの目はあまり穏やかではない。不穏、と呼ぶのがふさわしいと思う。
主人公はヴィンセントという青年で、冒頭は彼がニューヨークの三番街に向けて歩きはじめるところからはじまる。
このヴィンセントは、街中を歩くときには海の底を歩くような心地がするといい、周囲の人間の顔も、仮面を付けて波間に揺れているように見えると話す。
冒頭の1ページ目から、このヴィンセントというのは既に周囲との隔たりを強く感じていて、彼が唯一気に留めているのは、緑色の透明なレインコートを着たある少女のことだけだとわかる。
彼は路地を歩んでいても北に進んでいるのか、南に進んでいるのか分からなくなっている。彼はいま「自分がどこにいるのか」もわかっていない青年なのだ。
5セント玉を側溝に落としても、まるで気づいておらず、落としたことを新聞の売り子に言われて、悲しんでいる「ふり」をする。
新聞の見出しを読みながら、遅れて「でもこいつは、いったい何を言おうとしてるんだ?」と考える。
ひとをひととも思わずに歩いているので、買い物袋を抱えた女にぶつかって、イタリア語で罵声を浴びせられる。
ようやく彼は街中で探していたある少女に出会うが、煙草に火をつけてもらったあとで、煙草なんて吸いたくなかったんだといって、指で弾いて捨ててしまう。
この矛盾を抱えたアンバランスな心地というのが、作品を通して流れている「不穏」な目の正体だと思う。
ちなみに、少女は三番街と五十七丁目の交差点の「ダウンタウン」側に立っていた。これはヴィンセントが位置をはっきり認識している唯一の記憶だ。
カポーティがわざわざこのように描いているのは意味があることなので、ちょっと憶えておいてほしい。
暗やみから目を逸らし続けた青年・ヴィンセント

ヴィンセントというのは、一見するとまともな生活を送っている人間のように見える。
三十代の半ばで、画廊に勤め、小綺麗なアパートに住んでいる。部屋を飾り立てるほどには裕福で、生活にはまるで不自由していない。容姿は整っていて、過去に付き合った人物も少なくない。
まさに都会的な生活を謳歌している青年だ。
にもかかわらず、彼のその「まとも」さというのは、かなりアンバランスな均衡の上に成り立っている。
天秤の片方にはっきりとした重みが乗ってしまえば、もはや自分を保っていることができないくらいに。
「無頭の鷹」は都会的な世界に生きていたひとりの青年が、これまで目を逸らし続けてきた決定的な欠落を、ある少女が描いた絵によって暴かれてしまう、という物語だ。
ヴィンセントは、実のところ過去の記憶を片っ端から葬り続けながら生きている人間で、落ちるとわかっている穴に向かって自ら落ちていくような青年なのだ。
ビリヤードでいえば、もうポケットに落ちる寸前のところにある球のようなもので、それがDJという奇妙な少女に出会ってしまったことで、自らの人生のむなしさや、これまで目にすることを恐れていた、「不穏」な感覚に気が付いてしまう。
もうポケットに落とされるまえから、落ちることを恐れ続けている。そして、ほんとうに穴の中に落ちてしまった──ヴィンセントはそういう青年のように僕には見える。
ヴィンセントの矛盾と孤独を暴いた少女、DJ

ある日、ヴィンセントの勤め先の「ガーランド画廊」にひとりの少女が現れる。
この少女こそ、緑色のレインコートを着た少女であり、「無頭の鷹」の絵を描いた張本人のDJだ。
彼女は自分が描いた絵を買い取ってくれという。
ヴィンセントははじめ相手にするつもりはなかったが、フリーク(変わり者)に惹かれやすいヴィンセントは、見るだけなら、といってDJに絵の包みを開けさせる。
そこには首から上を切断された女性(足元に頭部が転がっていて、その髪の毛を毛糸玉のようにして猫が遊んでいる)と、頭のない「無頭の鷹」の絵が描かれていた。
ヴィンセントはその絵を見た途端、自分のためにこの絵を手に入れたくなって、30ドルの小切手をDJに支払おうとする。
名前と住所を尋ねると、「DJ」「YWCA(キリスト教系列の宿舎・ユースホステル)」とだけ書き残して去っていってしまう。
DJの描いた絵をアパートの部屋に飾ったヴィンセントは、絵の中の「無頭の鷹」に向かってこう語りかける。
絵は彼の部屋の暖炉の上に掛けられた。眠れぬ夜には彼はグラスにウィスキーを注ぎ、無頭の鷹を相手に話をした。自分の人生のあれこれについて語った。俺は詩を書いたことのない詩人だ、と彼は言った。絵を描いたことのない画家であり、ただの一度も(嘘偽りなく)恋に身を委ねたことのない恋人だ。要するに方向というものを持たないまったくの首なし人間なのさ。
「誕生日の子どもたち(「無頭の鷹」より)」トルーマン・カポーティ著 村上春樹訳 文藝春秋(2009)p.176より引用
「双頭の鷲」のシンボルの意味は支配者が二人いること

「無頭の鷹(たか)」にはっきりと対応しているかは分からないが、海外には「双頭の鷲(わし)」という表現があって、これは支配者が二人いることを表すシンボルマークとして使われている。
ヴィンセントにはどこか分裂的な気質があって、「何かを行おうとする→行なってから望んでいなかったことに気がつく」という行動パターンをずっと繰り返している。
「煙草を吸う」→「煙草は吸いたくなかった」、「新聞の見出しを読む」→「こいつは何を言っているんだ?」、そして最後に来るのは「DJに会う」→「DJには会いたくなかった」。
ヴィンセントは二律背反の気質をつねに持ち続けている。片方が進んでそのことをしながら、同時にもう片方の彼はまったくそれを望んでいないのだ。
その傾向にとどめを刺したのが、DJとの出会いだった。「双頭の鷲」を「無頭の鷹」にした張本人、といってもいいかもしれない。
誰のことも愛さなかったヴィンセントの本音

ヴィンセントはおかしなところを持った人物をなぜか愛してしまうという。
しかし本人は気がついていないが、彼は自分に似たものを相手のなかに見つけるたびに関係を持とうとしているのだ。
ヴィンセントがDJとの会話のなかで、過去に付き合った人物たちのことを思い返すシーンがある。
いとこのルシールは一日中、花の刺繍をしていて、スカーフにヴィンセントの名を縫い付けている。ゴードンはピストル自殺を遂げ、コニーは耳が聞こえないのに、ヴィンセントの靴音を聞こうとしている。
ヴィンセントが精神的に問題を抱えている人物たちを愛してきたことは明白だ。しかし、ヴィンセントは彼らに近づきすぎることで、彼らのようになることを恐れた。
だから付き合っては、切り捨てることを繰り返している。愛したひとはひとりしかいなかった、そしてその彼女も死んだ、とDJに嘘をつく。実際のところ、彼は誰のことも愛していない。自分自身でさえも。
正体不明の人物「デストロネリ」は、DJの病が生んだ妄想の産物

作中でDJは「デストロネリ」という正体不明の人物について、ヴィンセントに話しつづける。
DJは、「デストロネリ」なる人物を、誰もが知っているかのように話し、「彼はあなたに似てるし、私に似てるし、たいがいの人に似てるわ」という。
DJはこの「デストロネリ」を危険人物とみなし、この人物の影に怯えている。
「ミス・ホール」を殺した、「あいつ」がいるから本名は教えられない、絵画クラスのガムという年配の男性に化けている、フィラデルフィアでも会ったことがある、イタリア語でしゃべって体じゅうに刺青をしていた……。
ここまで書けば、DJが憎んでいる「デストロネリ」なる人物が、彼女の妄想の産物であることはほとんど疑いようがない。
〈ときどきあいつは人間ではなくなってしまうのよ〉と彼女は言った。このベッドの上で体を丸め、夜が明ける前のわずかな時間に、彼女はひと息にそれを語ったのだ。〈あいつはときどきまったくべつのものになるの。鷹や子どもや蝶々なんかにね〉。そしてこう言った。〈私が連れていかれた場所には何百人ものおばあさんや若い男たちがいたわ。若い男の一人は自分のことを海賊だって言ってた。一人のおばあさんは──もう九十に近い人なんだけど──私に自分のお腹をよく触らせて「どう?」って訊くのよ。「すごく元気良く蹴っているでしょう?」ってね。このおばあさんも絵画クラスに入っていて、彼女の描くものっていうとまるで出鱈目な柄のキルトみたいなの。
「誕生日の子どもたち(「無頭の鷹」より)」トルーマン・カポーティ著 村上春樹訳 文藝春秋(2009)p.207-208より引用
この文章っていうのは、読む人が読めば、DJが何について語っているのかわかるようにできている。
DJは、はっきりとした診断名が付くほど、精神的に重い病を持っていて、 彼女が連れて行かれたのは、精神的な病を持つ患者を集めた病棟や福祉施設だった可能性が高い。
自分のことを海賊だと信じている若い男と、子どもを持てるはずがない九十歳のおばあさんの奇妙な妄想がそれを裏付けている。
「出鱈目な柄のキルトみたい」とは、要するにサイケデリックな模様のことだ。
DJが「無頭の鷹」を描いた「絵画クラス」というのはそこで開かれていた。おそらく芸術療法のような治療プログラムだったのだろう。

ヴィンセントは、「無頭の鷹」──すなわち、自身が最も恐れ続けている「自我を失い、コントロールできなくなること」を体現しているDJという存在に、惹かれつつも遠ざけようとする。
ヴィンセントとDJはいわば、二つの境界の間で分かれている合わせ鏡のようなもので、ヴィンセントは現実の側に立ち、DJは空想の側に立っている。
ここで、アップタウンとダウンタウンの比喩が思い出される。彼女はいつも交差点で影になる側に立っていた。
そんな合わせ鏡のような存在をいつまでも眺めていれば、自我が崩壊するのは時間の問題だ。影はどこまで行っても底が見えない。
ヴィンセントは、DJの姿を通して、自身にもある狂気の兆候を見てしまうことを恐れている。
妄想の怪物を殺すためにヴィンセントが行った「封印」の儀式

ヴィンセントは、DJが「デストロネリ」の妄想に執着し続けるのを見て、はっきりと彼女に向かって「頭がおかしいのか?」と告げてしまう。
愛そうとしても、どうしても彼女を愛することができない。このままではヴィンセント自身でさえ「おかしく」なってしまいそうだから。
ヴィンセントは、彼女の幻を象徴するかのような「蝶々」の羽根を切ろうとして、鋏で「無頭の鷹」の心臓の部分を引き裂いてしまう。
そして彼女のスーツケースのなかに、その絵ごと閉じ込めてしまう。ここでやっているのは「封印」の儀式だ。
昔、流行していた伊坂幸太郎の作品に「アヒルと鴨のコインロッカー」があるが、あのラストをどうも思い出す。
映画版では、椎名が「神様を閉じ込めるんだ」といって、ボブ・ディランの曲が流れるラジカセを駅前のコインロッカーのなかに入れてしまう。
ヴィンセントは彼女の画をスーツケースのなかに閉じ込めて泣いている。
DJは、アパートの住人であるクーパーを「デストロネリ」だと錯乱し、鋏を持ったまま、その忌まわしき名前を叫んでいた。
クーパーとデストロネリを繋ぎ合わせるのは、単にイタリア人風の名前という共通点ぐらいしかない。そこには異常な論理の飛躍がある。
ヴィンセントとDJは絵によってしか分かり合えない。しかし、彼はそれを鋏で割いた。
暗やみを語るにはあまりに眩しすぎる言葉で

DJはヴィンセントのもとを去ったが、最後の場面で再会するシーンが描かれる。
雨が降りはじめ、雷鳴が轟(とどろ)くが、路上を歩く人々のなかで、彼と彼女だけが空を見上げずに歩いている。空は砕けた鏡のようになり、雨が粉みじんになったガラスのカーテンのように降り注ぐ。
これを読んだときの感覚を何といえばいいのか分からない。狂っていながらも、美しいと感じたのは確かだ。
カポーティは作品のなかでは、運命論の側に立つように振る舞う。ここに描かれているのは、人間の手にはどうにもならなかった哀しみだ。
DJが「デストロネリ」を憎むのを、誰に止めることができるだろう? ヴィンセントが「無頭の鷹」の心臓を割いてしまうのも無理からぬことだ。彼らは出会うべくして出会って、別れるべくして別れる。
カポーティは暗やみを見つめ続けずにはいられない人間の姿を描いている。その暗さを語るにはあまりに眩しすぎる言葉で。
余談:村上さんが新訳したカポーティの『遠い声 遠い部屋』が発売されましたね。ちょっと気になっております。
(了)