『バナナフィッシュにうってつけの日』の謎を追え!

何回読んでも分からなかった小説がある。僕にとってそれはJ・D・サリンジャーが書いた「バナナフィッシュにうってつけの日」という短編小説だ。
サリンジャーは1919年1月1日生まれの米国の作家だ。普段、本は読まないというひとでも名前ぐらいは聞いたことがあるかもしれない。
「ライ麦畑でつかまえて」を書いたひと、と言えばピンとくる人も少なくないだろう。
サリンジャーの主要な作品はどれも難解といわれる。
読み終えたときに印象的な人物はいくつも浮かび上がるのに、その人物の行動の意図が理解できない、ということによく出くわす。
サリンジャーが物語に登場させた人物のうち、最も理解が及ばない人物をひとり挙げよ、といわれたら、多くのサリンジャーファンは「シーモア・グラス」だと答えるだろう。
「シーモア・グラス」というのは、サリンジャーの連作短編に登場するグラス家の長男である。この人物の初出は、短編集「ナイン・ストーリーズ」に収められている「バナナフィッシュにうってつけの日」という短編だ。
「バナナフィッシュにうってつけの日」は、1948年1月に「ニューヨーカー」誌に掲載された。
サリンジャーが「バナナフィッシュ」の原稿をニューヨーカー誌に送ったのは1947年1月のことで、編集者のウィリアム・マックスウェルは、サリンジャーのエージェント宛てにこのような手紙を送ったという。
我われはJ・D・サリンジャーの「バナナフィッシュ」を部分的にはとても気に入っていますが、なにかそこに物語が、あるいはポイントが見つからないという感じがします。サリンジャー氏が街におられるなら、当社で私とニューヨーカー誌流の物語について、お話でもしていただければと思います。
「サリンジャー 生涯91年の真実」ケネス・スラウェンスキー著 田中啓史訳 晶文社(2013)
サリンジャーの『バナナフィッシュ』をはじめて読んだときに思ったこと

僕がサリンジャーの『バナナフィッシュにうってつけの日』を初めて読んだとき、一番に思い浮かんだ疑問は、「この物語に冒頭のパートは必要なのか?」。
もうひとつの疑問は「なぜシーモアは拳銃で自殺しなくてはならないのか?」ということだった。
バナナフィッシュはパートで言うと二部に分かれていて、前半部はシーモア・グラスの妻であるミュリエルとその実母が、ホテルの一室から電話を交わすというもの。
後半部では、青年シーモア・グラスと幼い少女ミュリエルが浜辺で「バナナフィッシュ」について話すというパートになっている。
初めて読んだ当時、学生だった僕はサリンジャーの作品に対する知識はまったく持ち合わせておらず(いまも持っているとはとても言えない)、前半パートと後半パートのつながりというものが見えてこなかった。
なぜこの作品の前半に、ミュリエルのマニキュアがどうだの、シーモアが木の方を見ないように車を運転するだの、彼はオーシャン・ルームにいただのと書いてあるのは、この物語の成立過程と関わりがあるのだ。
「バナナフィッシュにうってつけの日」は、「手がかりが見えない」小説だと僕は考えている。
もともと「バナナフィッシュにうってつけの日」の初稿には、前半の「ミュリエルが電話する」パートがなかったことを知っているだろうか?
前述のウィリアム・マックスウェルが目にしたサリンジャーの原稿は、後半パートのみの作品だった。おそらくさらにつかみどころがなかったはずだ。
ニューヨーカー誌の編集者でさえ「なにかそこに物語が、あるいはポイントがまったく見つからない」ので、後半の「バナナフィッシュ」パートのみでは掲載できないと判断したのだろう。
サリンジャーはこの小説の提出から約1年掛けて根気強く改稿し、1948年1月に『ニューヨーカー』誌上に採用されることになる。
そこには、もともとなかったはずの冒頭のパートが付け加えられていた。
なので、後半の「バナナフィッシュ」のパートを、『ニューヨーカー』の一般読者に納得して貰えるように、前半部の「ミュリエルの電話」パートが付け加えられたと考えられる。
乱立する「バナナフィッシュ」の解釈

「バナナフィッシュにうってつけの日」を簡単に言うと、シーモア・グラスという青年が、浜辺にいるシビル・カーペンターに向かって「バナナフィッシュ」という架空の生き物についての話をしたあと、ホテルの一室で拳銃自殺をする、という物語。
「なぜ、シーモアは死ななければならなかったのか?」がまったく描かれていないので、初見だとまず間違いなく鮮やかな結末に見える。
誰もシーモアが死ぬとは予見できないまま、彼はオルトギーズ自動拳銃の引き金を静かに引いて退場する。
「バナナフィッシュ」の解釈は文学ファンのみならず、文学者や研究者によっても意見が割れるので、これが正解ですとはっきり言える解釈はない(もともと文学とはそういうもの)。
ただ定説というのはあって、色んな解釈をまとめると大体は「戦争が引き起こした精神的な病の影響がシーモアに認められる」という解釈に落ち着く。
たとえば、シーモアは第二次世界大戦の復員兵で、車で運転しているときに「木を見ると変になってしまう」というエピソードは「そこに敵が潜んでいると戦争の習慣で考えてしまう」あるいは「森のなかで多くの味方が死ぬような激戦のトラウマ」を持っているからと言えなくもない。
シーモアは刺青を見られたくなくてバスローブを脱ごうとしない(実際にはシーモアに刺青はない)のは、戦争の傷痕を見られたくないという暗示とか、亜鉛華軟膏を塗った女は傷病兵の治療に使われるものだから戦争を連想させる、とか。
けれども「シーモア・グラスは戦争で心に傷を負って、だから精神的に錯乱して自殺したんだ」と言われても、僕にはどうも納得できない。
サリンジャーはそんなことを遠回しに読者に伝えるためにこの小説を書いたのだろうか? この結末が鮮やかに見えるのはシーモアの自殺の動機を巧妙に隠したから?
「バナナフィッシュにうってつけの日」のエピソードには、戦争にまつわる解釈が無数にあるけれど、それは枝葉末節のようなもので、そこにこだわる必要性が僕にはよく分からない。
「バナナフィッシュにうってつけの日」を読んで「シーモア・グラスが死んだのは戦争のせいなんですね」と言って納得するようなら、それはミステリー小説の読み方だと思う。
本を離れて考えてみればすぐに分かることだけれど、人間が死ぬ理由っていうのは、これが原因だとはっきり言えるものはない。
新聞やニュースでよく「〇×さんは『いじめ』が原因で亡くなった」「△△さんは『過労』が原因で~」と聞くけれど、ほんとうにそれだけが原因かというと、おそらく違う。そういう表現に慣れてしまっているだけだ。
「何か物事が起きるには、それに相応する原因が必ずなければならない」と僕たちは考えやすい。
こういう現実的な考え方(因果律)をそのまま文学の解釈に持ってくると、小説の根っこの部分が見えてこない。
人物Aの行動に合う描写を、ひたすら別の箇所から探し出してきてそれを当てるために読むことになる。
どんな文学作品もそのひとにとっては早押しのクイズ番組に過ぎないものになるだろう。
だけど、古典となるような文学作品は、そういうミステリー小説のようなやり方では書かれていないことがある。
作中の重要人物Aが何の理由もなく死ぬ、というのは文学作品では普通に描かれる。カミュの異邦人が分かりやすい例だけれど、銃を撃ったのは「太陽のせい」だと言う。辻褄が合わないように見えるが、ムルソーは嘘を吐いているわけではない。
僕はサリンジャーが、シーモア・グラスの拳銃での自殺を、何か特定の原因があった上で起きたことだと描いたようにはとても思われない。
サリンジャーの書く小説に出てくる登場人物はみんな「おしゃべり」で「饒舌」だ。でも彼らには特徴があって、ホールデンもフラニーもエドナも(そしてシーモアも)、みんな「言って、隠す」のだ。
だから、サリンジャーの小説を読むときは、言ったことよりも、「言われていないこと」の方に目を向けなければならない。
「バナナフィッシュ」の前半で山のように出てくる戦争がらみのことは単なるミスリードではないかと僕は思っている。
シーモアの戦後の病に関するエピソードが次々に表に出てくるのだから、シーモアが自殺した理由を戦争に求めることができれば、大方の「ニューヨーカー」誌の読者は納得する。
彼らは、誰かが死ぬのには理由がなければならないと考えるから。理由らしきものさえあればそれをストーリーと呼んで満足するのだ。
でもそれはサリンジャーが予め用意していた落とし穴じゃないだろうか。
サリンジャーはシーモア・グラスを最初から死なせるつもりで書いたと思う。でなければ、結末のシーンまで読者をだまし通すことはできない。
あの物語が面白いのは、誰もがシーモア・グラスが死ぬようには見えないように書かれてあったことで、サリンジャーは途中の思いつきでシーモアを殺したわけではない。
シーモア・グラスは最初の時点から自分が死ぬことを知っている人間として行動しているように僕には見える。
シーモアとミュリエルはなぜ同じ浜辺にいないのか?

作中で疑問に思われるのは、なぜ夫妻であるはずのシーモアとミュリエルは同じ場所にいないのか? ということである。
冒頭でミュリエルは実母に電話を掛けている。実母は、戦争後に精神錯乱の兆候があるシーモアのことをよく思ってはいない。何かにつけ、シーモアと別れさせようとする雰囲気をにじませているが、ミュリエルはシーモアをかばいつづける。
話題はほとんどシーモアについて語られるが、妻であるミュリエルが同じホテルの一室、507号室でシーモアと一緒にいられるのは、シーモアが引き金を引く最後の瞬間のみである。
しかも、シーモアは妻のミュリエルのことを「ミュリエル」とは認識していない。ただ「ツイン・ベッドの片方に身を横たえて眠っている女」として描写される。
この物語は異様なほどの対称性を保っている。ミュリエルが起きているとき、シーモアは浜辺で寝そべっていて、ミュリエルが眠っているとき、シーモアは活発に動き出す。
ベッドはダブルベッドではなく、「ツイン」の「片方」とわざわざ書かれているのがいい例だ。
冒頭の507号室と結末の507号室は、ほんとうに同じ部屋なのかと疑いたくなるくらい、シーモアとミュリエルは同じ時間と空間を共有することがない。
ミュリエルとシーモアは結局、お互いにひと言も喋らないまま離れていくことになる。彼らが話した相手はそれぞれ、実母とシビル・カーペンターで、死の間際に話す相手を間違えているように見える。
ミュリエルはいますぐ電話をやめて、浜辺にいるシーモアを探しにいくべきだし、シーモアはバナナフィッシュの話を出会ったばかりの少女に話しかけている場合ではない。
「ミュリエル」と「シーモア」は鏡合わせの関係にある?
シーモア・グラスは「Seymour Glass」と綴るけれど、翻訳にもある通り、「see more glass(もっと鏡をよく見て)」という意味も込められている。
僕は第Ⅰのパートと第Ⅱのパートは鏡合わせの関係性にあるのではないかと考えている。
どうしてそんなことを考えたのかというと、ミュリエルとシーモアの話す言葉がどう見ても奇妙なのだ。
たとえば、ミュリエルと実母の会話にはこんなくだりがある。
「とにかく今すぐ旅行なんてできそうもない。すっかり日焼けして身体もろくに動かせないの」
「ナイン・ストーリーズ」J・D・サリンジャー 野崎孝訳 (1988改版)新潮社
「そんなにひどく焼けちゃったの? あの<ブロンズ>のクリーム、使わなかったの? 鞄の中に入れてあげたじゃない。ほら、あそこの――」
「使ったわよ。でも焼けちゃったの」
「困ったわねえ。どこが焼けたの?」
「どこもかしこもよ、全身」
「まあ、困ったわねえ」
「でも、死にやしないわ」
ミュリエルはフロリダのホテルに「水曜の朝に着いたばかり」で浜に出たような描写はない。本来、「焼ける」可能性があるとしたらシーモアの方だ。
でもシーモアはバスローブをまとっていて「肩は白く」焼けた様子はない。終盤でバスローブを「ぴったりと襟まで合わせ」ている。その理由は、ないはずのいれずみを見られたくないという奇妙な理由だ。
ミュリエルの台詞も日焼けで「死にやしないわ」とまで言うのは少し大げさな表現ではないだろうか。
この第Ⅰ部のミュリエルは、ホテルの部屋にいながらにして、シーモアがいま「どこで」「何をしているか」分かっているという不思議な能力を持っている。
「で、先生は何て言ってらした? そのときシーモアはどこに居たの?」
「ナイン・ストーリーズ」J・D・サリンジャー 野崎孝訳 (1988改版)新潮社
「オーシャン・ルームよ、ピアノ弾いてたわ。彼、ここに来てから二晩ともピアノ弾いてるの」
ミュリエルはこのとき、精神分析の医師からピアノを弾いてるのはご主人か? と聞かれてそうだと答えている。ただオーシャン・ルームがあるのは「向こうの」部屋である。
「お母様」と娘は言った。「もう切りましょう。シーモアがそろそろ帰ってくる時間だから」
「ナイン・ストーリーズ」J・D・サリンジャー 野崎孝訳 (1988改版)新潮社
「今どこなの、あの人?」
「浜よ」
このミュリエルの言葉も変だ。どうしてミュリエルにはシーモアが帰ってくる時間だと分かったのだろう。シーモアが帰ってきたときに電話を掛けているとまずい都合でもあるのか?
また、シーモアがホテルの部屋に帰ってくると分かっていたのなら、なぜ最後のシーンで彼女は眠っているのだ? もしミュリエルが起きていたら、シーモアの自殺は防げただろう。
このあとも「彼は浜辺でただ寝そべっているだけ。バスローブを脱ごうともしない」とまるでその場を見てきたかのような返答をしている(実際にシーモアは浜辺で寝そべっていた)
そして「ミュリエルの電話」パートの終わりには奇妙な言葉が挟まれている。
「ミュリエル、ちょっと待って、あたしの言うこと聞いてちょうだい」
「ナイン・ストーリーズ」J・D・サリンジャー 野崎孝訳 (1988改版)新潮社
「なあに」そう言って娘は右脚に体重を掛けた。
「あのひとがちょっとでも変な真似をしたり、変なことを言ったりしたら、すぐに電話してちょうだい――分るわね、あたしの言う意味。あんた、聞いてるんでしょうね?」
僕は小説を書いたことがあるから分かるけれど、普通なら絶対に書かない説明の台詞をサリンジャーは挟んでいる。
「そう言って娘は右脚に体重を掛けた」
この電話のシーンではあまりにも不自然すぎる描写だ。電話のシーンでなぜ「娘が右脚に体重を掛ける」ことが重要なのだ? そして実母はどうしてこんなに必死に娘に呼びかけている?
バナナフィッシュの結末のパートで、シーモアはエレベーターで同乗した「鼻に亜鉛華軟膏を塗った女」にこう呼びかけている。
「あなた、ぼくの足を見てらっしゃいますね」エレベーターが動き出したとき、女に向かって青年が言った。
「ナイン・ストーリーズ」J・D・サリンジャー 野崎孝訳 (1988改版)新潮社
「何ですって?」と女が聞き返した。
「あなた、ぼくの足を見てますねと言ったんです」
最後は507号室でツイン・ベッドのふさがってない方のところへ歩いて行って腰を下ろし、「右のこめかみを」拳銃で撃ち抜く。
このとき、僕が思い浮かべたのは「右脚に体重を掛けたミュリエルは何をしようとしているのか?」ということだ。
なぜ、フロリダの海岸までバカンスに出掛けたシーモアのトランクのなかに、当たり前のようにオルトギース自動拳銃が入っているのだろう?
もしこの小説がほんとうに鏡合わせになるように作られているとしたら、シーモアが自殺を選んだなら、ミュリエルもまた死を選ぼうとしたのではないか?
ミュリエルはほんとうにただ「眠って」いたのか?

僕はバナナフィッシュの「ミュリエル」は最後の場面で単に「眠って」いるのではなく、何らかの中毒症状による「昏睡」状態にあると考えている。
シーモアとミュリエルの匿名性が異様なまでに保たれているのは、彼らを生きている人間として描いているのではなく、通常とは違う事情がある人間として描いているからではないか?
五階で降りると彼は、廊下を歩いて行って、507号室の鍵を開けて入った。部屋には仔牛皮の新しいトランク類やマニキュアの除光液の臭いが漂っていた。
「ナイン・ストーリーズ」J・D・サリンジャー 野崎孝訳 (1988改版)新潮社
部屋に除光液の臭いが漂うほどの量がどのくらいのものか、僕は使ったことがないので分からないが、除光液には化粧品のなかでは毒性が高い「アセトン」という成分が含まれている。
また除光液の臭いの正体は「酢酸エステル」が含まれている可能性があり、これは「バナナ」のような臭いがするという。偶然にしては奇妙な一致だ。
ミュリエルのパートの締めくくりも返答としては、まるで別れを告げるみたいだ。
「いいから、ミュリエル、お母様に約束してちょうだい」
「ナイン・ストーリーズ」J・D・サリンジャー 野崎孝訳 (1988改版)新潮社
「分かったわよ。約束します。じゃあね、お母様。パパによろしく」そう言って娘は電話を切った。
ミュリエルは途中で何度もこの電話を切ろうとしている。電話の料金が高い、シーモアがもうすぐ帰ってくるから、と何かと理由をつける。
でもこの電話を掛けようとしたのは「実母」ではなく、「ミュリエル」の方だ。
タイトルは「バナナフィッシュにうってつけの日(A Perfect Day for Bananafish)」になっているが、物語の筋を読めば自殺にうってつけの日だったとも読める。
先に自殺しようとしたのは「シーモア」ではなく「ミュリエル」だったのではないか? もしくは二人は自殺するためにこのフロリダの海岸までやってきた可能性はないのか?
「シーモア」が帰ってくると分かっていて、電話を切ったミュリエルが最後の場面で「眠って」いるのは明らかに不自然だ。
僕の見立てとしては、マニキュアの除光液に含まれている成分を故意に服用し、ミュリエルは中毒症状により昏睡した。
電話のなかですっかり「日焼け」したので身体もろくに動かせない、と言っているが、「日焼け」で動けないということはないだろう。
「全身が焼けるような」「でも死にやしない」のは、除光液の成分を吸ったか飲用したか。
ホテルの部屋番号、「507号室」は、オルトギーズ自動拳銃の口径7.65ミリを逆から読んだもの。「0」に入るのは「6」で、バナナフィッシュがくわえていたバナナの本数をシビルが「6本」と答えており、自殺に使う部屋として暗示していた可能性がある。
765という数字がぴったり当てはまるところは作中でここしかない。ミュリエルが「ビンゴ」大会に参加しているのはヒントだったかもしれない。ビンゴでは真ん中の穴を開けるのが通例だ。
「ミュリエルの電話」パートで話されていることは主にシーモアのこと。では、シーモアは何を話していたかというと「バナナフィッシュ」の話をシビルにしている。
でも、第Ⅰパートと第Ⅱパートは鏡合わせで対称的な関係にあると考えると、シーモアが話していた「バナナフィッシュ」の話はミュリエルについて話していたのではないか、と僕は考えた。
バナナフィッシュは架空の魚で、穴のなかに入るまえにはごく普通の魚だが、バナナ穴のなかに入ってしまうと豚みたいに行儀がわるくなって大量のバナナを平らげてしまう。
バナナを食べ過ぎたバナナフィッシュは肥えてしまって、二度と穴の外には出られず、最後は「バナナ熱」にかかったまま穴の中で死んでしまう、という話。
何ともつかみどころのない抽象的な話なんだけど、人間に当てはめてみるとどうもバナナフィッシュのバナナに麻薬のような意味を持たせているように見える。
シーモアがこれから自殺することを仄めかしている話に聞こえなくもないが、ここで話されているバナナフィッシュの話は、明らかに中毒症状と似ていて、そのイメージはシーモアには合わない。このイメージが合うのは、どちらかというとミュリエルだと思う。
追記(2023/12/11):
もうひとつ別の解釈としては、バナナフィッシュは悟った人間だけが見えるものとしている可能性がある。
「バナナフィッシュ」は英語で「bananafish」と綴る造語なのだが、サリンジャーと編集者の間でこれを一語で表すか、二語にして「banana・fish」と区切るかで話し合ったというエピソードがある。
バナナは「黄色」で、フィッシュは「青色」を象徴する。このことが実は、シーモアがシビルの水着の色を間違えたこととも絡んでくる。
普通のひとなら「黄色」と「青色」を別のものとして認識するけれど、悟ったひとにとってはこの「色の違い」は「ない」ものとして見ることができる。
つまり「バナナフィッシュ」が見えるひとというのは「黄色」とか「青色」とか、そういう区別(分別)を付けずに見ることができる。
そういうひとにとって「バナナ(黄色)」でも「フィッシュ(青色)」でもなく、「バナナフィッシュ(黄色でもあり、青色でもある)」が見える、という意味かもしれない。
バナナフィッシュがバナナ穴に入っていって戻れなくなる話は、一度、悟ってしまうともう元の見方には戻れない「不可逆性」を表していると思われる。
そして悟っているがゆえに、孤独に穴のなかで死んでしまう。
シーモアというのは、天才的なグラス兄弟のなかでも最も「悟り」に近いような賢い人物として描かれている。
やはり、シーモアが「バナナフィッシュ」のたとえ話を持ち出したのは、自らが「死ぬしかない」ことを打ち明けたシーンだと思う。理由は後述する。
「シビル」に見立てられた不可解な少女「シャロン・リプシャツ」
この物語にはもうひとり、不可解な人物が登場する。それがシャロン・リプシャツで、彼女はオーシャン・ルームでピアノを弾いていたシーモアの隣に座った、3歳半の幼い女の子である。
そう主張しているのシビル・カーペンターで、このシャロン・リプシャツという女の子はシーモアとシビルとの話の間にしか出てこない。
しかし、向こうの部屋(オーシャン・ルーム)でピアノを弾いているのはご主人か、と聞いた精神科医がいて、医師は「ご主人は身体の具合でも悪いのか?」と尋ねている。
このときに部屋にいたのは、シーモアひとりだったのか、シャロン・リプシャツが同席していたのか、謎が残る。
ちなみに、シーモアがここに来てから二晩ともピアノを弾いている、とミュリエルが話しているのでバナナフィッシュの物語の冒頭開始時刻は、金曜日の14時半と推定できる。
さらに<1948年度のミス・精神的ルンペン>というあだ名をシーモアはミュリエルに名付けているので、年は1948年、場所はフロリダ海岸のホテル。
補足しておくと、キリストの磔刑があったのも金曜日の15時頃という説が有力だ。
もしサリンジャーがシーモアにキリストと重ね合わせる意味を持たせていたとしたら、シーモアが引き金を引いたのは、30分~1時間後の15時前後と思われる。
物語の登場人物に「キリスト」を重ね合わせる、というのは少々突飛な話だと思われるかもしれない。
しかし、同時期のアメリカ文学でこれをやったひとがいて、アーネスト・ヘミングウェイの『老人と海』だ。老人と海のサンチャゴはキリストをモチーフにしているのではないかという説がある。
アメリカ文学で物語の登場人物をキリストと重ね合わせる手法はあり得ると、参考程度に考えて貰えばよい。なお、サリンジャーはヘミングウェイと戦時中に親交があった。
シャロン・リプシャツという女の子がシーモアの隣でピアノを弾いていたことに対して、シビルは嫉妬している。
シーモアはこれに対して「ああ、シャロン・リプシャツか。よくそんな名前が思い浮かんだもんだ。記憶と欲望を混ぜ合わし、か」と呟いている。
シャロン・リプシャツという女の子が実際に存在しているのかは不明である。シビルが嫉妬のために嘘を吐いたとも考えられるからだ。
存在しているとしてもシャロン・リプシャツという名前ではない可能性が高い。
このシャロンという実在が不明確な少女の謎が物語にどう関わるのか、僕には繋がりが見えなかったが、シャロンとシーモアの絡みでひとつ気になる箇所がある。
シーモアは、シビルをなだめるために、「シャロンをきみだと思うことにしたのさ」と言うくだりがある。
「あのね、シビル、聞けばなあんだってきみも言うようなことさ。ぼくはあそこに坐ってピアノを弾いてた。きみの姿はどこにもなかった。そこへシャロン・リプシャツがやって来てぼくと並んで腰かけた。押しのけるわけにもいかないだろう?」
「ナイン・ストーリーズ」J・D・サリンジャー 野崎孝訳 (1988改版)新潮社
「いくわよ」
「いや、いかん。それはいかんよ。そんなことはぼくにはできない」と、青年は言った「でもね、僕がどうしたかを教えてあげよう」
「どうしたの?」
「シャロンをきみだと思うことにしたのさ」
ここで引っ掛かったのは、シーモアは「シャロン」を「シビル」に見立てたことだ。僕はこれを「バナナフィッシュ」の謎を解く鍵のひとつかもしれないと考えている。
シーモアはシビルの着ている「カナリア色(黄色)」の水着を見て、「きみのその水着、いい水着だね、ブルー(青色)の水着っていうの、こんなに好きなものはないな」と言う。
普通に考えれば「黄色」のものが「青色」に見えるなどありえない。つまりシーモアは、目の前のものを違うものとして認識していますよ(見たままの通りには認識していませんよ)、ということ示している。
シーモアは「シャロンをきみだと思うことにした」と言うが、実はシーモアはシビルに対しても同じことをしたのではないかと僕は疑っている。
つまり、シーモアは「シビル」を別の誰かに見立てて話している可能性はないのか? ということだ。
ここでヒントになるのが、「ブルー」という色味で、作中で青いものを好んで身に着けていた可能性がある人物がシーモア以外にもうひとりだけいる。
「そう。で、あんたのブルーのコートの具合は?」
「ナイン・ストーリーズ」J・D・サリンジャー 野崎孝訳 (1988改版)新潮社
「まあいいわ。パットを少しとってもらった」
ミュリエルである。
ミュリエルの身につけている衣装についても、少し妙な話があるので、ここで書いておきたい。
ミュリエルの服装については冒頭で記述されている。彼女はホテルから電話を掛けているが、白い絹の化粧着のほかには何一つ身につけていないと言う。
人物の衣服を示したければ「ミュリエルは白い絹の化粧着を着て」と書けばいい。ご丁寧に他に何も着けておらず、指輪はバスルームに置いてきたという。
ホテルの室内だからおかしくないと言えばおかしくないのだが、ミュリエルが仮に自殺未遂を行うつもりだという立場で見ると、ちょっと符号するものがある。
アメリカでは遺体が包まれるときの服に白い絹が使われる場合がある。その下には何も着けないことが多いようだ。
これは少し気になった程度なので単なる憶測ぐらいで考えて貰えるといい。
ミュリエルに関してさらに付け加えると、あれだけ丁寧にマニキュアを仕上げていたはずのミュリエルが、最後のシーンで除光液を使っているらしい(除光液の匂いが部屋に漂っている)のはどういうわけだろう。
「やりかけていたことを慌ててやめるような女ではない」ミュリエルが、なぜ爪の輪郭まできっちり見えるように塗ったマニキュアを、わざわざ剥がす理由があるのか?
そもそもミュリエルが「やりかけていたこと」とは、マニキュアを塗ることだったのだろうか。
オルトギース自動拳銃が入ったトランクと除光液の奇妙な並列
シーモアが507号室に入っていったとき、部屋には「仔牛革の新しいトランク類」や「マニキュアの除光液」の匂いが漂っていたという。
サリンジャーは部屋にいくつもあるはずの匂いのなかから、わざわざこの二つを並列させるように書いている。
ちなみに仔牛革のトランク類のひとつには、シーモアが自殺に使うことになるオルトギース自動拳銃が入っている。
この二つの並列が仮に、シーモアとミュリエルがそれぞれ自殺に使ったものの象徴と考えるとどうだろうか。
「鏡合わせ」になる法則がここでも働いているとしたら、シーモアが自殺に使ったものがトランクに入っていたとしたら、マニキュアの除光液を使って自殺を試みた(未遂に終わった)ミュリエルという説はないだろうか。
作品のなかで、はっきりと明言されていないのは「シーモア」と「ミュリエル」の名前だ。
シビルはシーモアのことを「see more glass」と言っただけだし、「ミュリエル」は実母からそう呼ばれているが、地の文ではぜったいに名前が呼ばれることはない。ただ「女」とだけ記述される。
この二人がなぜ匿名なのかというと、僕なりの考えとしては、この二人は通常考えられている、ひとりずつの「人間」ではなく、二人でひとつの存在だからというのが、僕の仮説だ。
作者のサリンジャーは、「この二人のうち、いずれどちらかが死ななくてはならない」、「シュレディンガーの猫」のような状態にいる存在として、シーモアとミュリエルを描いているように見える。
「謎解きサリンジャー」が提示したヒント
第Ⅰパートでミュリエルは「右手右脚」しか使っていないという説を知っているだろうか?
これは「謎解きサリンジャー」(竹内康浩・朴舜起著 新潮社刊)という本に載っていたことなのだけれど、会話文ではなく、地の文を注意深く観察すると、ミュリエルが身体の右の片方しか使っていないことが分かる。
この理論に則れば、ミュリエルがバスルームに指輪(結婚指輪らしきもの)を置いてきた理由も分かる。結婚指輪は通常、左手の薬指にするもので、それを着けていると「左手」が使える(実在する)ことになってしまうから。
「謎解きサリンジャー」では、ここから義足であることを見いだして、シーモアとして描かれている男は、バディ・グラスでもある可能性に言及している。
ただその場合、シーモアの死については説明が付くけれど、ミュリエルが「右手右脚」のみの存在であることに説明がつかないのでは? と思ったりもした。
作中ではシビル・カーペンターも「左手左足」しか使っていない。唯一、シーモア・グラスだけが「両手両足」を使うことができる存在として描かれている。
このことは何を意味するだろう?
僕は、ほかの登場人物がみんな片手片足しか使えない中で、シーモアだけが「両手両足」を使えるということは、「完全性」を表すと思っている。
おそらくサリンジャーが言いたいのは、普通のひとはみんな「片手片足」で生きているものだということだ。
つまり、「誰かの支えがなくては生きてはいけない」、「もう片方の支えを必要とする」ことを、ミュリエルやシビルが「片手片足しか使わない」ことによって描いている。
普通のひとは、「不完全」で、「自己完結」することはできない。だからこそ、誰かを頼ったり、関係を持ったりすることができる。
しかし、シーモアというのは「悟った」人間として描かれている。シーモアは「誰かの助けや支えがなくても立ったり、ものを掴んだりできる」存在だ。
そういう「シーモア」にも苦悩があって、それは「ミュリエル」や「シビル」のようなものの見方には「戻れない」ことだ。
「バナナ穴」の中に入っていくバナナフィッシュの話の「不可逆性」とも繋がる。
ミュリエルは「普通の女の子」で、「シーモア」のことをひとりの夫として求めている。
シーモアはミュリエルの足りない左半身、つまり「左手左足」の存在になってやりたいが、彼には「両手両足がすでにある=悟ってしまっている」ので、ミュリエルが望んでいる「普通の夫」にはなれない。
このままでは「ミュリエル」の願いを一生叶えてやれないまま、形だけの夫婦として過ごすかもしれない。
「ミュリエル」はいつか思い詰めて、何らかの行動に出るかもしれない。
そうなる前に、自分がいなくなることで、「ミュリエル」のことを自由にしてやりたい。
シーモアはそう考えたのではないか。
ツインベッドに二人が横たわったとき、ミュリエルは「右手右足」をベッドに埋めていて、シーモアは拳銃自殺をしたあとに「左手左足」をベッドに埋めることになる。
シーモアが拳銃自殺によって半身を失ったとき、はじめて彼はミュリエルにとって欠けていた片方を埋める存在になれる。
つまり、シーモアは自殺しなければ、ミュリエルのほんとうの花婿になることができないという運命を背負った男だったのではないか?
シーモアの視点から会話の流れを再現する
ここで物語に戻って、シーモアの視点で物語を再現してみよう。シーモアは最初、シビルに「see more glass」と声を掛けられる。
シーモアはここで自分の本名「seymour glass」を言い当てられた、と思って思わず襟元までローブで隠す。シーモアが隠していたはずの本名を言われたとしたら、その人物は誰なのか?
自分の本名を知っているのは、同じように匿名の妻である「ミュリエル・グラス」だけのはずで、シーモアは「シビル」のことを見ながら、この子は実は「ミュリエル・グラス」なのだと錯覚する。
シビルはおかまいなく「パパが明日ヒコーキで来るの」と言う。「ミュリエルの『パパ』が迎えにくる」と考えたシーモアは、ミュリエルのパパ(父親)が娘(ミュリエル)のことをひどく心配しているのを知っているので「そろそろ来てもいいころだ、もう来るだろうとしょっちゅう思っていた」と言う。
「女のひとはどこ?(シビルの意味は『ミュリエルはどこにいるか?』)」とシビルに聞かれるが、「ミュリエル」に聞かれていると考えているシーモアは「そいつは難問で、いそうなところは何千とある」と答える。
シビルのことをミュリエルだと考えているシーモアは、「ミュリエルが好む色はブルー」だと知っていて、シビルが着ている水着は「ブルー」であるに違いないと考える。実際には「黄色」なのでシビルは否定する。
ここでシーモアはシビルの足をつかまえて、その足が両足あるかどうかを確認している。(否定されたので、再び、シビルが誰か分からなくなった状態)。
シーモアは相手を確認するために「自分の生まれは山羊座」だといい、「きみは?」と問う。星座によって相手が誰か当てようとしている。しかし、会話はかみあわず、シビルに話を逸らされる。
シャロン・リプシャツの話があり、「自分は誰かに見立てて話している」つもりであることをシーモアはシビルに向かって明かす。
「きみも若いころにはずいぶんバナナフィッシュを見たことがあるだろう?」と尋ねる。幼いシビルに「若いころ」と言うのは不適切だが、ミュリエルに話し掛けているつもりなら「若いころ」と声を掛けるのは正しい。
あるいは、もっと赤ん坊のように生まれたての頃なら、ものごとを「バナナ(黄色)」とか、「フィッシュ(青色)」とか、区別せずに「バナナフィッシュ(青でもあり、黄でもある)」として見ることが出来ただろう? という意味。
シビルが答えなかったので、シーモアは再びどこに住んでいるか? と尋ねる。(シーモアはまた相手が誰だか分からない)
「コネティカット州ホーリーウッド」と答えると、それは「コネティカット州ホーリーウッドの近くか」とオウム返しをする。
シビルはわけが分からないが、もういちど同じ答えを返し、「左手で左足」をつかんで、片足跳びをするという奇妙な動作をする。
シビルの答えとこの奇妙な動作を見たシーモアが「万事がはっきりした」と言う。(つまり、片手片足で動くシビルはまだ「悟ってはいない」のだとシーモアは確信した)
このあとは延々とオウム返しの会話を続け、シビルを呆れさせる。(禅問答でシビルを試している)
バナナフィッシュの話は、自身の本心(自らがこれから死のうとしていること、他に打つ手はないこと)をシビルにたとえ話を通して打ち明けたように読める。
シビルも同様に片手片足の存在として描かれている。青年はシビルの濡れた足の片方を持ち上げてキスをし、最後は別れていく。(シビルがミュリエルではなく、シビルだと分かった。キスした足が左右のどちらか描かれていないが、おそらく左足)
エレベーターで見知らぬ女に足を見られるのをいやがるのは、自身が「両手両足」が使える存在であることに注目されたくなかったから。
最後は眠っている(あるいは、マニキュアの除光液で自殺を図った?)ミュリエルを自由にするために、シーモアは右のこめかみを撃ち抜いた。
もしシーモアにキリストのイメージを当てはめるとするなら(シーモアは山羊座だと言っている。キリストの誕生日が12月25日だと仮定すれば、山羊座で一致)、ミュリエルを救うために死で贖おうとしたと見ることができるかもしれない。
シーモアは「自分がいなくなれば、ミュリエルを助けることができる」と考えていたに違いない。
シーモアが拳銃自殺を終えたあとの二人は、はじめてベッドで眠って半身を埋め、「片手片足」ずつの存在になる。そういう形でしかシーモアは彼女に愛を示すことができなかった。
まとめ 「わからない」けれど「美しい」小説

いずれにせよ、この『バナナフィッシュにうってつけの日』には通常の論理では読み解けないものが含まれていることは確かだと思う。
僕の解釈はあまり一般的なものではない。大いに誤読している可能性は十分にある。正直にいうと、僕は「バナナフィッシュにうってつけの日」の小説を理解することはできなかったと白状する。
ただその「分からなさ」を整理するために、今回の記事を書いた。疑問点の洗い出しという意味で、「こんな風に読んだやつもいるんだ」ぐらいの、与太話ぐらいに考えて貰えれば幸いだ。
ここに書いた解釈は明らかにとんでもない異説だと僕自身でも思っているので、間違っても鵜呑みにはしないように。
こんな考察なんか抜きにしても、「バナナフィッシュにうってつけの日」の物語が美しいことには変わりない。
たとえシーモアが拳銃で頭を撃ち抜くにしても、そのときはじめてシーモアはミュリエルと同じ場所にいて、ツイン・ベッドで向かい合わせに眠っている。
(了)





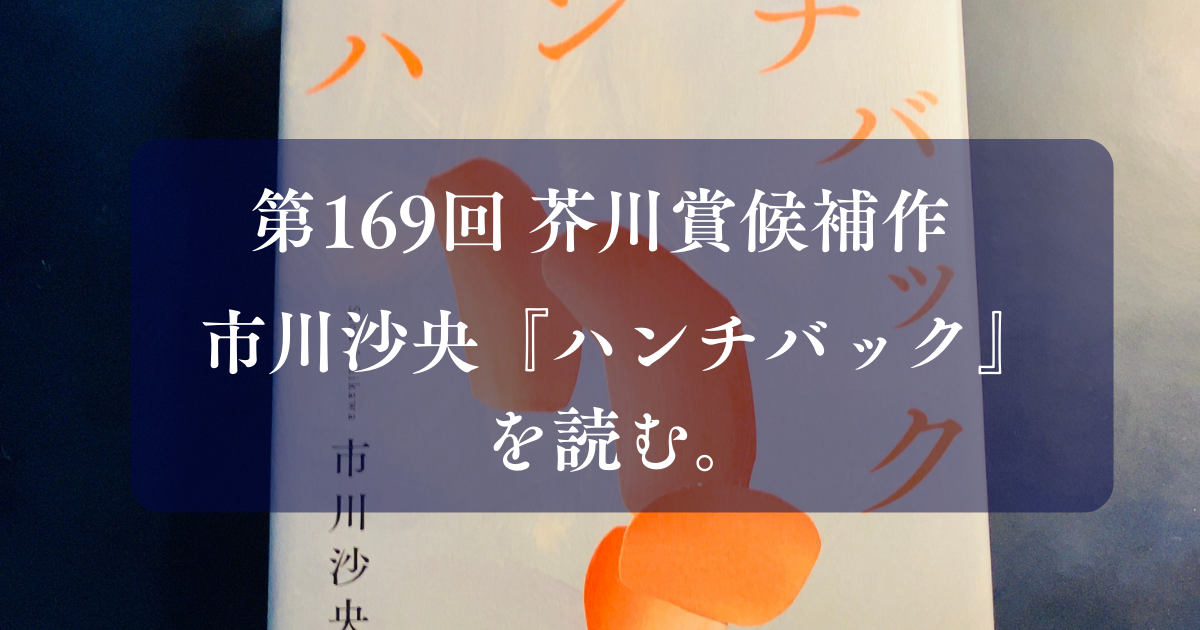


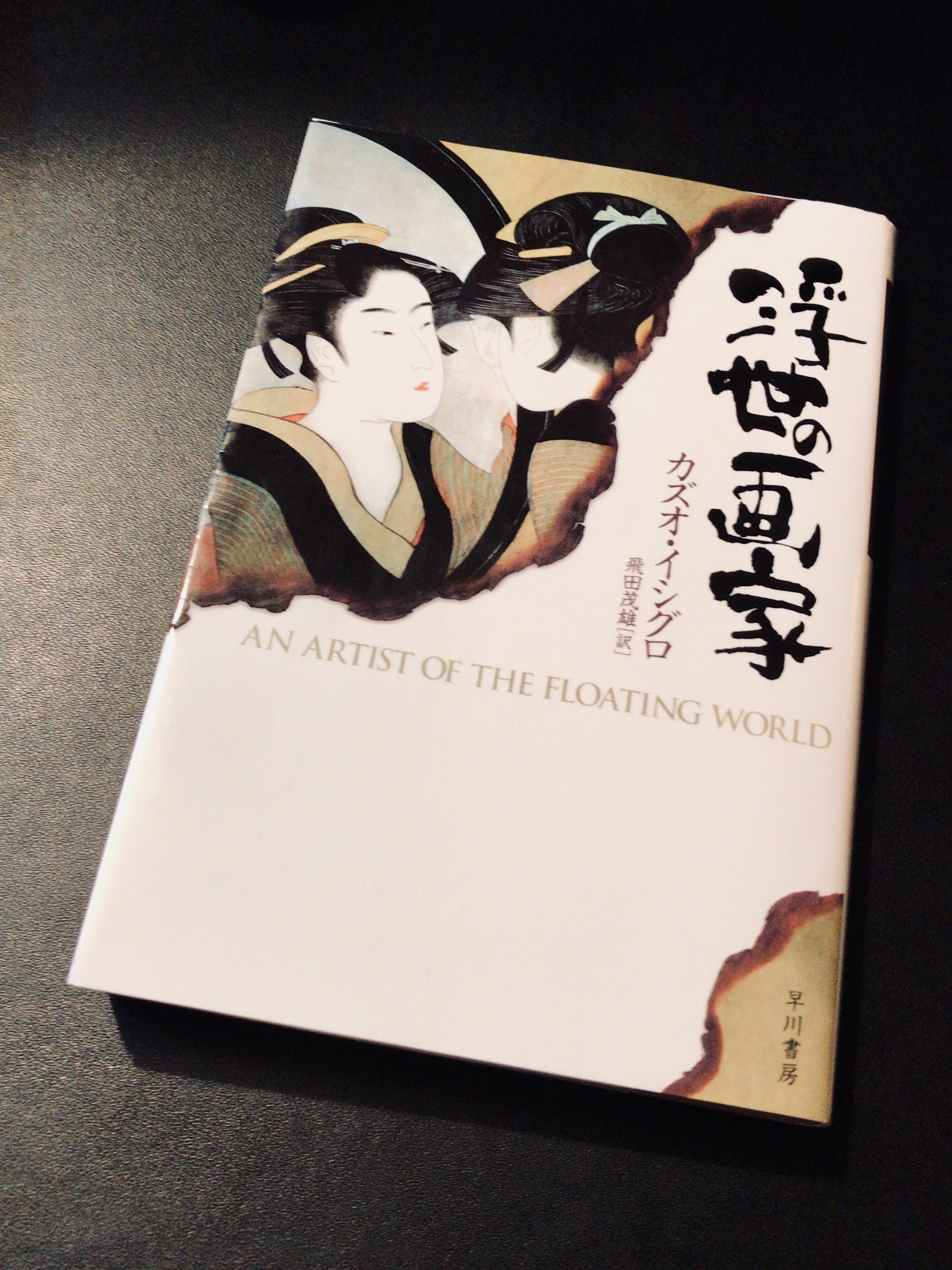
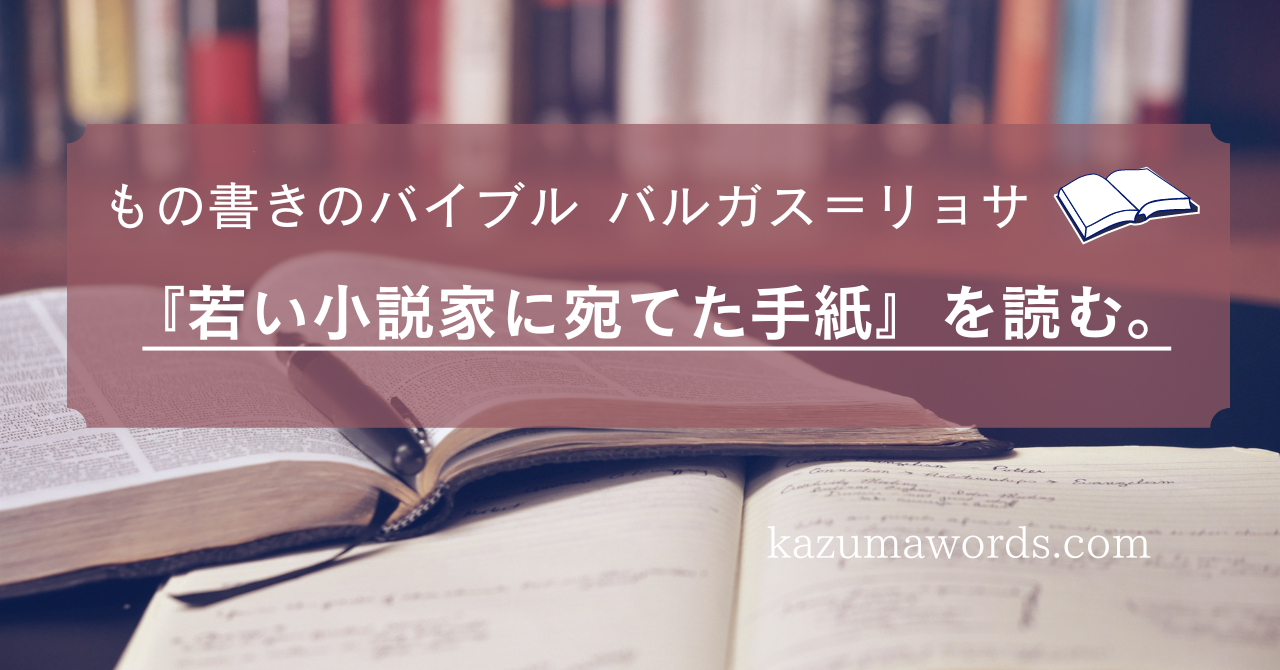




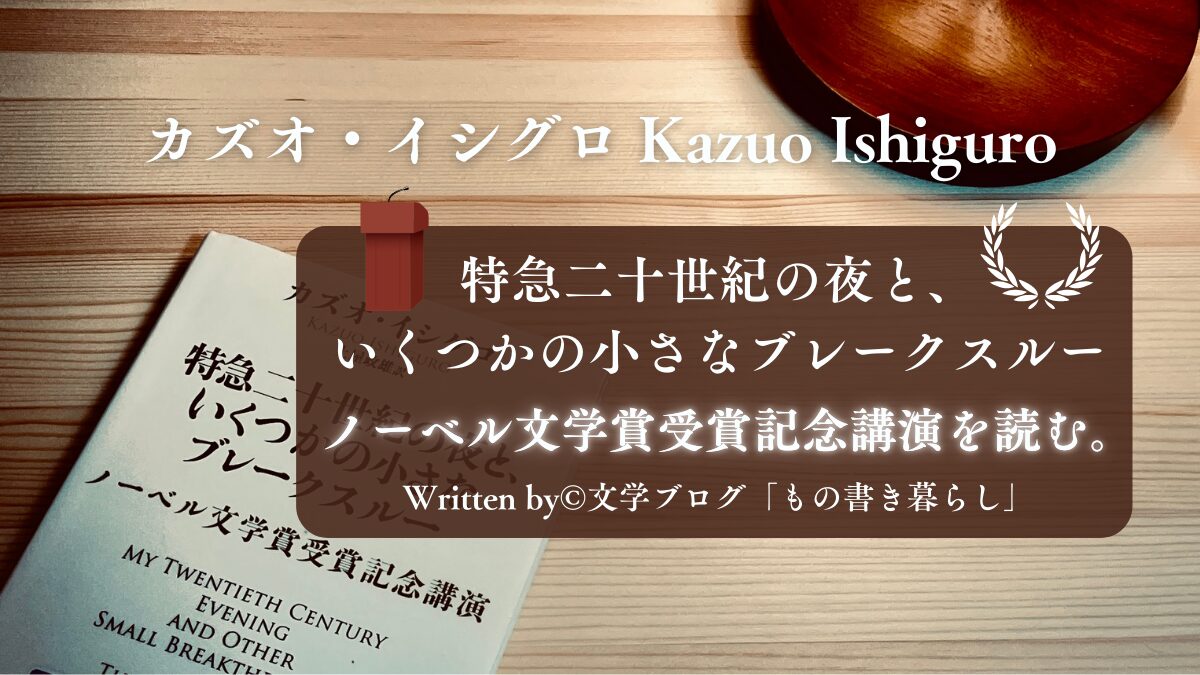
解説面白かったです!
サリンジャーは好きだけど、バナナフィッシュにうってつけの日については読後ポカーンでした。
面白いとは思ったんですけど
戦争のトラウマを示唆する描写は多いので、
まあそういうことかな?って自分なりに納得しようとしてましたが、そんな簡単というか単純なことでもなさそうですよね。
ありがとうございました♪
まこさんへ
コメントをお寄せくださり、ありがとうございます。管理人のkazumaです。
『バナナフィッシュにうってつけの日』の考察を楽しむきっかけになれば、とても嬉しく思います。
この作品を『戦争の影響が見られる』というだけで解釈するには謎が多く残り過ぎています。
シーモア・グラスが「戦争のトラウマ」のためにオルトギースの引き金を引いたようには、僕には見えません。
ネット上には「戦争のPTSD」でこの作品を片付ける解釈ばかりなので、一石を投じるために書きました。
僕はどちらかというと、戦争よりも妻のミュリエルを自由にするためにシーモアは自殺したのだと思っています。
何十回もこの作品を読み直しましたが、サリンジャーは「戦争のせい」ですべてを片付ける作家ではありません。
サリンジャー本人は、生涯で戦争のことをほとんど口外しなかった人です。
そんなことを言うためにサリンジャーはこの作品を書いたわけじゃないよな、といつも思っています。
読んだ時の「違和感」はきっと大切なものなので、それを離さずに持ち続けていると、自分なりに納得できる読み方に辿り着くかもしれません。
kazuma