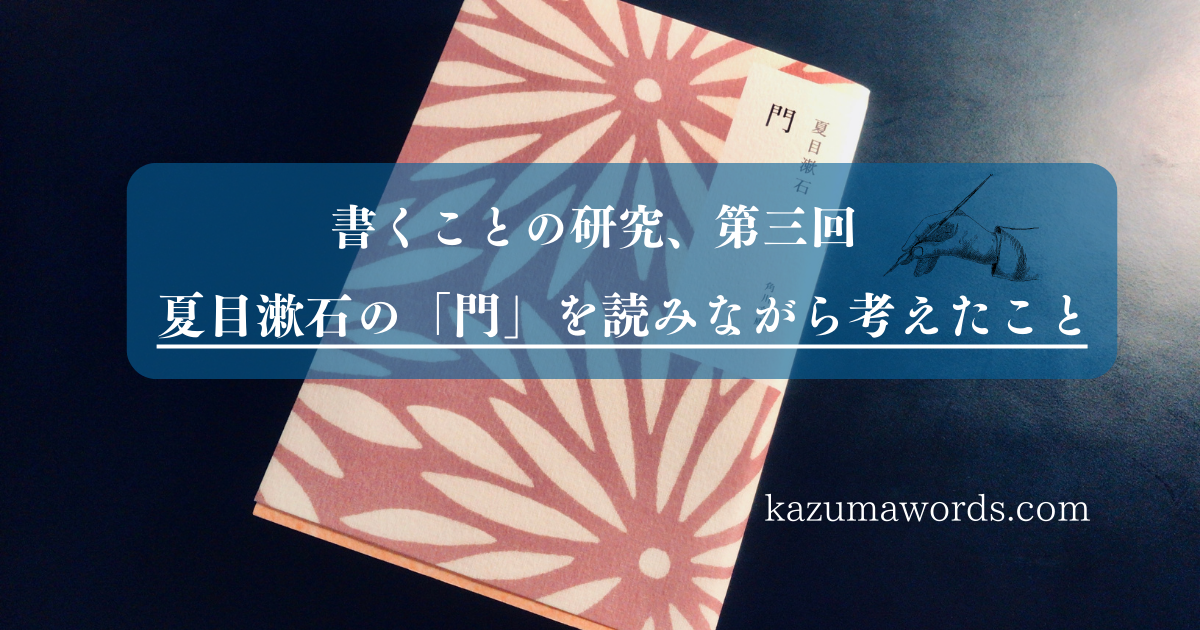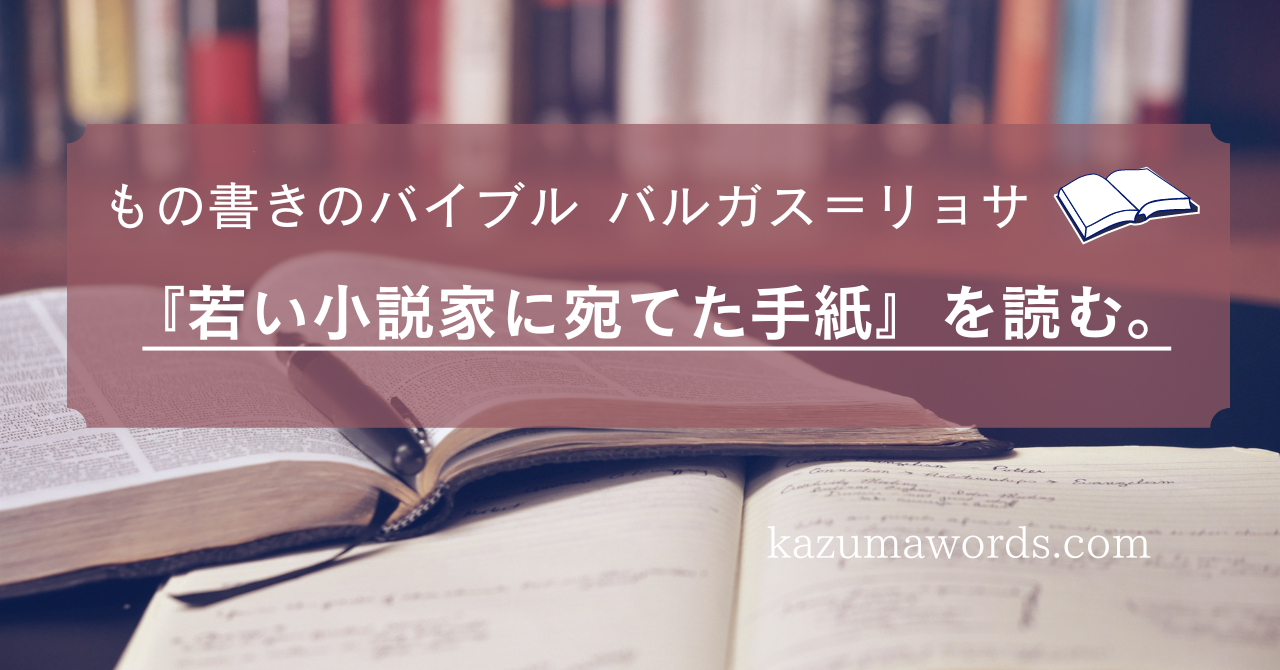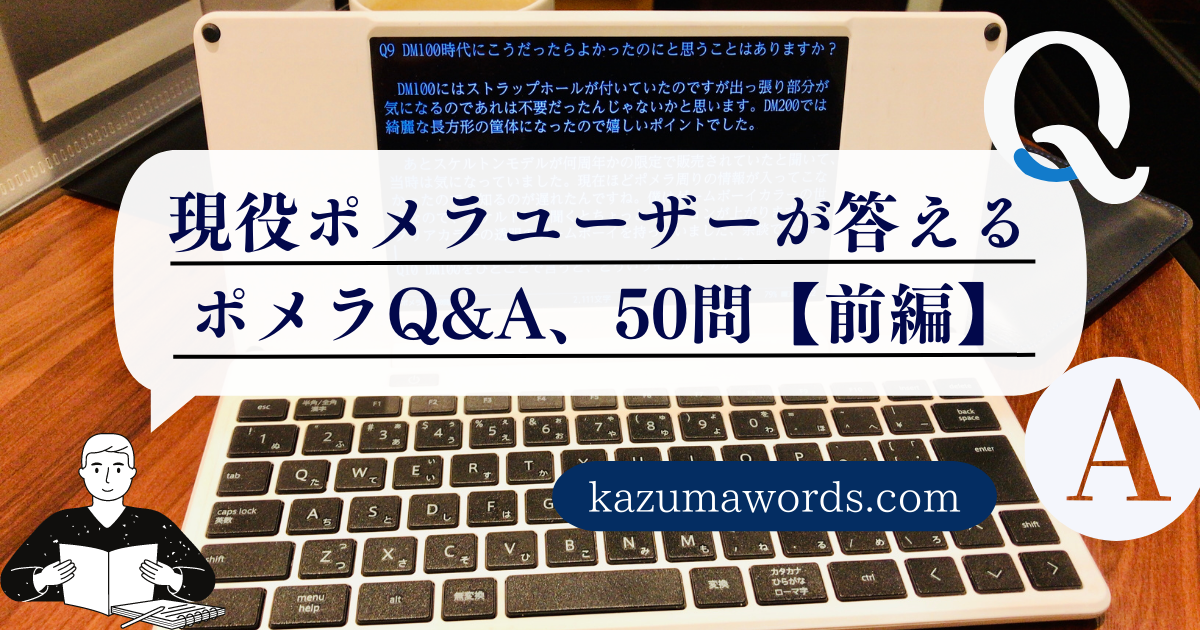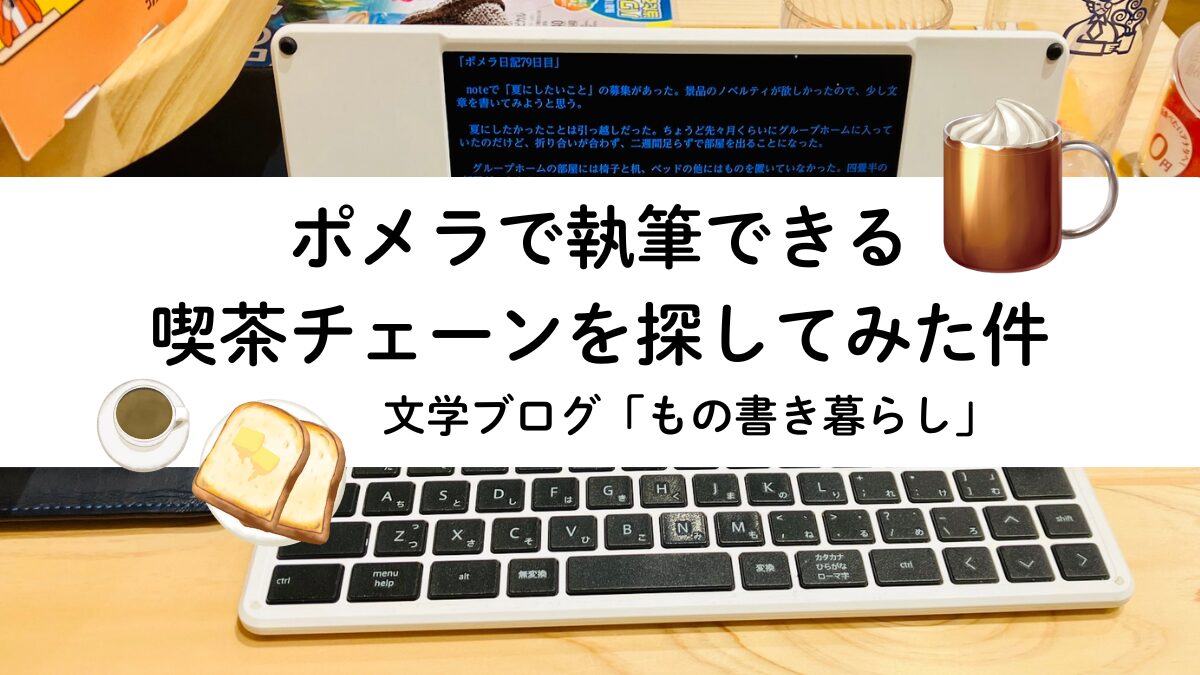なぜ、読み手に分かるように書く必要があるのか?

小説は読み手に分かりやすく書く必要がある?
もの書きのkazumaです。書き方の研究、第四回は「なぜ、読み手に分かるように文章を書く必要があるのか」についてです。
この問いは、僕が小説を書くときにけっこう昔からつまずいていた問題なんです。
どうして読者に分かるように文章を書く必要があるのか、と言われたら、そんなの読者が読むものだからでしょ? 当たり前のことじゃないか、と思われがちですが、この問いについてはいくつか切り分けて考える必要のある問いだと僕は考えています。
たとえば、よく巷に出回っているような文章指南の本には、常に相手に分かりやすい言葉を使って簡潔に書くのがいいとか、基本的に一文は短く区切って書くものとか、まあまあ出鱈目なことが書いてあって、そもそもなぜ読者に対して分かりやすく書くべきかということについて、その前提から疑ってかかったものって少なかったりします。
今回の記事では、読み手に対して分かりやすく書くとはどういうことか、小説において分かりやすく書くことは常に最善であると言えるのか、という疑問について掘り下げてみましょう。
誰かに読まれることを想定しなければ、アウトサイダーアートに近付くという話
僕が小説を書きはじめた頃、作品に対する感想でよく言われていたことは「文章が独り善がりだ」ということでした。
というのも、僕には自分の作品にも読者がいるということの実感が限りなく薄くて、作者である僕だけが分かっていればいいや、百歩譲って、自分と似た感覚の持ち主にだけ伝わればいいやと思って書いていたところがあります。
相手に伝えようと思って書いたわけではなくて、自分に宛てて小説を書いていたんです。
すると、自分の中では確かに通じている表現だけれども、読み手には決して伝わらない表現というものが作品のなかに現れることになります。
こういう風に誰かに読まれることをほとんど想定せずに書かれた物語というのは、アウトサイダーアートの範疇に近い表現であって、それも一種の表現であることには間違いはないけれど、少なくともひとに読ませるような代物ではなくなってしまうんですね。
読者を最初から想定しないような表現をしたいのであれば、そもそも作品を公開する意味っていうのはほとんどないんです。
たとえ日記文学のようなものであったとしても、誰かに読まれうることを想定した作品だけが文学として残っています。
つまり、一般的な意味での文芸作品っていうのは、どんな形式で書かれたものであれ、誰かに読まれることを前提に書かれた物語、ということになります。
「誰にでも分かりやすいこと」は文学のなかにはない
では、なぜ分かりやすい文章を書く必要があるのか、について見ていきましょう。
現代では「誰にでも分かりやすいことはいいことだ」と考える風潮がありますが、小説で描かれることって、実はその真逆なんですね。
「誰にでも分かりやすいこと」って文学のなかにはないんです。
たとえば、芥川の『羅生門』の内容をちょっと思い出してみてください。
雨降りのなかで下人が待っている。下人は明日の食い扶持もままならない人間で、雨が降りやむのを朱雀大路で待っている。
下人の目の前にあるのは、明日には餓死するか、それとも盗人になるかという二者択一の問いで、手段を選んでいるような余裕はない。しかし下人には、盗人になってまで生きていく決心が付かずにいた。
そんな下人が寝床を探すうちに死体のある屋上で妙な老婆を見つけてしまった。話を聞けば、この老婆も困窮のために死体から髪を奪って、鬘(かずら)を作って食いつなごうとしている。その死体になった女はもともと商場で危険な蛇を売っていたような女で、生きるためにはそうするしかなかったという。
だから老婆はこの女の髪を引き抜いても、この死体である女には許されるだろうと考えている。
そんな説明を老婆から聞いた下人は、この理屈に納得して老婆の着ている服を奪って盗人となる。老婆の論理で行くなら、生きるための悪なら許される。
この話を読んで、おそらく芥川はこれらの登場人物の倫理観を問うてはいるけれど、なにが善で、何が悪かなんていう構図の決まった、分かりやすい話はしていないんですね。
下人や老婆や死体の女のしたことを「仕方のないこと」と考えるかどうかは、あくまでも読者に委ねられているんです。
つまり文章を書くときの「分かりやすさ」っていうのは二種類あって、誰もが読みやすいような形の文章に整えるという表面上の「分かりやすさ(読みやすさ)」の話と、物語の筋やそこで語られている内容の「分かりやすさ(型があるかどうか)」の二つの次元があるんです。
文章としては万人が読みやすい文章で書かれていながら、かつその内容については一切の理解が及ばないということは両立しうるんです。
多くのプロがインタビューなどで答えている「読者にとってなるべく分かりやすい(平易)な言葉を選ぶことを心がける」って言うのは、あくまでも文章が読みやすいかどうか、という形の話であって、そこで語られている物語そのものが分かりやすいかどうかっていうこととは、また別の話なんですね。
もしこれを読んでいるあなたが、エンタメ作家になって商業的に売れることを目指しているとか、文学賞でも一発取って、華々しくデビューして小説一本で喰っていきたいとか、そういうこと考えているのなら、僕がここで長々と書いていることは何の役にも立ちませんので、いますぐブラウザバックして、このページを閉じてください。
簡潔に書くことが、小説において常に善であるとは言えない
僕が書きはじめた頃に危惧していたのは、そういう読者にとって「分かりやすい」表現だけを求めていくと、表現が画一的になってきて、最終的にはどれも似たような表現方法ばかりにならないかと考えていました。
たとえば、ヘミングウェイが文章とは簡潔に書くべきものだ、と言ったとします(べつにスティーブン・キングだろうが、村上春樹でも構いません)。
それを聞いたもの書きが感銘を受けて、じゃあ文章は何でも簡潔に書けばいいんだ、と考えて、みんなその通りにやり始めたとしたらどうでしょう?
ヘミングウェイっぽい文章とか、村上春樹っぽい文章とか、要するに他の誰かの有名作家が言ったことにただ従うだけなら、二番煎じのものしか出来上がらないわけです。
ヘミングウェイにはヘミングウェイの考えや美学があって、それを小説で表すときには簡潔な表現以外にはあり得ない、と考えたからそう書いただけであって、その結論の部分だけ持ってきて、じゃあ文章はおしなべて簡潔に書かなければいけないかというと、そうではありません。
ヘミングウェイの文学論は、厳密にはヘミングウェイにしか役に立ちません。村上春樹の比喩を忠実に模倣したとしても、村上春樹にはなれません。当たり前の話です。
スティーブン・キングが受動態と副詞を使うなって『書くことについて』のなかで言ったとしても、あなたに何か別の考えがあって、それを使うだけの理由が小説のなかにあるなら、スティーブン・キングの忠告を真に受ける必要はないんです。
たとえ言った相手がどれだけ有名で影響力のある作家だとしても。
僕は語ろうとする物語が要求してくる言い方や表現の形式があると考えていて、物語の内容と形式に分けて語るのは難しいんじゃないかと思っています。
たとえば、何年もある部屋のなかに意識的に閉じこもっている中年の男を主人公に据えたとします。
こうした男の意識を描こうとしたときに、簡潔で明晰な文章で書こうとするとどうもそぐわないという気がします。
三人称で外側から男を観察するように描いてもいいですが、あえて一人称という形で行くなら、男の過剰な意識を表すために文章のテンポを長く取ったり、読点を打つ間をわざと外したり。
脈略のない思考のために独白の最中に意味のない脱線をしたり、部屋の外側の音に異常に敏感で、通常では聞こえない音を拾うことができたり、ということを表現するのがふさわしいように思ったりします。
こういうときでも簡潔に、一本槍な調子で書いたとしたら、この中年男の語りに説得力や真実味がなくなってしまいます。
「分かりやすさ」から新しい文学は生まれない
僕は作品として誰もが読みうる可能性があるように平易で「読みやすい」文章を書く必要があると考えてはいますが、その話の内容や語り方まで「誰にでも分かるように」書く必要はないと考えています。
読み手にとって「分かりやすい」表現っていうのは、極端に言うとどこかで見たことのある、既に型ができてしまっている表現のことで、もう誰かが既に一度やってしまった表現なんです。
そして、そういう作品は大衆に受け容れられて一時的に支持されることはあったとしても、文学的に新しいことをやったと見なされることはありません。
つまり「誰にでも読みやすく」「誰にでも分かるような」型通りに書かれた文学は、既製の価値観のなかで作られてしまった文学であって、たとえ本人が書いたものについてそう思っていなくても、先行する作品に追従する文学とみなされてしまいます。
純文学の作品を読むときに、どこか筋から外れたような、あるいは関節を外したような作品が多いのは、そういった従来の型からなんとか逸脱しようと試みているからで、その逸脱の仕方が独創的であればあるほど、芸術的に価値のある表現だと見なされる傾向にあります。
もしあなたがエンタメのような大衆文芸ではなく、新しい文学の表現領域に挑戦したいというのであれば、誰かの言った方法論に従うのではなく、自分で独自にその方法論と文体とを確立しなくてはなりません。
いままでに誰もやったことのない作品の書き方を模索するわけですから、象を針の穴に通すくらい難しいことをやるわけです。
むろん、いま僕がここで言った「象を針の穴に通すくらい」というような陳腐な表現は、新しい文学作品を打ち立てようとするときには使うことができません。
もう既にそれは、誰かが言った、手垢の付いた表現であるからです。
だから純文学的な作品を書こうとするときに、作家志望のほぼ全員が頭を抱えることになるわけです。
誰も言っていないような語り方など、存在するのかと。どうすれば自分だけが表現しうるものに辿り着くのかと。
もしそれをたったひとつでも見つけられたら、あなたはそのときに紛れもない作家になります。
2023/05/17 16:39
kazuma