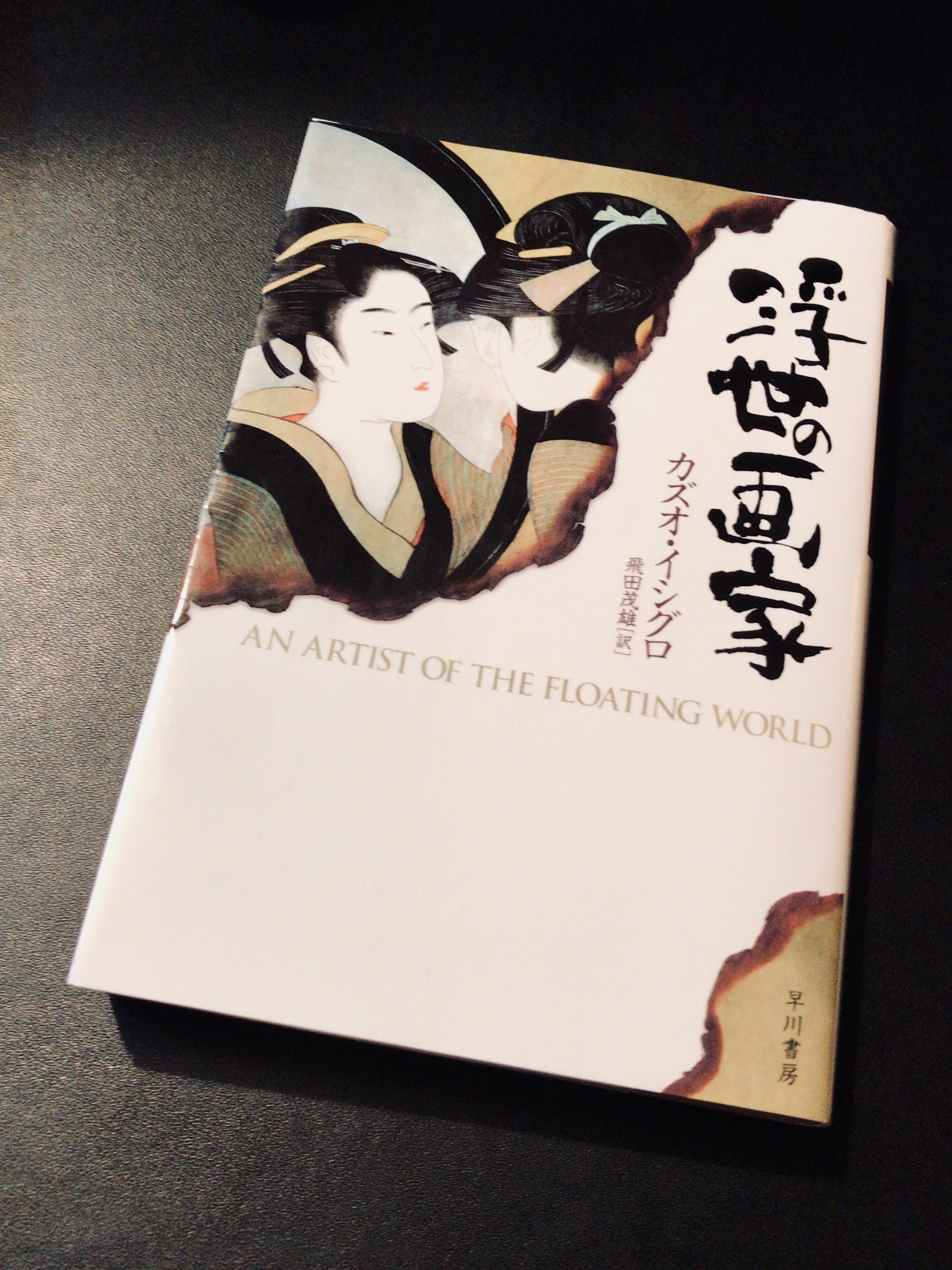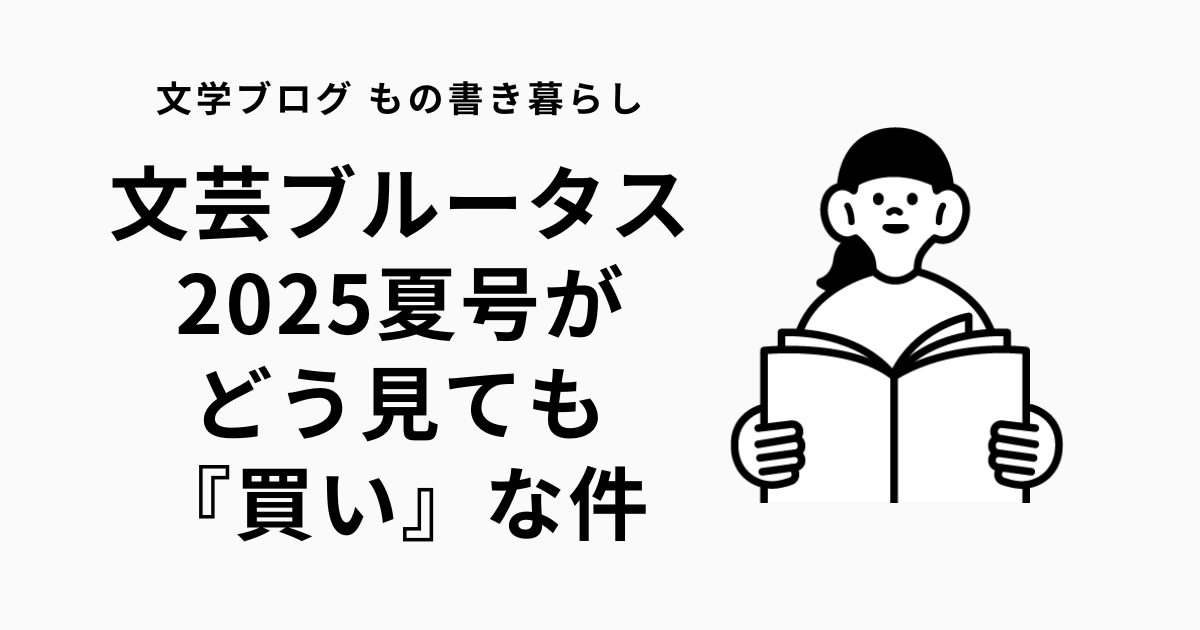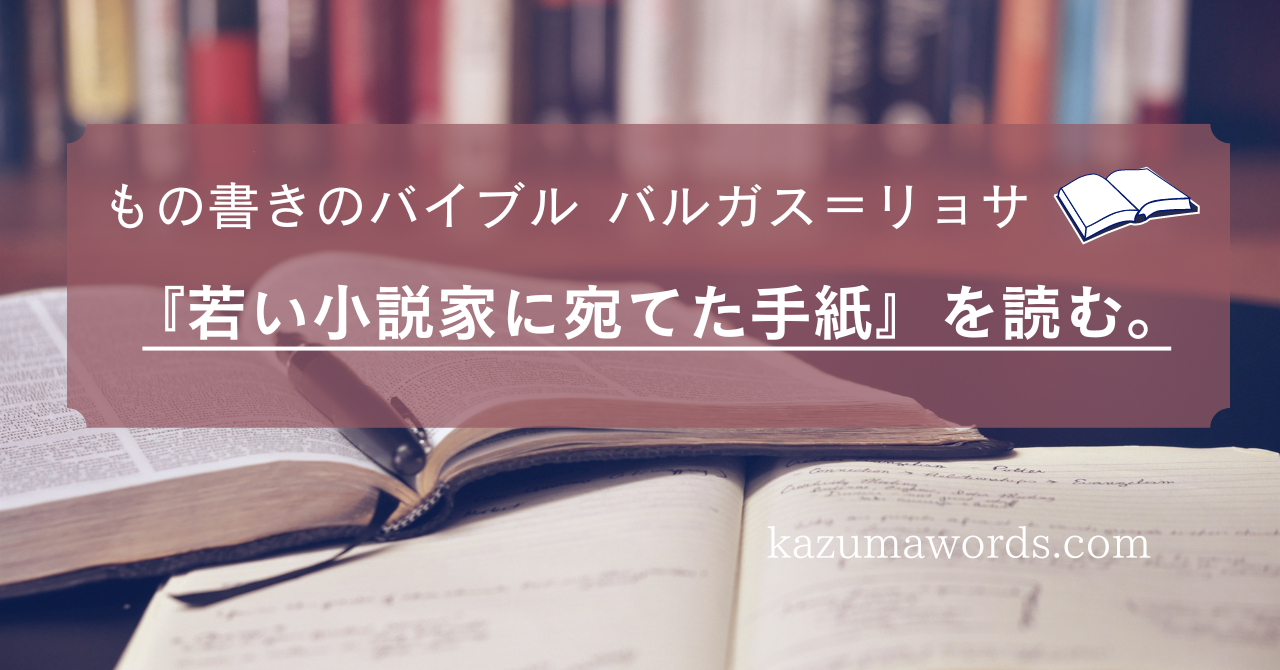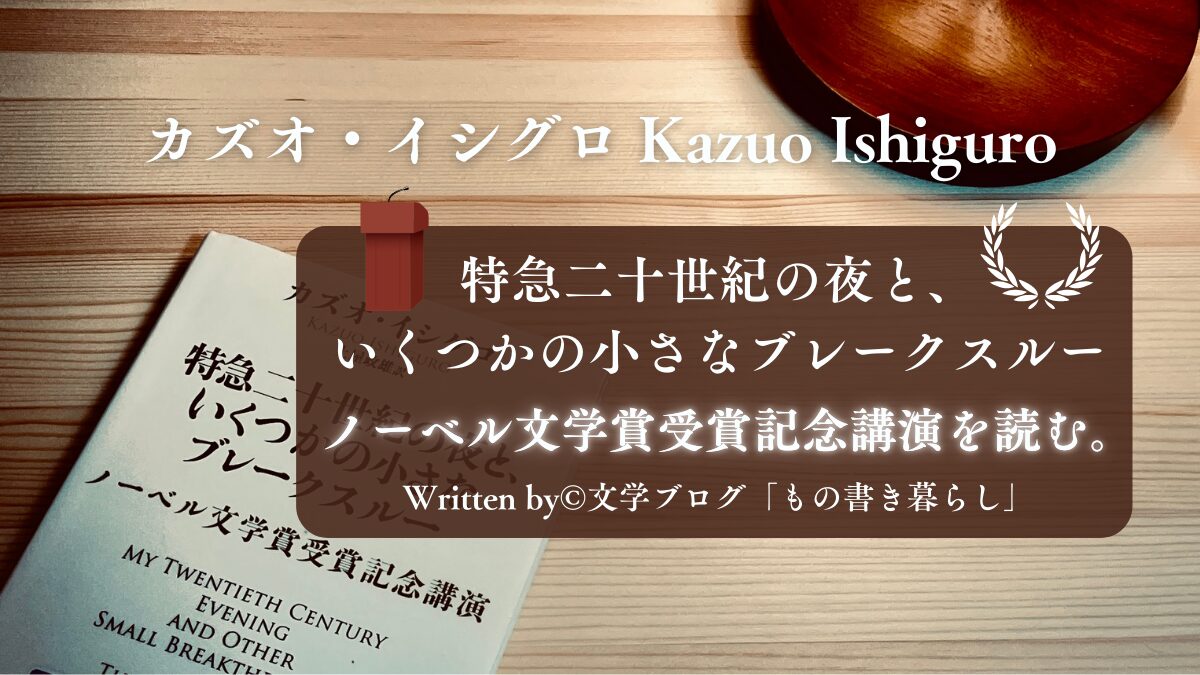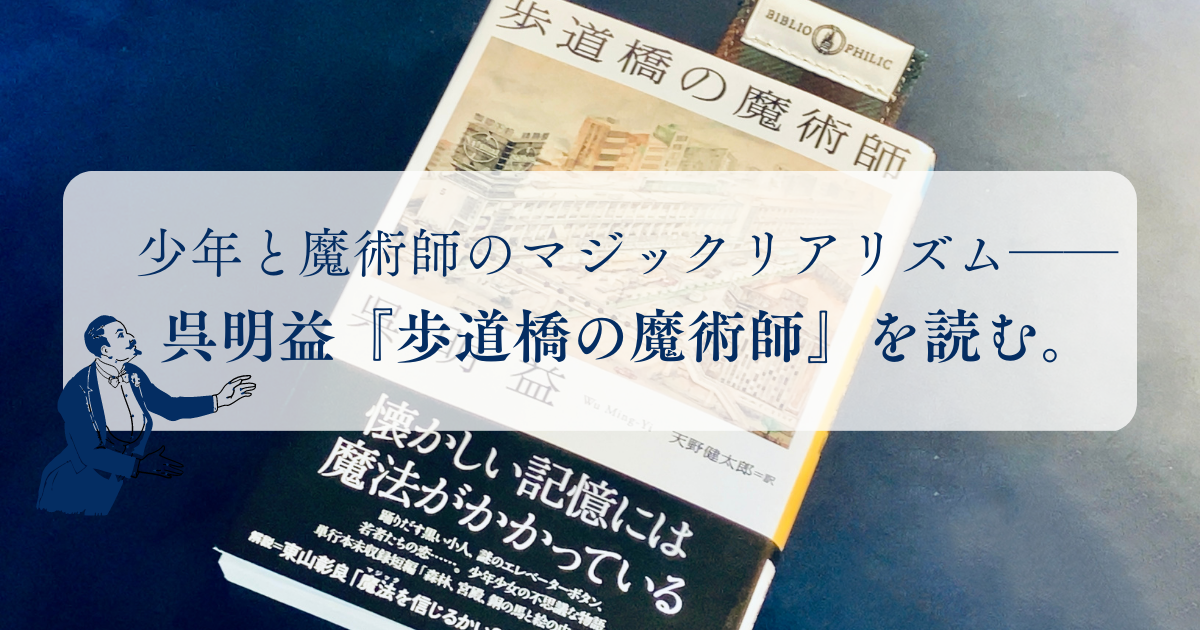「もの書くひとのリアリズム──アニー・ディラード『本を書く』」

アニー・ディラードの「本を書く」を読みまして。
どうも、kazumaです。今回、取り上げるのはアニー・ディラードの『本を書く』。もの書きならきっと興味が湧くと思う、他の書き手がどのように執筆に向かっていて、何を考えて文章をつくるのか。
あるいは自身が書き手でなくとも、作家がどんな生活を経て作品を生み出すのか、気になる人はいるんじゃないかな。僕もそのひとりだ。もの書きであるか、そうでないかにかかわらず、芸術作品がどのように生まれてくるか、そこに秘密はあるのか、ないのか、あるとすればなんなのか。
アニー・ディラードは答えてくれる。ただし答えそのものを示すのではなく、ものを書く生活そのものを読者の前に提示することによって。
作家の仕事場=書斎はどこか?
最初に言ってしまえば、ものを書くことに秘密などない。それは書き手になればわかる。見つけなければならない主題はすでに書き手のなかにある。問題はどうやってそれを見つけるかだ。
アニー・ディラードはこの本の第一章のなかで、もの書きにとっての仕事場、つまり書斎についての話をしている。
魅力的な仕事場は避けるべきである。部屋には眺めなどいらない。そうしておけば、想像力は暗闇の中で記憶に出会うことができる。この小屋を七年前に書斎にしたとき、私は長い机を殺風景な壁に押し付けた。
引用元:「本を書く」アニー・ディラード著 柳沢由実子訳 田畑書店 第一章 p.13
僕はもの書きに必要なのは壁だと思う。それは現実的な意味合いにおいても、精神的な意味合いにおいても。
僕はもうずっと長いこと、白い壁に向かってタイピングしつづけていて(いまではいたるところに窪みと焦げ付いた色合いの染みがある)、それが当たり前になってしまった。
だからアニー・ディラードの言っていることはなんとなくわかる。
小説を書くためにわざわざ小洒落た喫茶店にまで出かけて行って、いちいち長ったらしいコーヒーの名前をオーダーする必要はない(これは僕の意見)。
棺桶一つ分のスペースさえあればひとは本が読めるし、物置ほどのスペースがあれば人はものが書ける(これはアニーの意見)。
そういうストイックな、硬派なところに共感して、僕はこの本を読み進めることにしたのだった。
もの書き生活のスケジュール、アニーの場合
アニー・ディラードは『ティンカー・クリークのほとりで』という本を書いている。
僕はアニーがどんな文章を書いているのか、まったく知らないが、もの書きの生活について彼女はこんな風に記述している。
私は正午まで眠った。やはり作家である私の夫もそうした。午後ちょっと書き、早い夕食後、散歩をしてからまた書いた。その数ヶ月間、私は夕食とコーヒーとコカコーラとチョコレートミルク、そしてマールボロのヴィンテージ(煙草)しか摂らなかった。夜中の一時か二時まで働いて、家に帰ったころにはくたくたになった。
引用元:「本を書く」アニー・ディラード著 柳沢由実子訳 田畑書店 第一章 p.14
画に描いたような、不摂生なタイプのもの書きだ。僕はこんな生活を続けたら身が保たないんじゃないかと思うけれど、アニーにはアニーのリズムがあるらしい。
ものを書くという行為は、生物的に見れば極めて不自然な行為だと思う。何時間も椅子に座って、ノートの前でペンを握り、PCの前で手を組み合わせ、キーを叩いてはうなされているのだから。
動物としては完全に余剰行為、健全な社会生活を営む上ではまったく必要のないことを、もの書きは絶えず行っている。
ときに個人の健康や社会的生存よりも執筆を上に置く。そうまでして言わずにはいられない、書かずには済ませられない、そういう種類の人間がもの書きになる。
日々の生活のなかで、本を書く時間と読む時間、この二つを捻出しなくてはならない、できることならぼうっとものを考える時間も、最初の一文が降りてくるまで机の前で待つ時間も。
気分転換だって必要だ。書く生活にはリズムが伴う。書くことを見つけたかったら、書くリズムを見つけることだ。
何も机の前でうなされているだけがもの書きじゃない。ノートを広げ、PCやポメラの電源を入れて、席に着く。そのずっと前から書くことははじまっていて、自分がもっともよく書けるタイミングで書き始められるように生活を持っていかなくてはならない。
ほかの誰でもない、自分だけのタイミングをつかまえるのだ。
一冊の本を書くには二年から十年はかかる。それが標準。
一冊の本を書くには、だいたい二年から十年の歳月がかかる。それ以下ということはめったにない。
引用元:「本を書く」アニー・ディラード著 柳沢由実子訳 田畑書店 第2章 p.52
アニーはこのように言っている。僕も同意見だ。ここで言っているのはひとつの完成された長編小説のことだと思う。
商業作家には年何冊ものペースで刊行する書き手がいたり、あるいはアマチュアにも同じように年に何度も公募の期限に間に合わせるように書く器用な書き手もいるけれど、僕は駄目だった。そういう風には小説を書けなかった。
締め切りがあるから書けるんだ、というひともいる。そういう意見はわからなくもない。僕だって過去にそうしてきた。でも、出来上がる作品はどこか無理やり刈り揃えられた芝生みたいに、不自然なまとまり方をしていた。
書き手の欲は作品に滲み出してしまう
アニーは、映画になることを考えて作られた作品は必ず腐ったにおいがする、と言っている。読み手はそれを嗅ぎつける。
賞を獲りたい、書いたものが認められたい、プロになりたい、褒められたい。そういう欲望がもし書き手のなかに疼いているのであれば、それは作品に自ずと現れてくる。
だから、まずそれを粉々に砕いて塵芥にしたところからはじめなくてはならない。誰にも認められなくてもいい、賞なんて獲らなくていい、プロになれなくても、作品をちっとも褒められなくていい。
それでも書くというのなら、そのときにはじめてひとはもの書きになるのだと思う。
世の中には二十になるかならないかの頃に華々しく賞を獲ってデビューする作家もいる。僕にも在学中に作家としてデビューした知人がいた。そいつの本が大学の生協に平積みにされているのを見たとき、憧れもしたし、悔しくもあった。
POPには作家としての名前が大きく記されていた。そいつはきっと誇らしかったろう。授業の合間にお祝いの言葉をひとこと言ったが、一方で、内心僕は惨めだった。
賞に応募したあと、文芸誌にちっとも載らない名前を、何度確認したかわからない。俯いたまま書店をあとにする。ぼんやりと横断歩道を渡る。ため息をつく。いっそ轢かれてしまえ──繰り返すことが次第に馬鹿らしくなった。
憧れも悔しさも惨めさも、どうでもいい。僕はただ、自分の文章をものにするまで書き続けることしかできないのだ。
SNSで持ち上げられたり、小説投稿サイトで人気を集めている作家をいいなと思うこともあるかもしれない。
でも、人気があることと、それが作品にとっていいことかは、別の話だ。
サリンジャーが書けなくなっていった原因のひとつは「ライ麦畑」が売れ過ぎたからだと僕は思っている。
アニー・ディラードの彩られた日々、作家は精神世界に生きてはいない
僕はアニー・ディラードのストイックなところに惹かれたが、それはとりもなおさず、これから書かれる文章のためだった。
ストイックだからといって、アニーの生活が〆切間際の缶ヅメ作家のようになっているわけではない。むしろその逆で、彼女の生活は色づいている。
執筆小屋にたどり着く小道で聴いた鳥のさえずり、図書館の閲覧室で出会った謎のチェスプレイヤー、ブラインドの羽根の間から見る独立記念日の花火、離島での薪割りに、洗濯バサミが付いたヤカン、発火したタイプライター、などなど。
作家は精神世界のなかで生きてはいない。街中を歩くひとと同じように外の空気を吸い、手を動かして働き、疲れたら眠る。
ただ他のひとびとよりもちょっとものごとの受け止め方が違う、っていうだけなのだ。それをきちんと覚えていて、しかるべき手順を踏めば、作家は身の回りにおきたどんな些細な出来事でさえ物語にすることができる。
彼女は本の中の世界で起こることだけじゃなくて、ちゃんと人生を知っている。
頭の中だけで小説を組み上げられるわけじゃないことも、付け焼き刃ではなんの役にも立たないことも。
アナログチックで骨折り損、何一つ思い通りにはならないこの人生からでしか、ものを書くことは学べない。そのことを彼女はよく知っている。だからこんなに執拗なまでに遠回りをして、ものを書くことの外側にある、もの書きの実際の生活そのものを描写しているのだ。
いままで、ものの書き方について指南する本は古今東西、数多とあったろう。
でももの書きの生活そのものについて取り上げ、そこに着目したのは現代ではアニー・ディラードただひとりだったのではないか。彼女の生活にはもの書きとしてのリアリズムが息づいていた。
まとめ:ものを書かずにはいられなくなる本。
アニー・ディラードの「本を書く」は、もの書きを焚き付けてくれる。ものを書くことの意味を見失ってしまったひとに、この本をすすめたい。最後に刺激的な一節をいくつか紹介して終わろう。
靴の売り子は──他の人のために働き、二人か三人の上司に答えなければならず、彼らのやり方で仕事をしなければならず、すべては彼らの命令どおり、場所も時間も彼らに合わせて働くにもかかわらず──人のために役立って働いている。さらに、もし靴の売り子がある朝仕事に現れなかったら、だれかが必ずそれに気がつくだろう。あなたが精魂込めて書く文章は、それ自体、なんの必要性も願望もない。それはあなたを知らない。世の中のほうも、誰もあなたの文章を必要としてはいないし、誰だって靴のほうをもっと必要としている。世の中にはすでに、価値のある、精神を高め人を感動させる、知性にあふれた力強い文章がたくさんある。『失楽園』が素晴らしいと思ったら、買いますか。ピストル自殺でもしたらどう? 実際、またもう一ついい加減な文章を世に送り出すくらいなら。
引用元:「本を書く」アニー・ディラード著 柳沢由実子訳 田畑書店 第二章 p.50
もしこの人生が本物の戦いでなかったら、その戦いで成功がこの宇宙に永遠に続くなにかをもたらさなかったら、人生は、いつでもその気になったら引き上げることができる、私的な芝居みたいなものだ。だがどうも人生とは本物の戦いのようだ。──ウィリアム・ジェイムズ
引用元:「本を書く」アニー・ディラード著 柳沢由実子訳 田畑書店 第六章(エピグラフ)p.132
どう? こんなことを言われてしまったら、書く気にならない?
kazuma